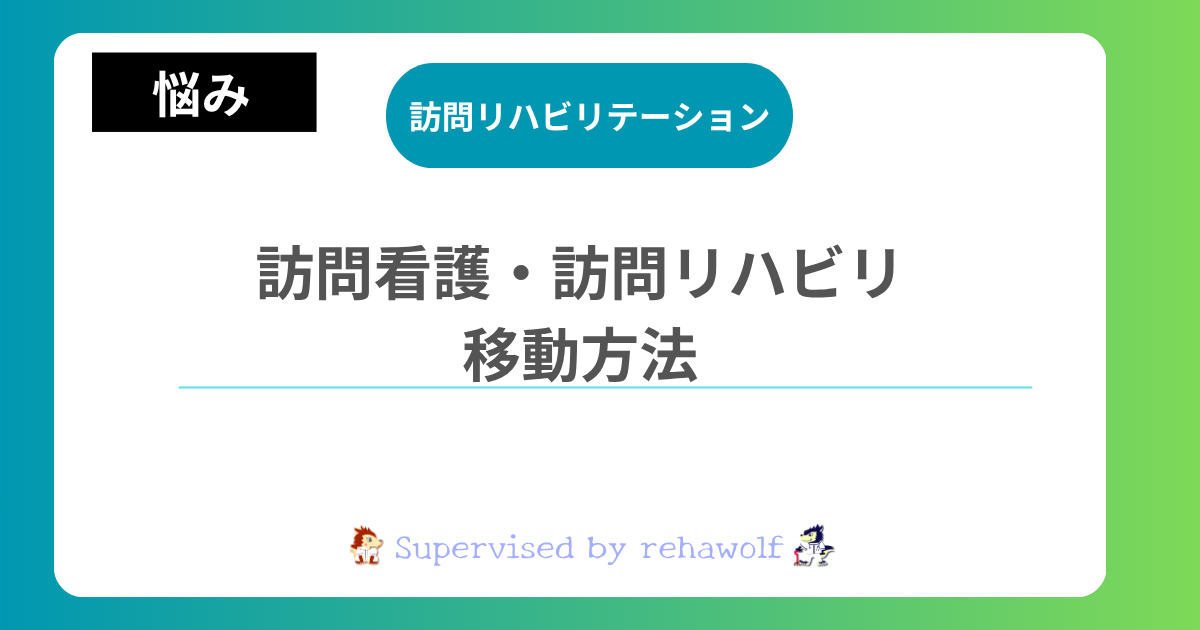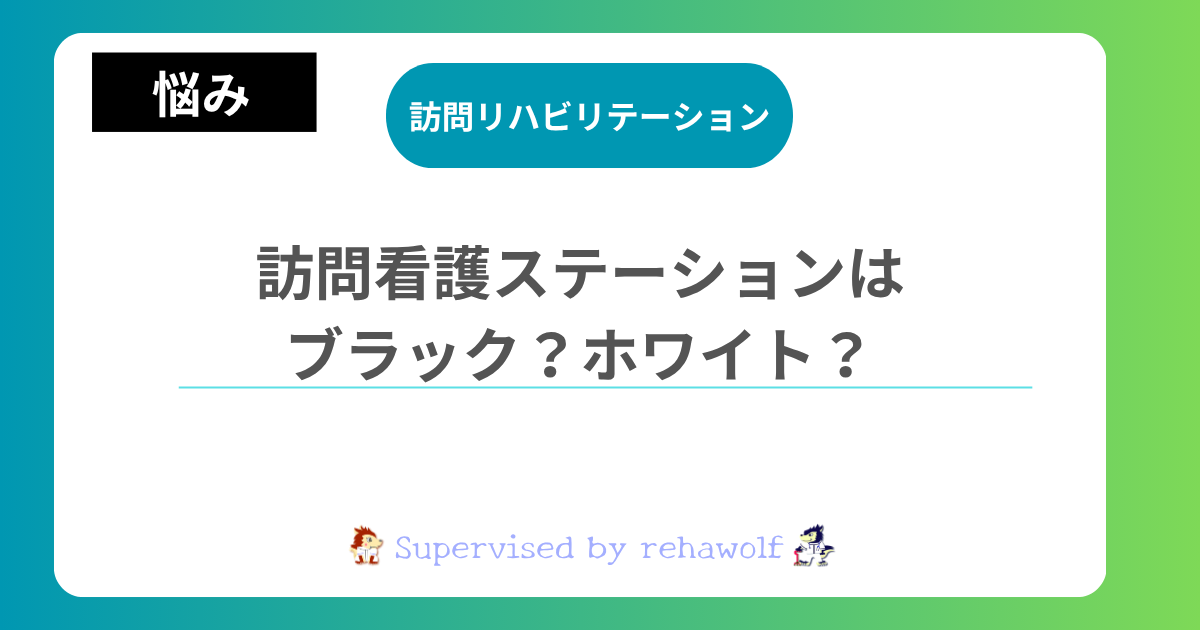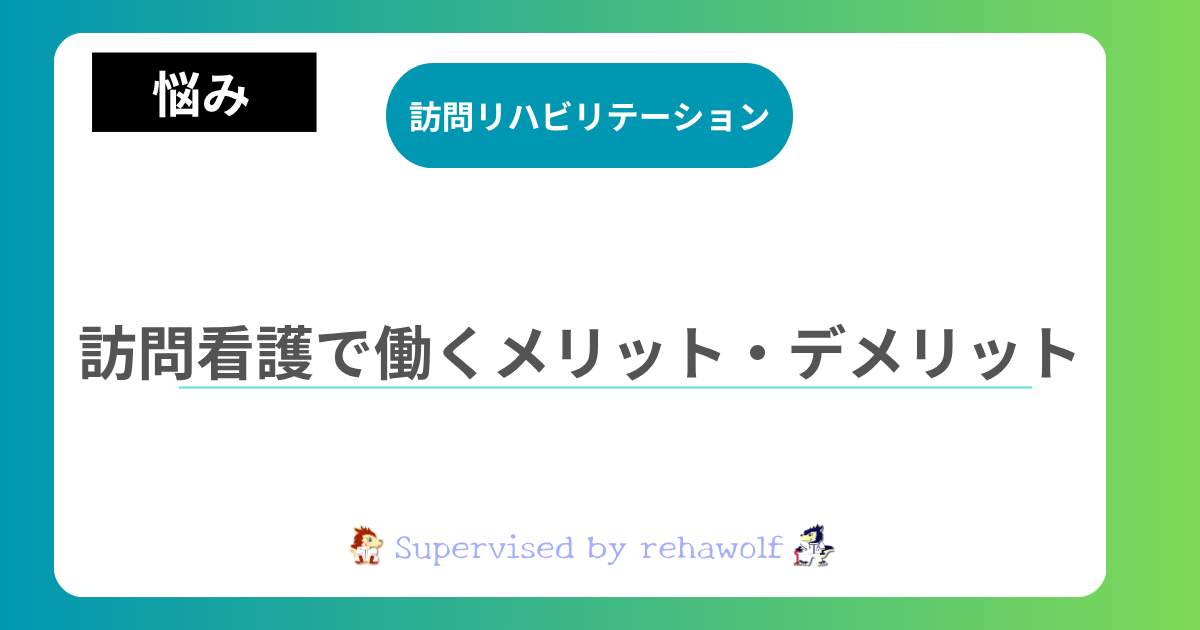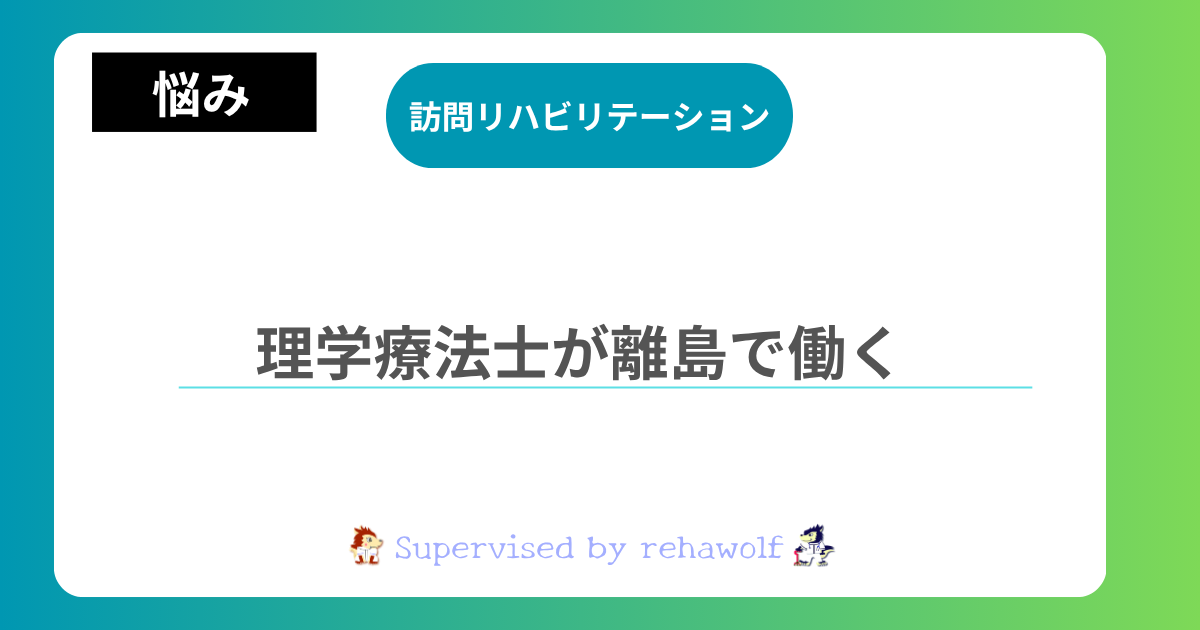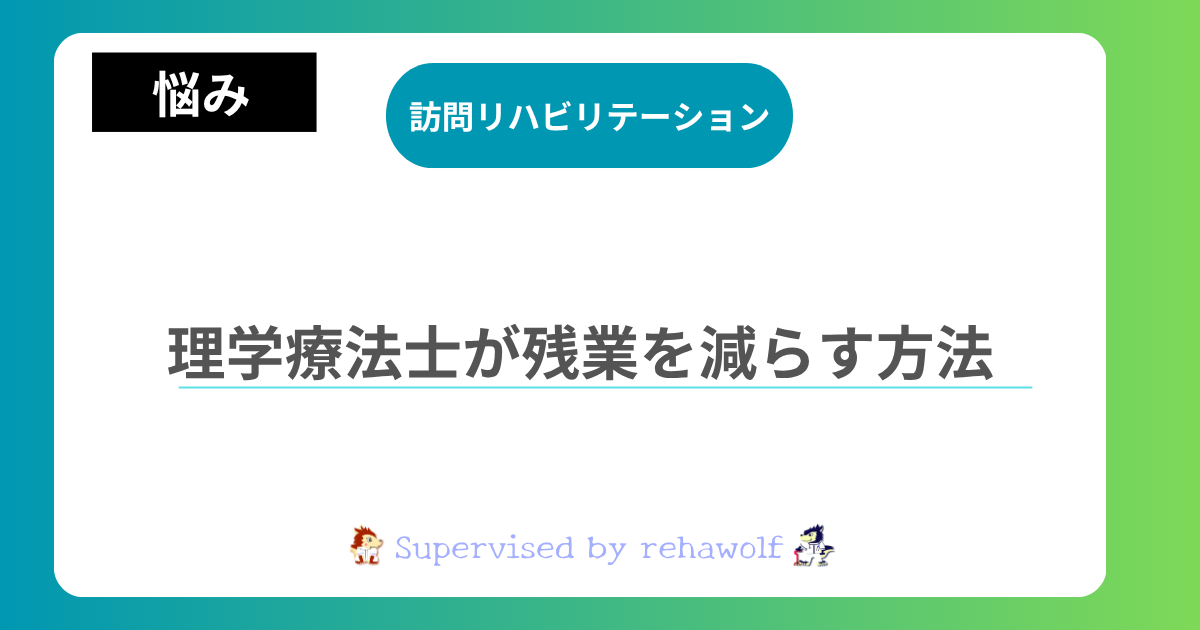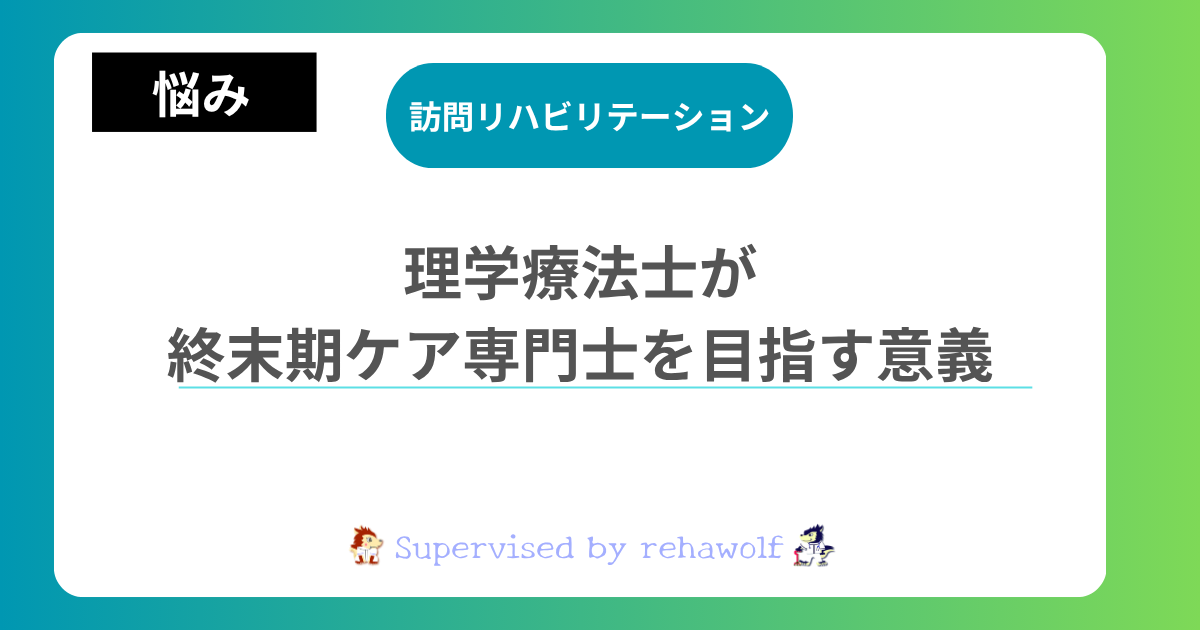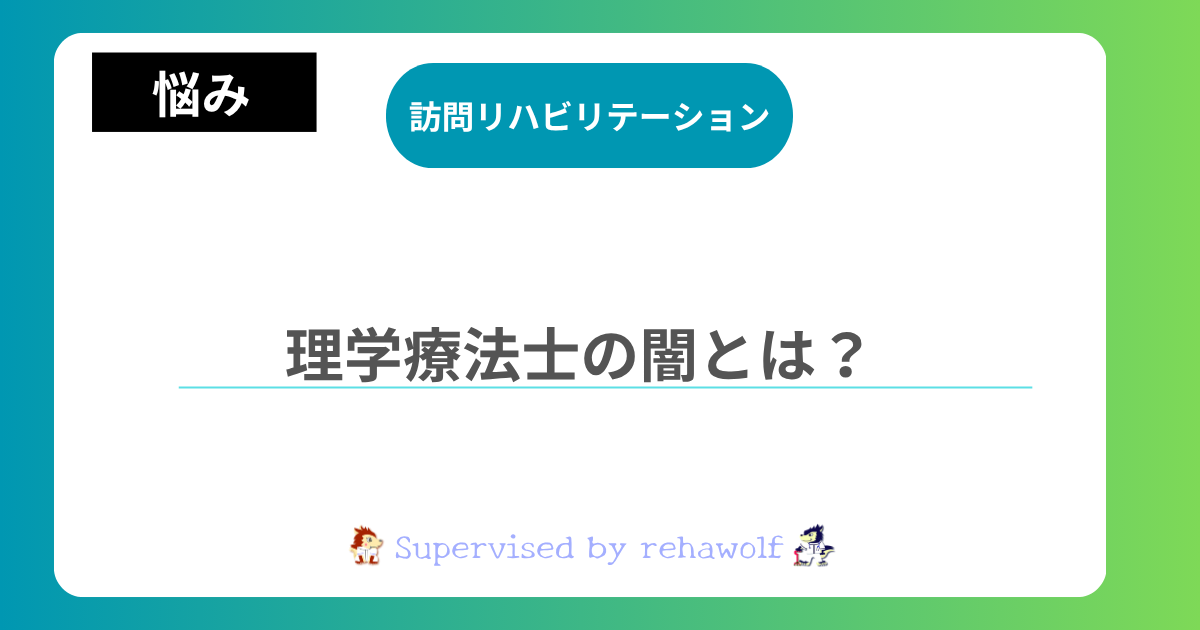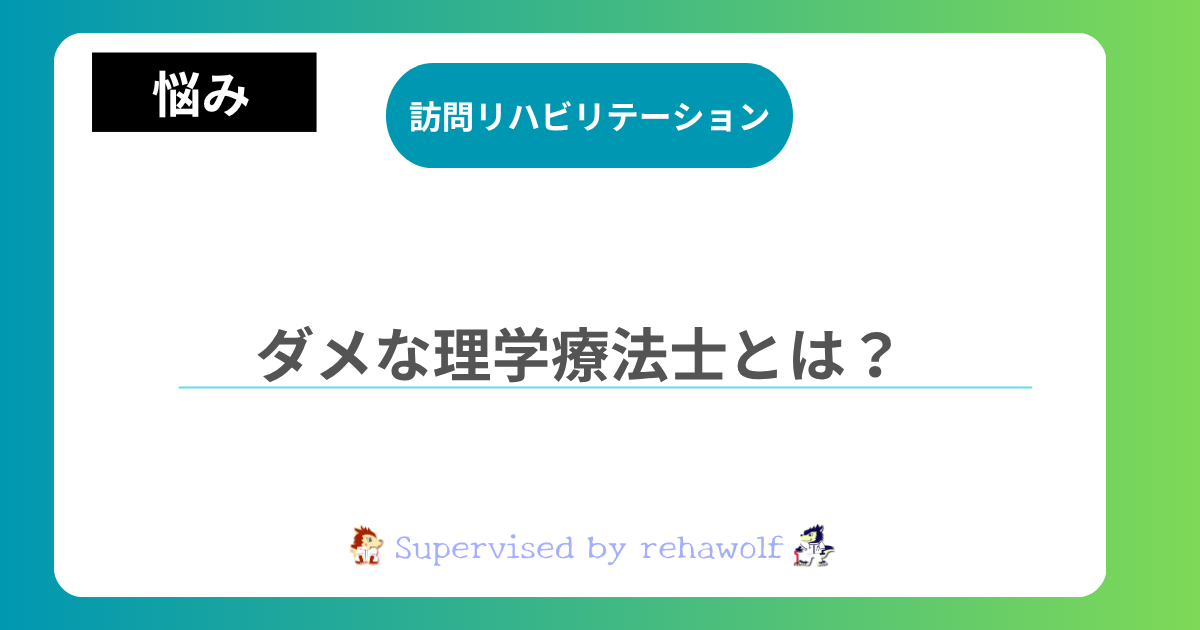訪問看護ステーションでリハビリ職が辞める理由とは?現場の実態と続けるための工夫
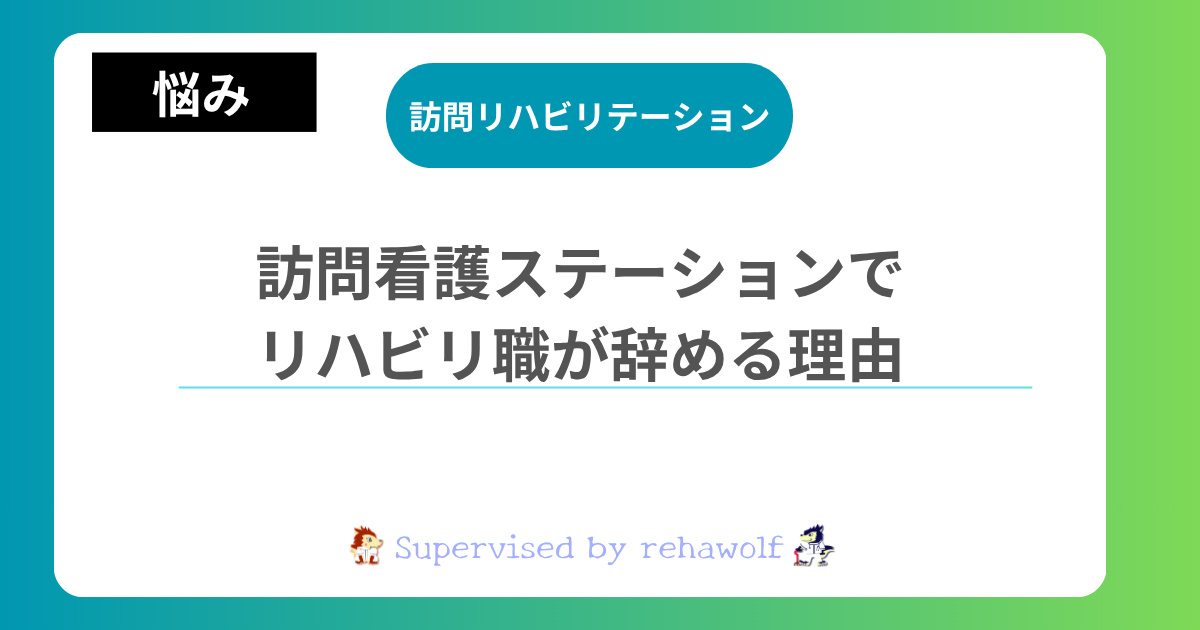
訪問看護ステーションは、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)といったリハビリ職にとって、在宅分野で活躍できる場として注目されています。
しかし実際には「長く続かず辞めてしまう人が多い」という声も少なくありません。
なぜ訪問看護ステーションではリハビリ職の離職が起きやすいのでしょうか。
この記事では、リハ職が辞める主な理由と背景を整理し、辞めずに働き続けるための工夫について解説します。
訪問看護ステーションでリハビリ職が辞める主な理由
1. 一人で訪問するプレッシャー
病院や施設と違い、訪問リハは基本的に 一人で利用者宅に訪問 します。
- 突発的な体調変化にどう対応すべきか不安
- 家族への説明や調整も一人で行う責任の重さ
このプレッシャーから「自分には向いていない」と感じ辞めるケースがあります。
2. 移動の負担と効率の悪さ
1日4〜6件の訪問を車や自転車で移動するため、移動時間のストレスは大きな要因です。
- 渋滞や天候の影響
- 移動に時間を取られ、1日のスケジュールがタイトになる
身体的にも精神的にも負担が大きく、辞める理由につながります。
3. 記録・事務業務の多さ
訪問リハは医療保険・介護保険の制度に基づいて提供されるため、計画書や報告書などの事務作業が多いのが特徴です。
- 「リハビリ以外の事務作業に追われる」
- 「記録が残業に直結する」
こうした不満が積み重なります。
4. キャリア形成への不安
病院勤務と比べて症例の幅が狭く、「スキルアップにつながらないのでは?」と不安に思うリハ職も少なくありません。特に若手は急性期や回復期を経験してから訪問に移りたいと考えることが多いため、早期離職につながるケースがあります。
5. 人間関係・組織体制の問題
小規模なステーションでは人員が限られており、人間関係がギクシャクすると居づらくなります。また、上司のマネジメント不足や経営方針への不信感が離職の原因になることもあります。
6. 給与や待遇への不満
訪問件数に応じた歩合制を導入している事業所もあり、件数が少ないと収入が安定しません。「働いているのに給料が見合わない」と感じ、辞める選択をする人もいます。
なぜリハビリ職は訪問看護ステーションを辞めやすいのか?
背景には次のような要因があります。
- 在宅分野はまだ若い領域 → 教育体制が整っていない事業所が多い
- 利用者宅という特殊な環境 → 病院勤務の延長では対応できない課題がある
- 需要の高さによる急成長 → 人材育成よりも人員確保が優先されがち
つまり、リハ職が辞めやすいのは個人の適性だけでなく、業界全体の未成熟さも影響しているのです。
辞めずに続けるための工夫
1. 教育体制が整った職場を選ぶ
- 新人研修や同行訪問が充実しているか
- マニュアルや相談体制があるか
求人の段階で確認することが重要です。
2. 自己学習を続ける
訪問リハの専門書やオンライン研修を活用し、スキルの不安を補うと自信につながります。
3. 無理のないスケジュールを交渉する
訪問件数が過剰でないか、事務時間が確保されているかを確認しましょう。
4. チームでの連携を大切にする
看護師やケアマネとのコミュニケーションを密にし、「一人で抱え込まない」ことが続けるコツです。
辞めたいと思ったときの選択肢
- 別の訪問看護ステーションに転職 → 体制が整った職場なら続けやすい
- 病院や施設に戻る → 再び臨床経験を積むのもキャリアの一部
- パート・非常勤で続ける → ライフスタイルに合わせて無理なく働く
「辞める=失敗」ではなく、自分に合った働き方を探すことがキャリア形成につながります。
まとめ
訪問看護ステーションでリハビリ職が辞める理由は、
- 一人訪問のプレッシャー
- 移動や記録業務の負担
- キャリアや待遇への不安
- 人間関係や組織体制の問題
といった多方面にあります。しかし、教育体制のある職場を選び、スキルや働き方を工夫すれば長く続けることも可能です。訪問看護の現場は在宅医療の重要な柱であり、リハ職の活躍の場はますます広がっています。辞める理由を正しく理解し、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。