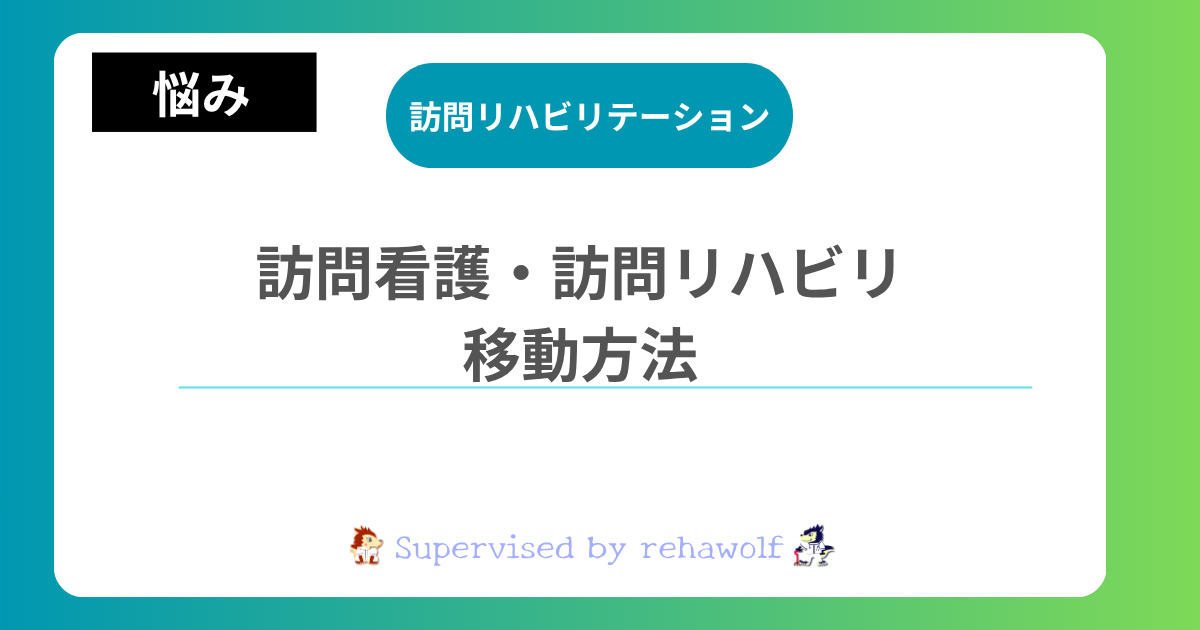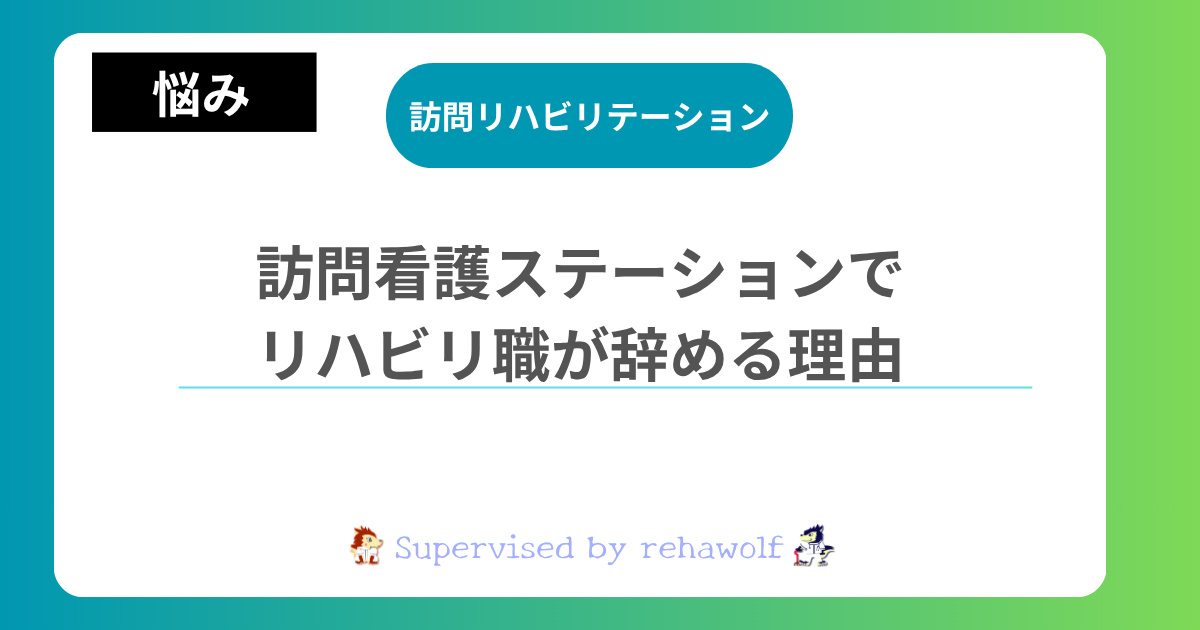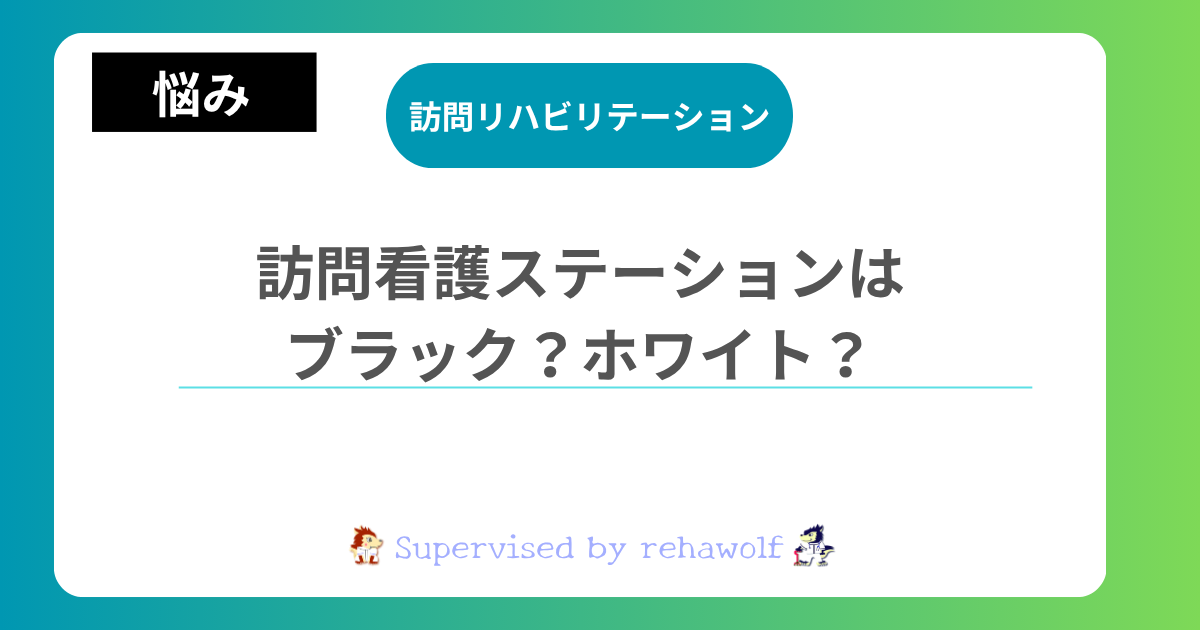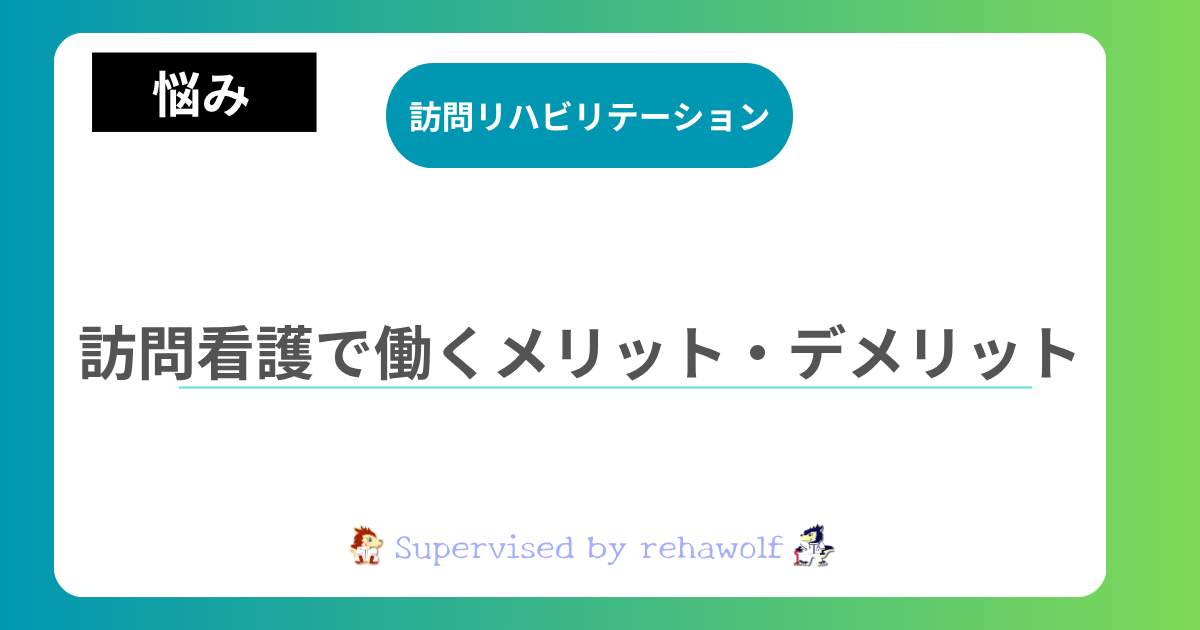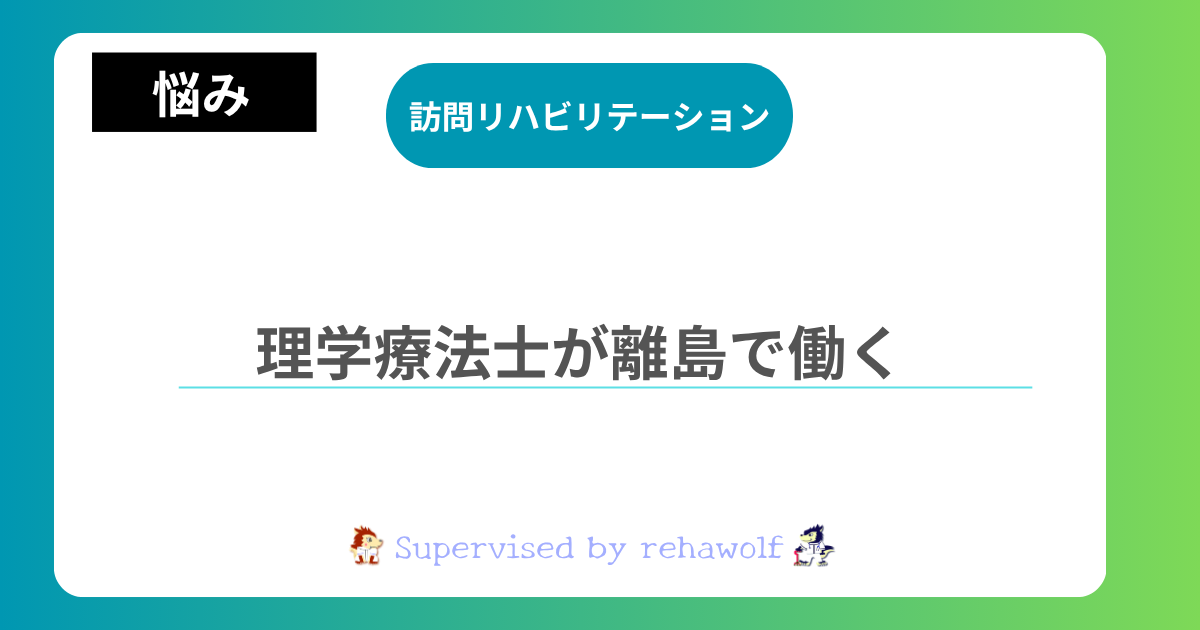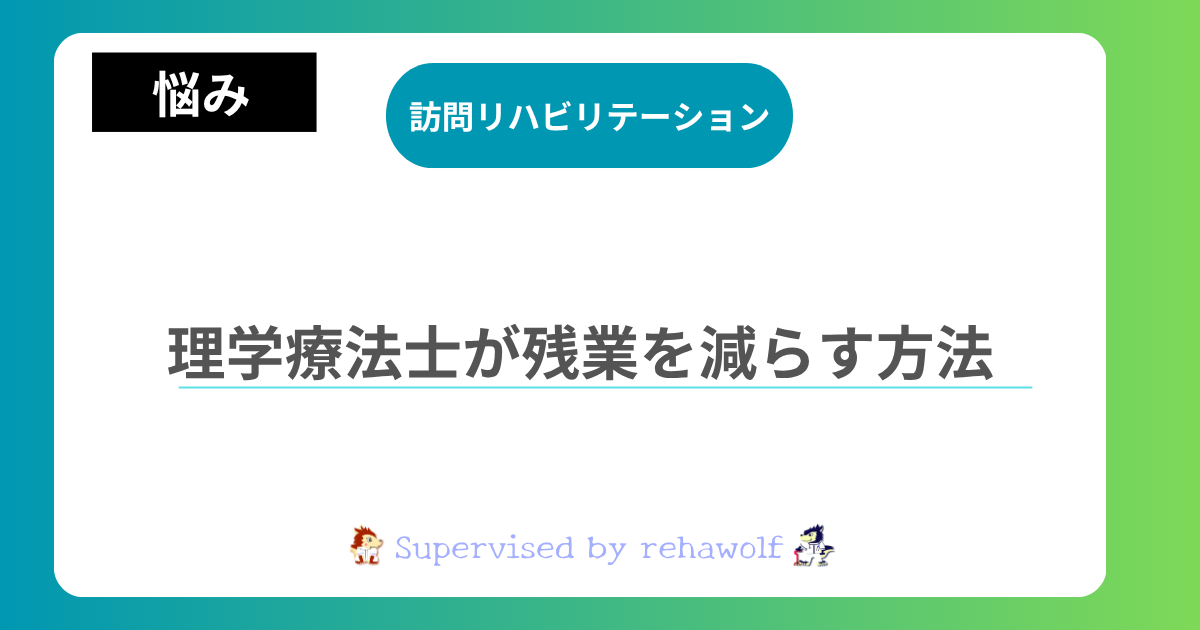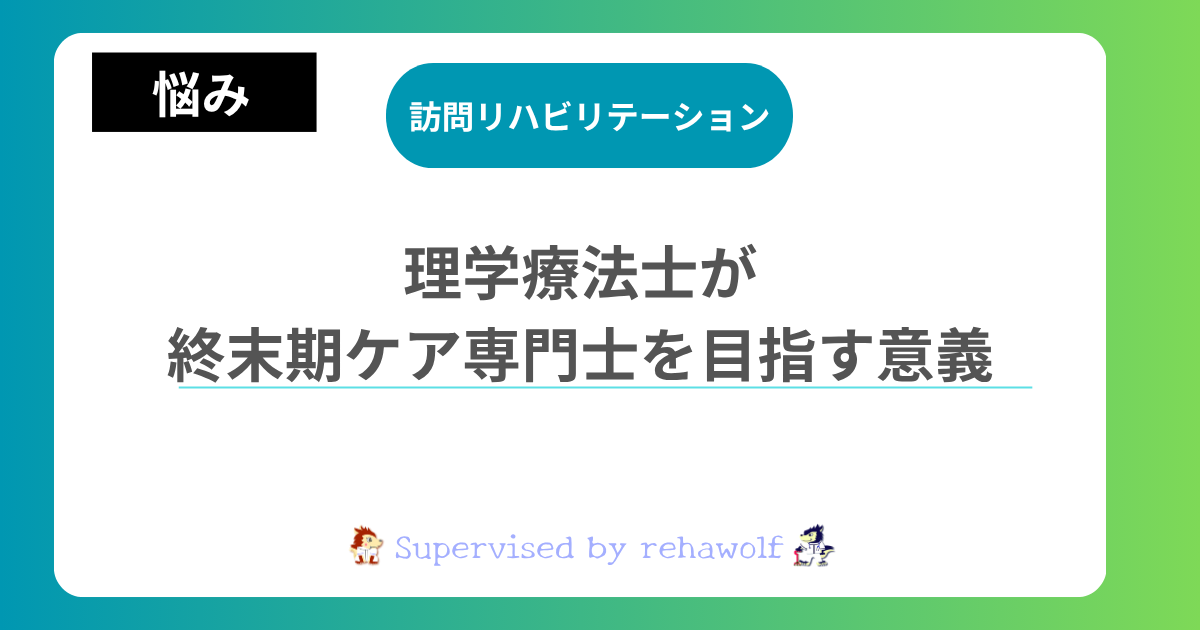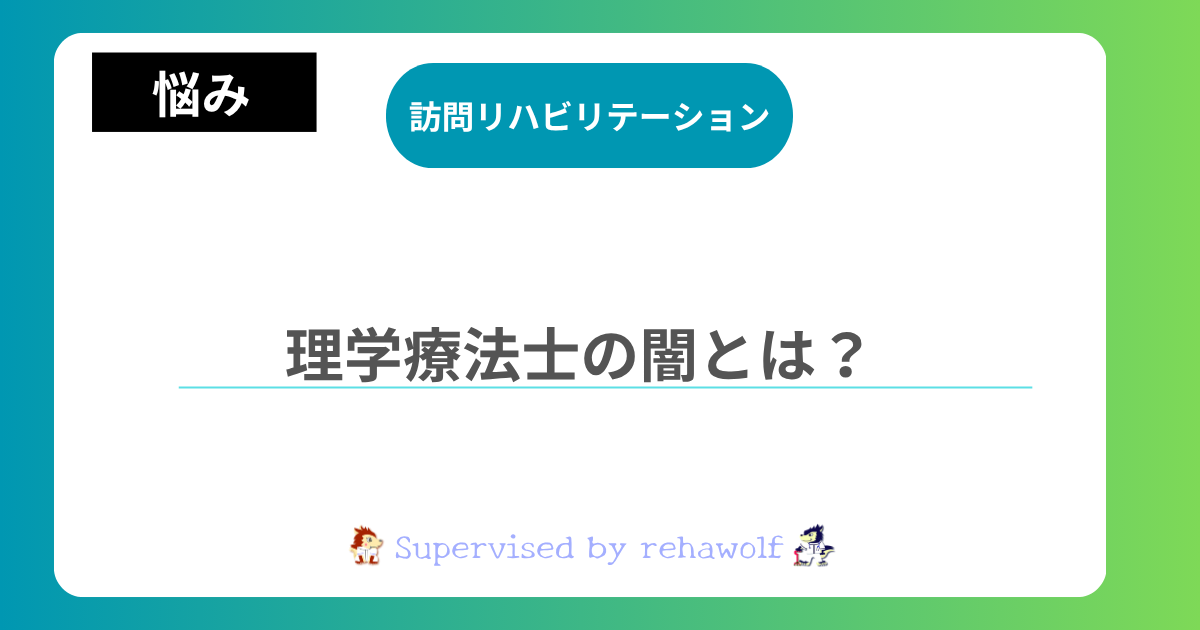60代の理学療法士の定年後の選択肢は何がある?おすすめを紹介
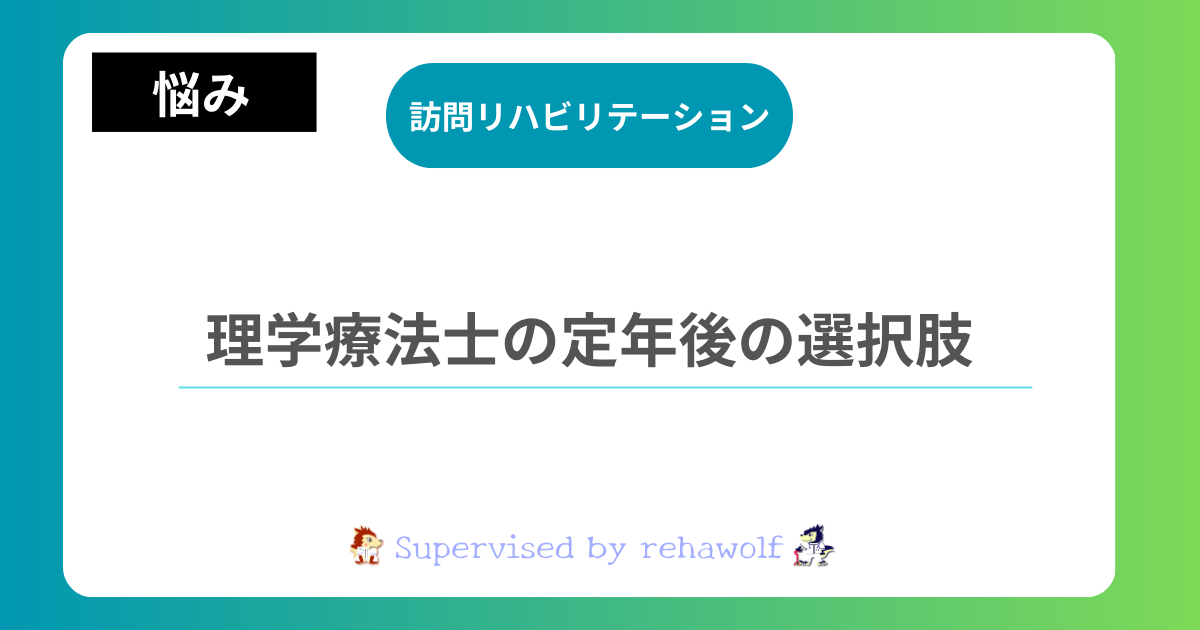
理学療法士として長年働いてきた方にとって、「定年後の働き方」は大きなテーマとなります。
現在、多くの職場では60歳を定年として定めていますが、医療や介護の分野では、経験豊富な理学療法士が求められるため、定年後も仕事を続けることは十分に可能です。さらに、年金の受給開始年齢が引き上げられていることもあり、「定年=引退」という考え方はもはや過去のものとなりつつあります。
しかし、60代になると体力の問題も出てくるため、「今までと同じ働き方で良いのか?」と悩む人も多いでしょう。
そこで本記事では、60代の理学療法士が定年後に選べるさまざまな選択肢について詳しく解説します。
理学療法士として引き続き働く道、ケアマネジャーなどの関連資格を活かした道、教育やコンサルタント業への転身、さらには全く新しいキャリアに挑戦する道まで、幅広く紹介していきます。
「まだまだ社会に貢献したい」「収入を確保しながら、自分のペースで働きたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてください。
人生100年時代で年金がもらえる年齢も遅くなってきている
現代は「人生100年時代」と言われるようになり、60歳や65歳になっても、まだまだ働ける時代になりました。それと同時に、年金の受給開始年齢が引き上げられていることもあり、多くの人が「定年後も収入を確保する必要がある」と感じています。
現在、日本の公的年金は原則として65歳から受給できるようになっていますが、今後さらに受給開始年齢が引き上げられる可能性も指摘されています。これにより、60歳で退職した場合、「年金がもらえるまでの数年間をどう生活するか」という課題に直面することになります。また、年金だけでは十分な生活費を賄えないケースも多く、「働きながら年金を受け取る」という選択をする人も増えています。
さらに、医療の進歩により、60代はまだまだ元気な世代と考えられるようになりました。体力や健康状態にもよりますが、「仕事を続けたい」「社会とのつながりを持ちたい」と考える人が増えているのも事実です。そのため、定年後の働き方を早めに考え、準備しておくことが重要になります。
60代の理学療法士の定年後の選択肢は何がある?
60代の理学療法士の定年後の選択肢は何があるか紹介します。
そのまま理学療法士を継続(意外と60歳なら平気)
理学療法士は、体力を使う仕事ではあるものの、医療や介護の現場では60代でも働いている人は多くいます。特に、リハビリの分野では経験が非常に重視されるため、「年齢が高い=働けない」というわけではありません。実際に、多くの病院やクリニック、訪問リハビリの現場では、60代の理学療法士が活躍しているケースが多く見られます。
また、理学療法士の仕事には「指導的な立場」や「管理職」としての役割もあります。例えば、若手セラピストの教育や、リハビリ部門の運営管理などを担当することで、体力的な負担を軽減しながら働き続けることが可能です。
特に、訪問リハビリの分野では、比較的ゆったりとしたペースで仕事ができるため、定年後も無理なく続けられる職場として人気があります。もし体力的にきついと感じる場合は、週に数日だけ働く「パート勤務」や「嘱託契約」などの働き方を検討するのも良いでしょう。
体力のことを考えてケアマネジャー(介護支援専門員)
理学療法士としての経験を活かしながら、体力的な負担を減らせる仕事の一つが「ケアマネジャー(介護支援専門員)」です。ケアマネジャーは、利用者のケアプランを作成し、適切な介護サービスを提供するための調整役を担う仕事であり、デスクワークが中心となるため、体力的な負担が少ないのが特徴です。
理学療法士は、5年以上の実務経験があればケアマネジャー試験を受験できるため、定年を迎える前に資格を取得しておくことで、スムーズにキャリアチェンジすることが可能になります。また、理学療法士としての専門知識があると、リハビリに特化したケアプランを作成できるため、他のケアマネジャーと差別化できる強みになります。
経験を活かして外部顧問やコンサルタント
長年の経験を活かし、病院や介護施設の外部顧問やコンサルタントとして活動するのも、定年後の選択肢の一つです。特に、リハビリの現場では「人材育成」や「組織運営」に関する知見を持った専門家が求められています。
例えば、以下のような仕事があります。
- 病院のリハビリ部門の運営支援
- 訪問リハビリやデイサービスの開業支援
- セミナー講師や研修講師として活躍
このような仕事は、体力的な負担が少なく、これまでのキャリアを活かしながら働けるため、60代以降でも無理なく続けることができます。
教育的ポジションで再雇用を目指す
理学療法士養成校の講師や、研修施設の指導員として働く道もあります。特に、経験豊富な理学療法士は、教育の現場で求められることが多く、大学や専門学校で後進の育成に携わることができます。
また、教育機関だけでなく、病院や介護施設内での「職員研修」や「新人教育」に関わる仕事もあります。これらの仕事は、指導経験やコミュニケーションスキルが求められますが、定年後もやりがいを持って働ける仕事の一つです。
医療介護以外の全く別の道にチャレンジ
「せっかくの第二の人生だから、新しいことに挑戦したい!」という方には、全く異なる分野での仕事も選択肢になります。例えば、
- 趣味を仕事にする(カフェ経営、農業など)
- 地域活動やボランティアに参加する
- フリーランスとして執筆や講演活動を行う
など、理学療法士の枠にとらわれない働き方も可能です。新しい挑戦をすることで、人生の充実度を高めることができるでしょう。
おじさんやおばさんになっても自分のため社会のために働こう!
60代を迎えると、「もう定年だから引退しよう」と考える人もいるかもしれません。しかし、現代の日本では、60代はまだまだ現役で働ける世代です。医療の進歩によって健康寿命が延び、70代でも元気に活動している人が増えています。特に、理学療法士のような専門職は、年齢を重ねるほどに経験や知識の深みが増し、むしろ「ベテランの価値」が高まる職業です。そのため、「年齢を理由に引退を考える」のではなく、「自分にできることを探して、社会に貢献し続ける」ことを意識してみるのも良いでしょう。
また、定年後に仕事を続けることは、「社会とのつながり」を維持することにもつながります。人は、仕事を通じて社会と関わることで、生きがいを感じやすくなります。特に、理学療法士は患者や利用者とのコミュニケーションが多い職業のため、「誰かの役に立っている」と実感しながら働くことができる点が大きな魅力です。定年を迎えたからといって、突然社会とのつながりを断ち切るのではなく、「自分のペースで働く」という選択肢を持つことで、精神的な充実感も得られるでしょう。
さらに、「収入面」でも、定年後の働き方は重要です。公的年金の受給年齢が引き上げられ、年金だけでは生活が厳しくなる人も増えている中、「定年後も収入を得る手段」を持つことは大切なポイントです。特に、理学療法士の資格や経験を活かせる仕事は多く、体力的な負担を減らしながらも安定した収入を得ることが可能です。例えば、週に数日だけ働くパート勤務や、リハビリ指導を行う講師業、訪問リハビリなど、選択肢はさまざまあります。
もちろん、理学療法士の仕事だけにこだわる必要はありません。新しい分野に挑戦することで、「第二の人生」をより充実させることもできます。例えば、地域のボランティア活動に参加したり、趣味を活かして新しい仕事を始めたりすることも、定年後の選択肢として考えられます。重要なのは、「年齢を理由に諦めるのではなく、何歳になっても挑戦を続けること」です。
人生100年時代。60代はまだまだ「社会に貢献できる年代」です。理学療法士としてのキャリアを活かしながら、自分に合った働き方を選び、心身ともに充実したセカンドライフを楽しんでいきましょう!