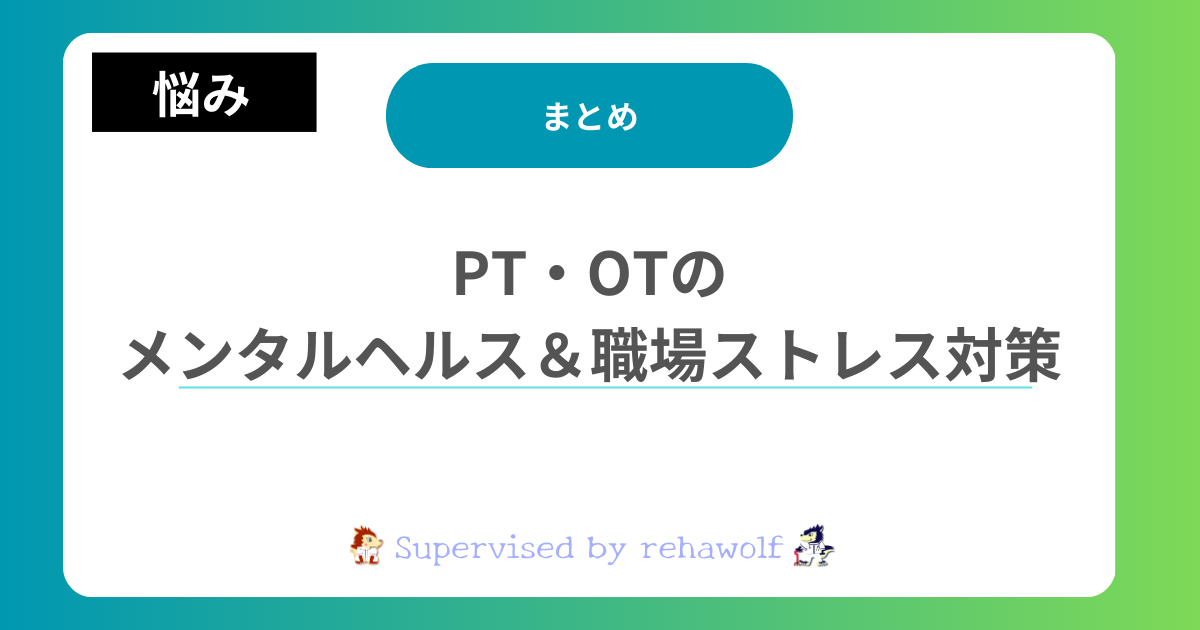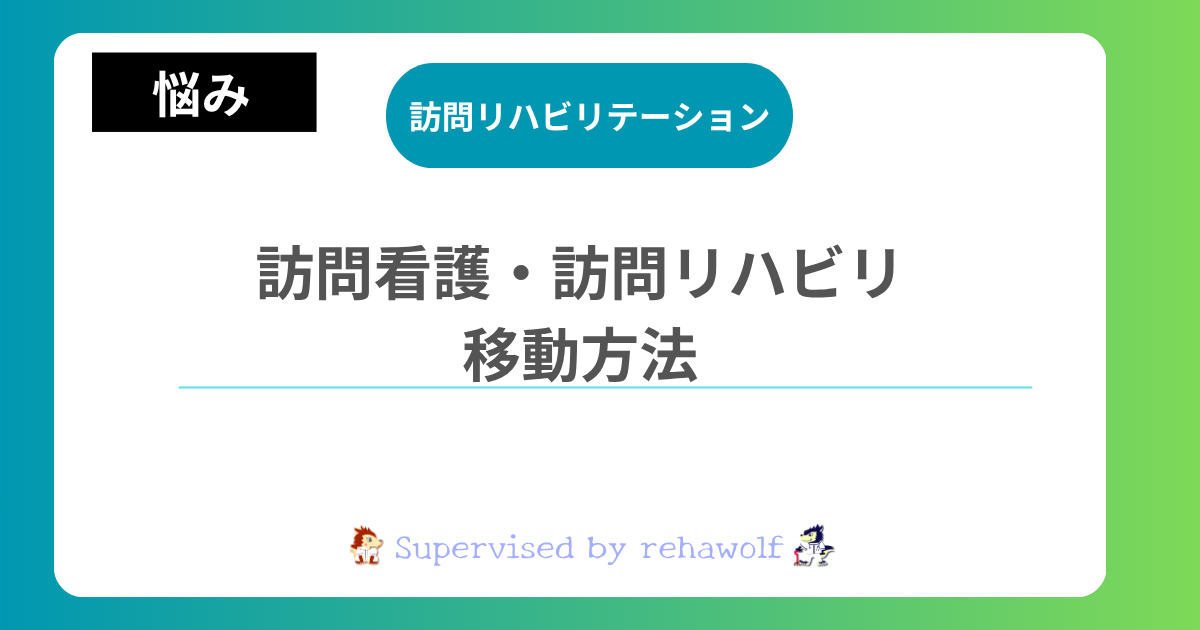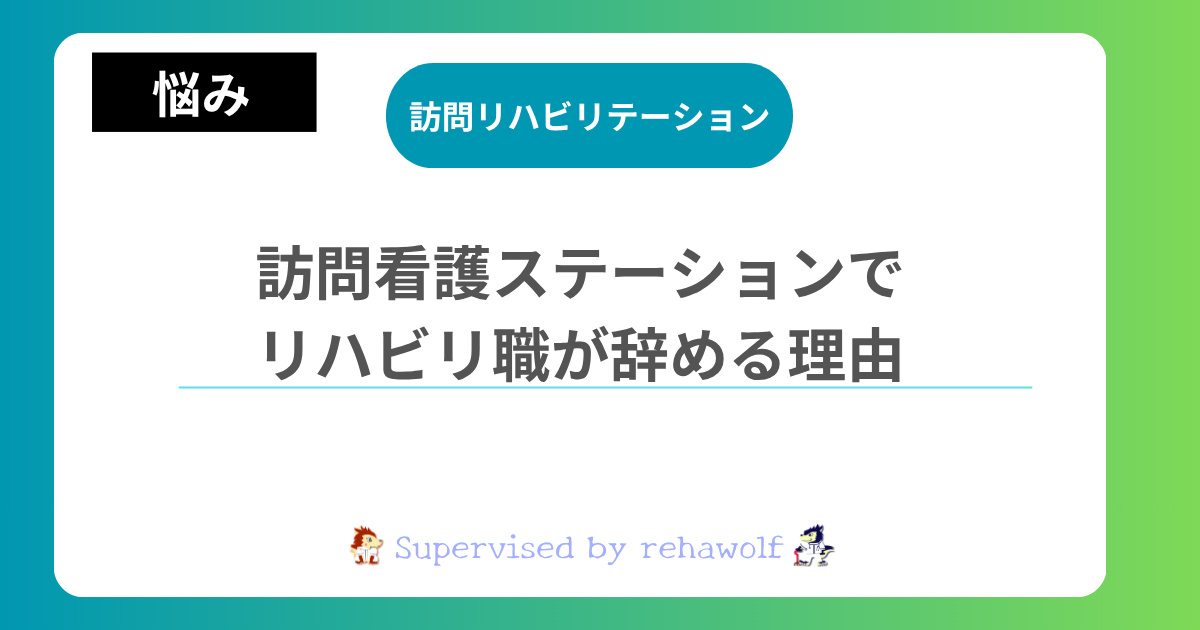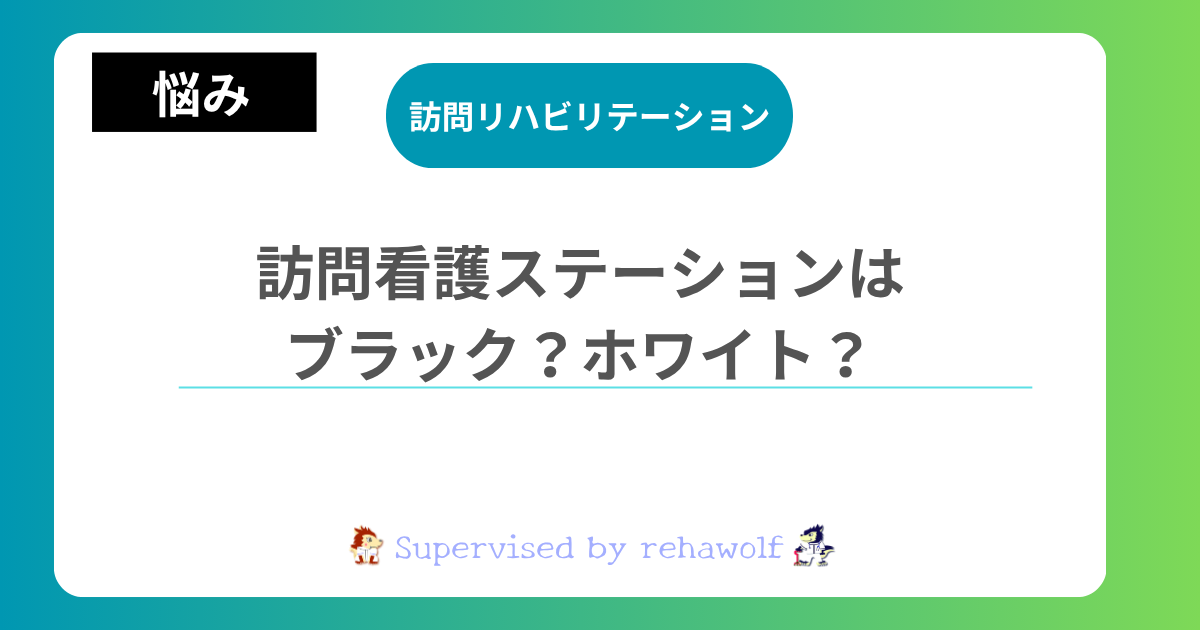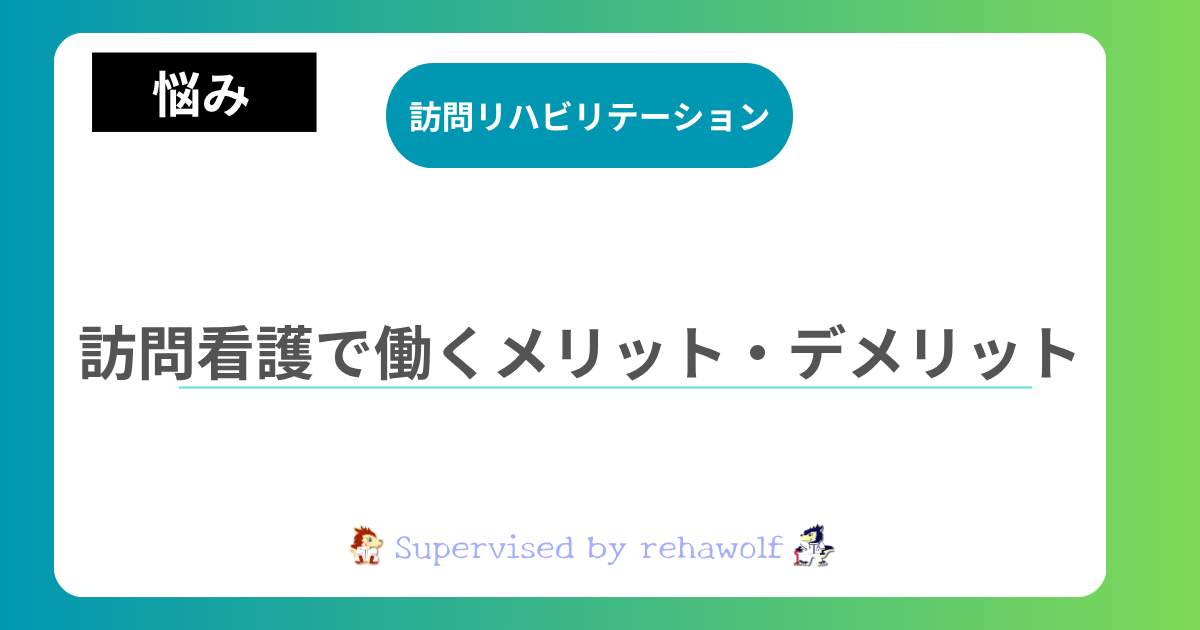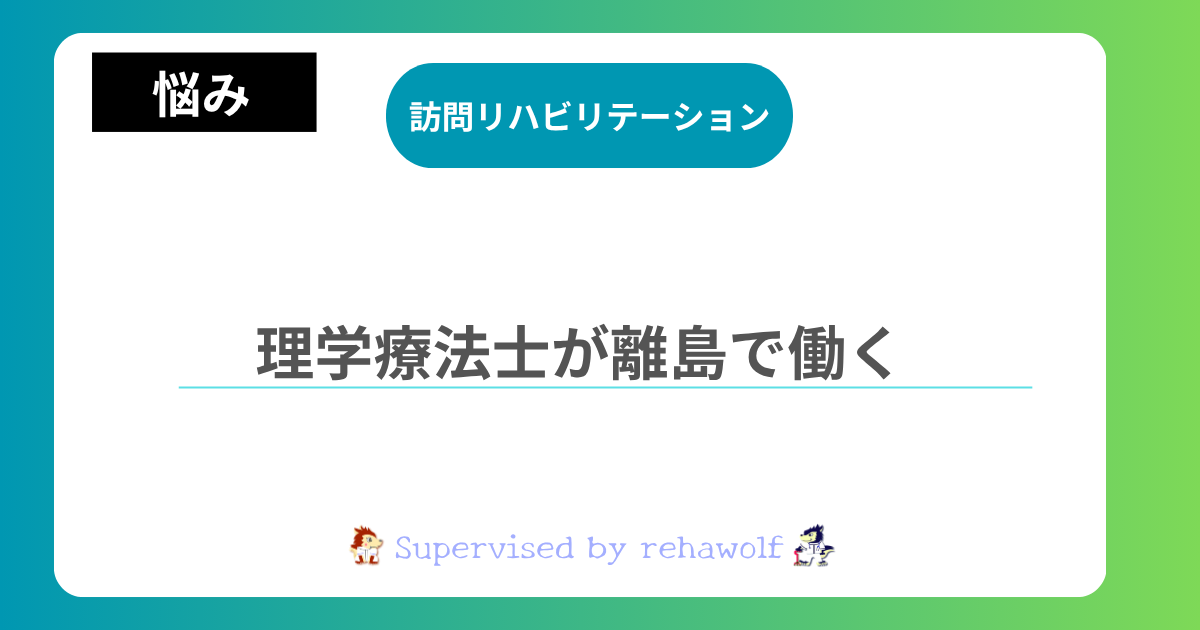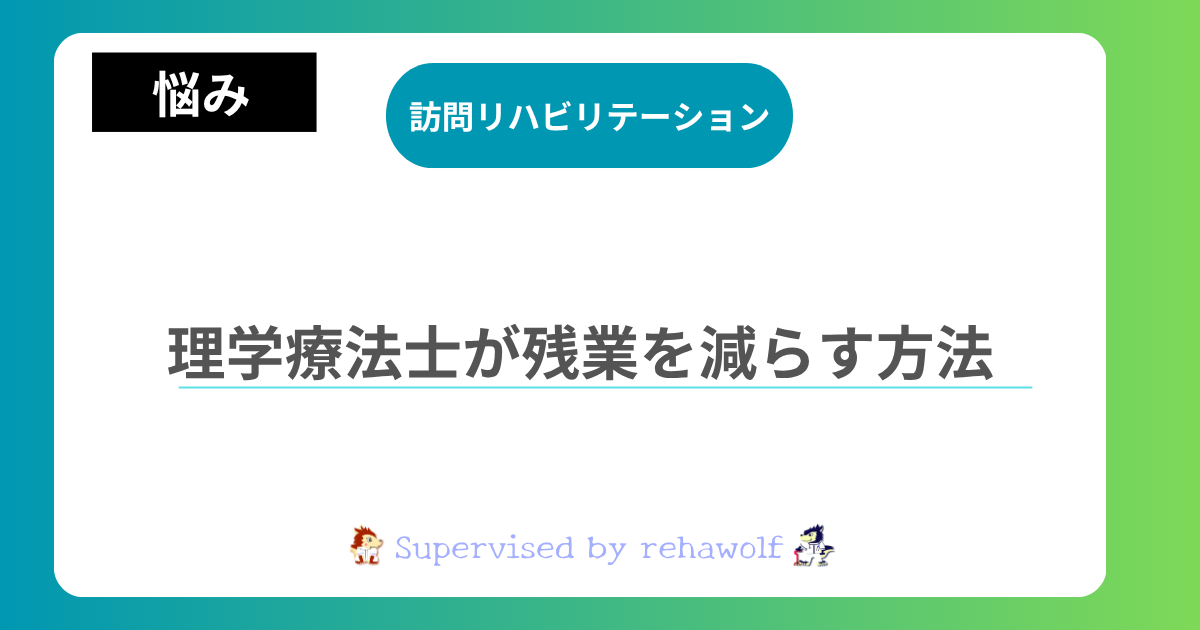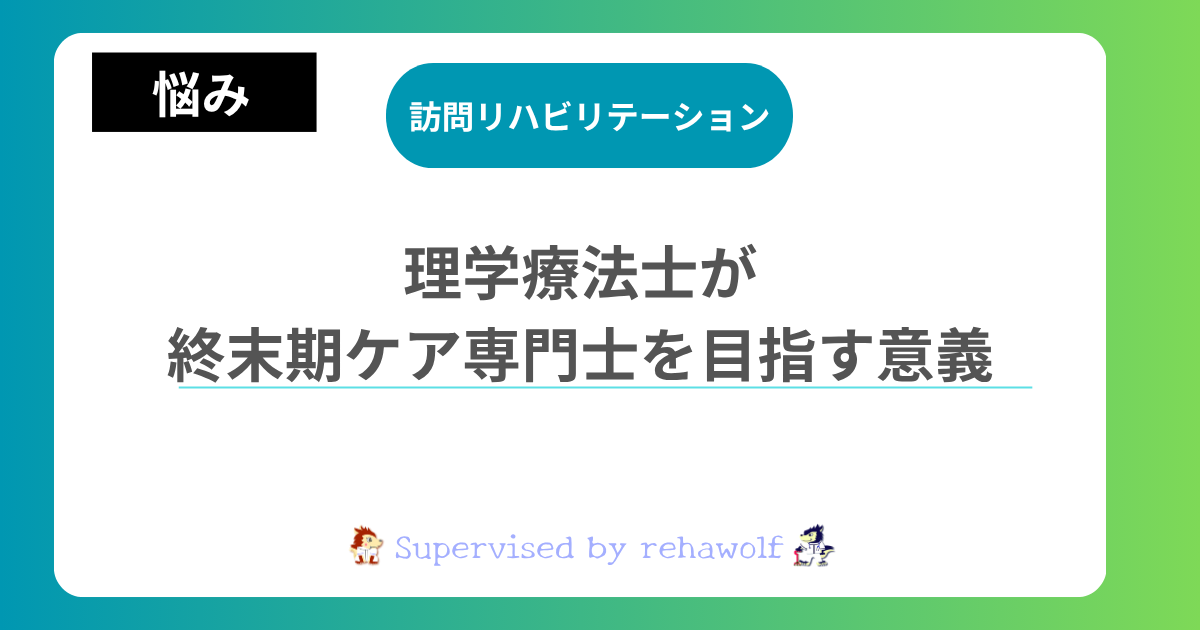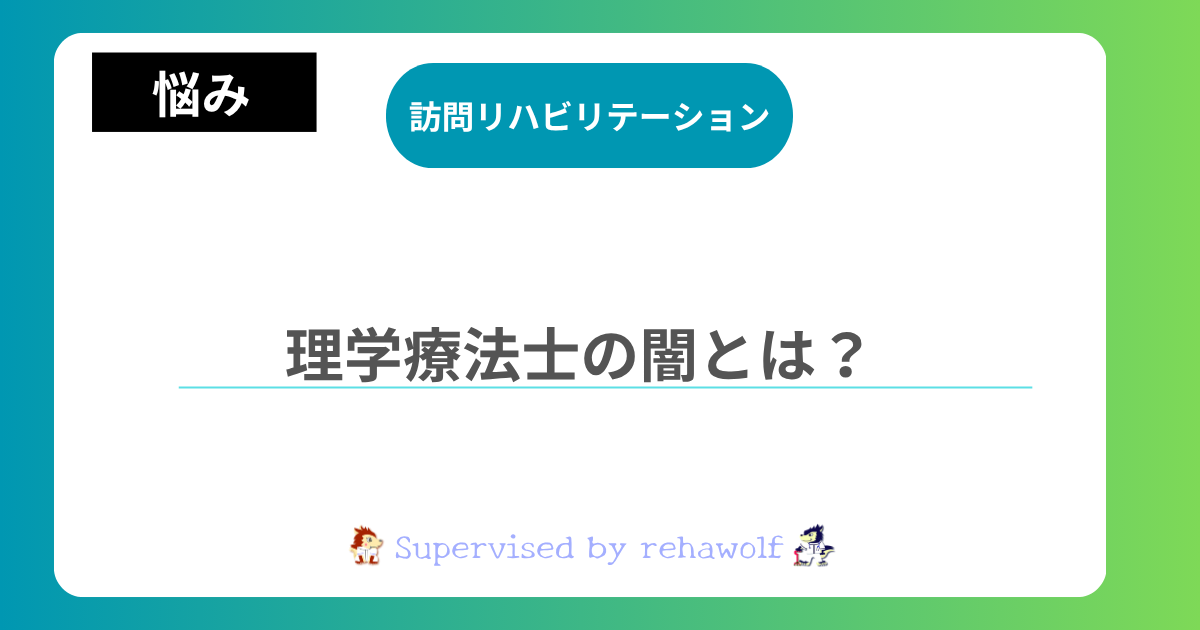訪問リハビリの人間関係はどう?よくある悩みと解決法を解説
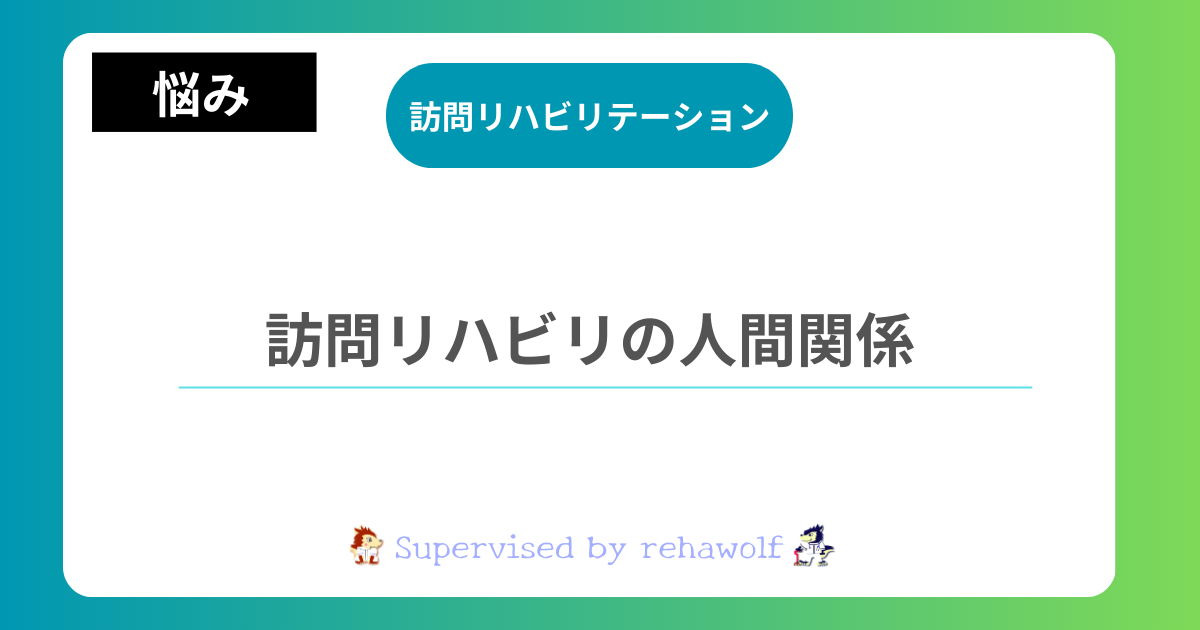
訪問リハビリは、利用者さんの自宅でリハビリを行うため、病院や施設とは違った人間関係の特徴があります。
患者さんや家族と深く関わる一方で、事業所のスタッフ同士や多職種との連携も欠かせません。
そのため「訪問リハビリの人間関係は大変?」「職場で孤立しやすい?」と不安に感じる人も少なくありません。
本記事では、訪問リハビリ特有の人間関係の特徴やよくある悩み、解決方法、転職を考える基準について詳しく解説します。
訪問リハビリの人間関係の特徴
利用者・家族との関係が中心
訪問リハビリでは、利用者さんや家族との信頼関係が仕事の質に直結します。病院のように短期間で入退院する患者さんとは違い、長期にわたって関わることが多いため、人間関係が濃くなりやすいです。
スタッフ同士の関わりは少なめ
病院勤務と比べると、1日の大半は個別訪問のため、スタッフ同士で顔を合わせる時間が少ないのが特徴です。そのため「孤独感を感じる」という声もあります。
多職種との連携が重要
訪問リハビリは、医師や看護師、ケアマネジャー、介護職員などと連携して支援を行います。情報共有や連携不足があるとトラブルにつながりやすいため、コミュニケーション力が求められます。
訪問リハビリの人間関係でよくある悩み
① 利用者・家族との対応が難しい
- 家族の希望が強く、専門的判断と衝突する
- 利用者本人と家族の意向が異なり板挟みになる
- コミュニケーションがうまくいかず不信感を持たれる
② スタッフ間の交流不足
- 1人で訪問する時間が長く、孤立しやすい
- 情報共有が不足しがちで、ミスや誤解につながる
- 上司や先輩に相談するタイミングが取りにくい
③ 多職種との意見の相違
- ケアマネジャーの計画と現場の実情が合わない
- 看護師や介護職との連携不足で利用者に負担がかかる
- 専門職間の立場の違いから摩擦が生じやすい
人間関係の悩みを解決するための工夫
① 利用者・家族には丁寧な説明を
専門用語を避け、わかりやすく説明することで信頼関係を築けます。また、要望にすべて応えるのではなく、医学的に妥当な範囲で調整することが重要です。
② スタッフ同士の情報共有を徹底
定期的なミーティングやチャットツールを活用し、訪問で得た情報を共有することで孤立感を軽減できます。小さなことでも共有する習慣を持つことが大切です。
③ 多職種とは「協力の姿勢」を示す
自分の専門性を主張するだけでなく、他職種の意見を尊重し、協力的な姿勢を示すと関係がスムーズになります。共通のゴールは「利用者の生活の質向上」であることを忘れないようにしましょう。
人間関係が良好な訪問リハビリ職場の特徴
- チームミーティングが定期的に行われている
- スタッフ同士の距離感が近く、相談しやすい雰囲気がある
- 多職種連携がスムーズで、情報共有が徹底されている
- 管理者がスタッフの働きやすさに配慮している
こうした職場では、人間関係の悩みが少なく定着率も高い傾向があります。
人間関係が原因で転職を考えるべきケース
- 利用者や家族とのトラブルが絶えず、サポート体制が弱い
- スタッフ間の関係がギスギスしており、改善の見込みがない
- 上司が相談に乗ってくれず孤立してしまう
- 精神的・身体的に限界を感じている
訪問リハビリは需要が高く、職場を選びやすい環境です。人間関係の悩みが深刻で解決できない場合は、無理をせず転職も選択肢に入れるべきです。
まとめ:訪問リハビリの人間関係は工夫と環境選びで改善できる
訪問リハビリでは、利用者や家族、多職種との関わりが多く、人間関係の悩みを抱える人も少なくありません。
孤立感や板挟み、連携不足などの課題がありますが、丁寧な説明や情報共有、協力的な姿勢によって改善できるケースも多いです。
それでも解決が難しい場合は、人間関係が良好な職場への転職を検討することも大切です。
働く環境を整えることで、訪問リハビリのやりがいを長く感じながら続けていくことができるでしょう。