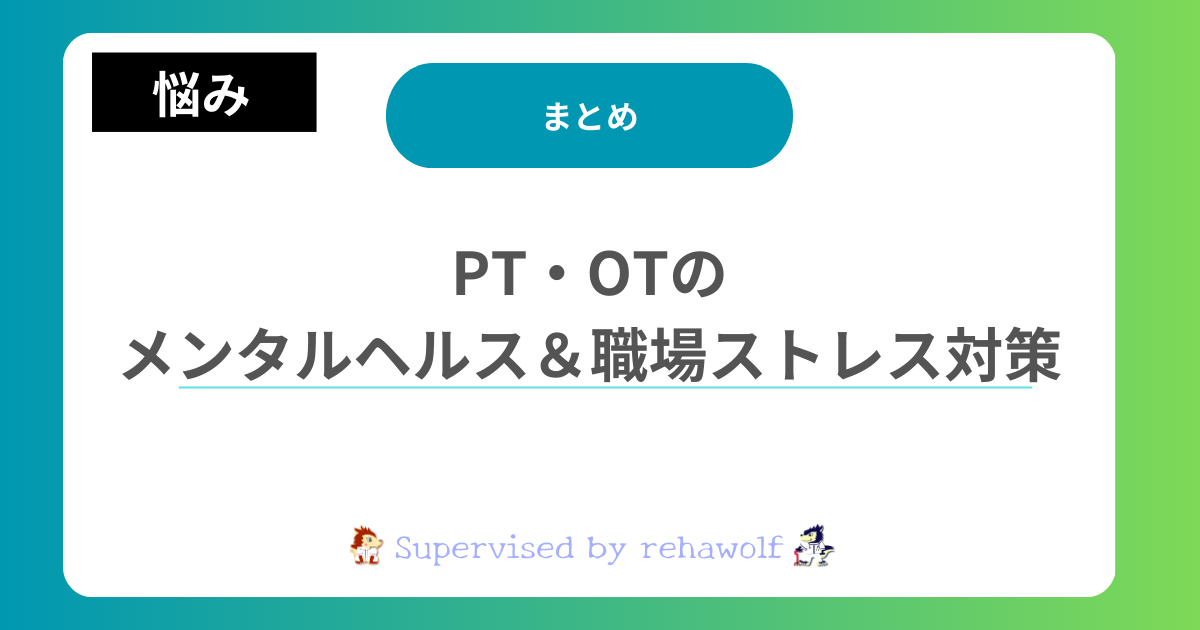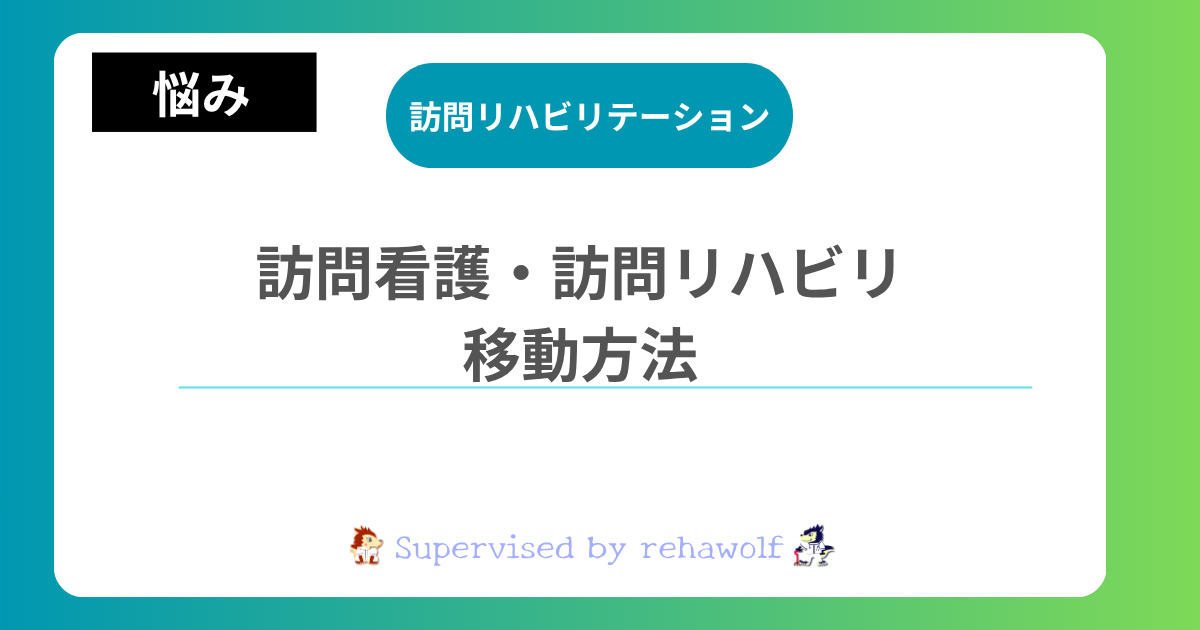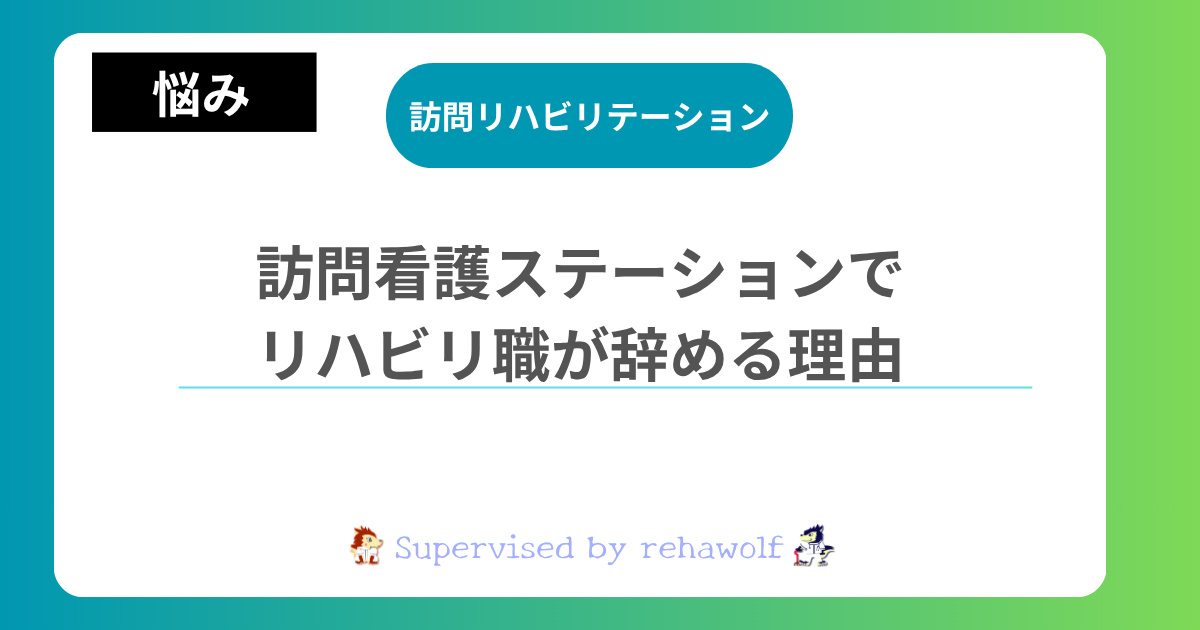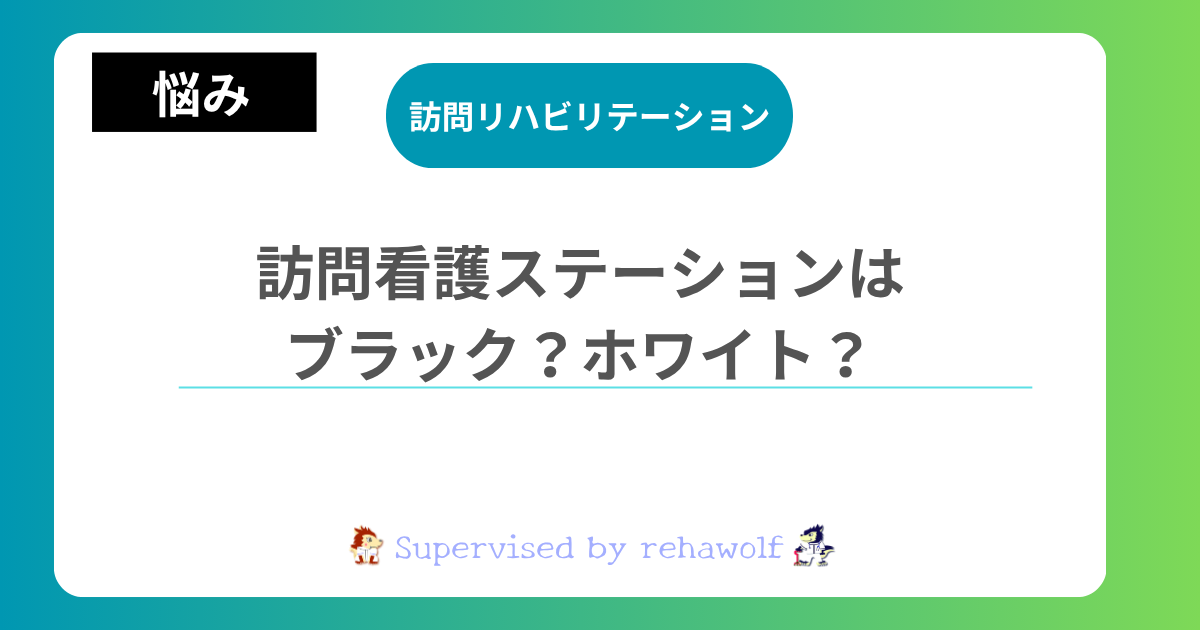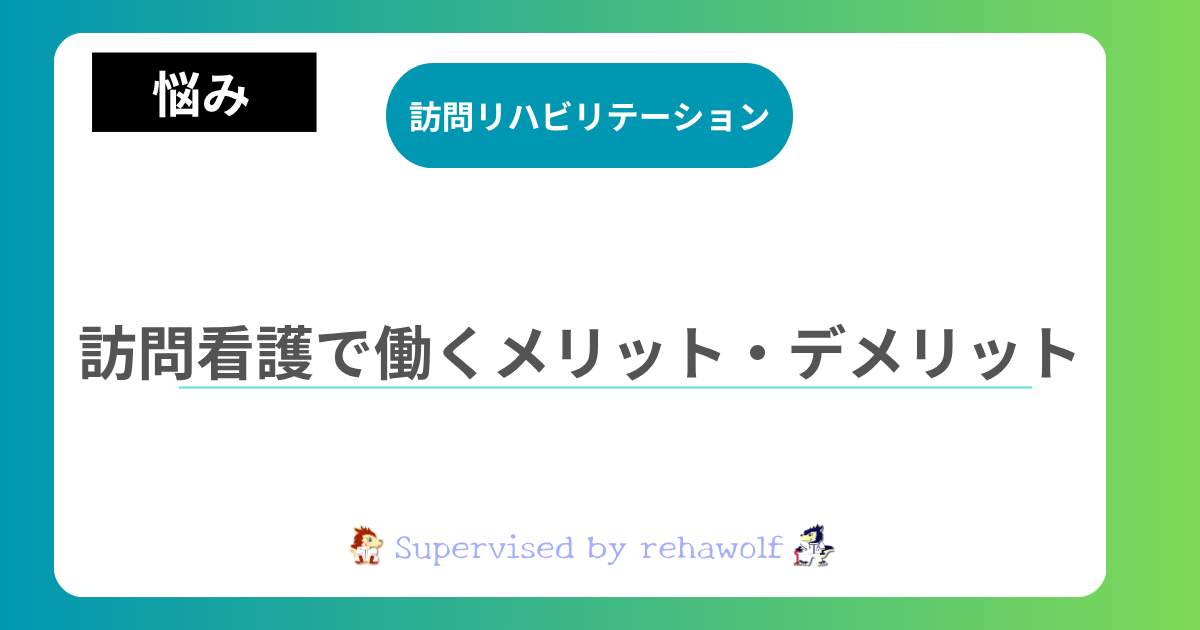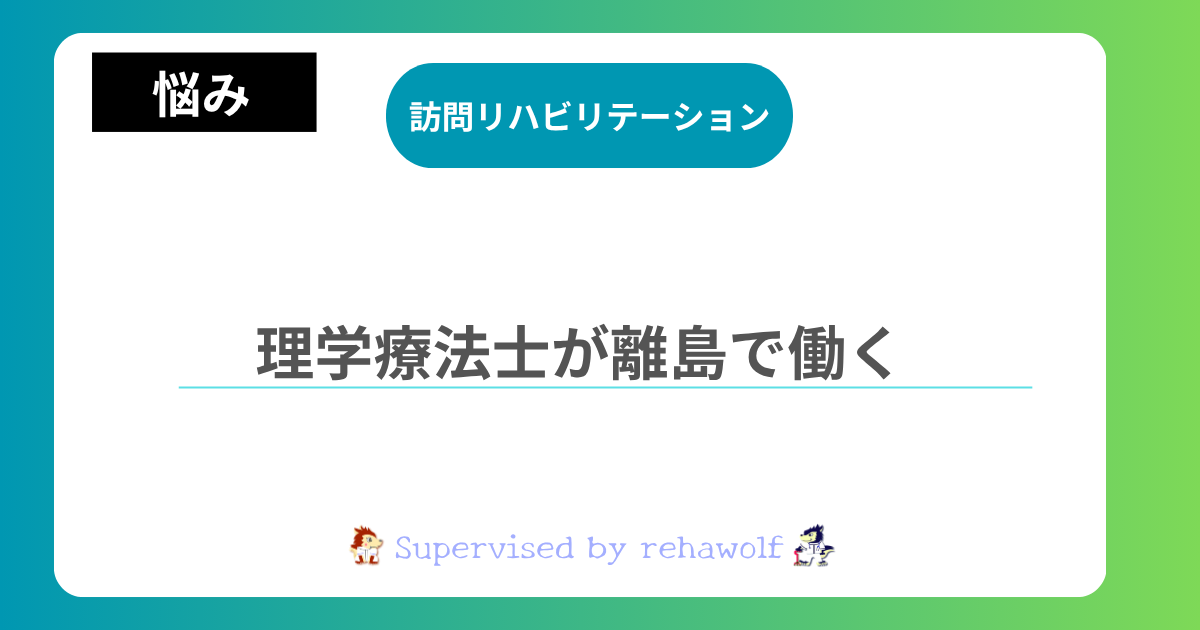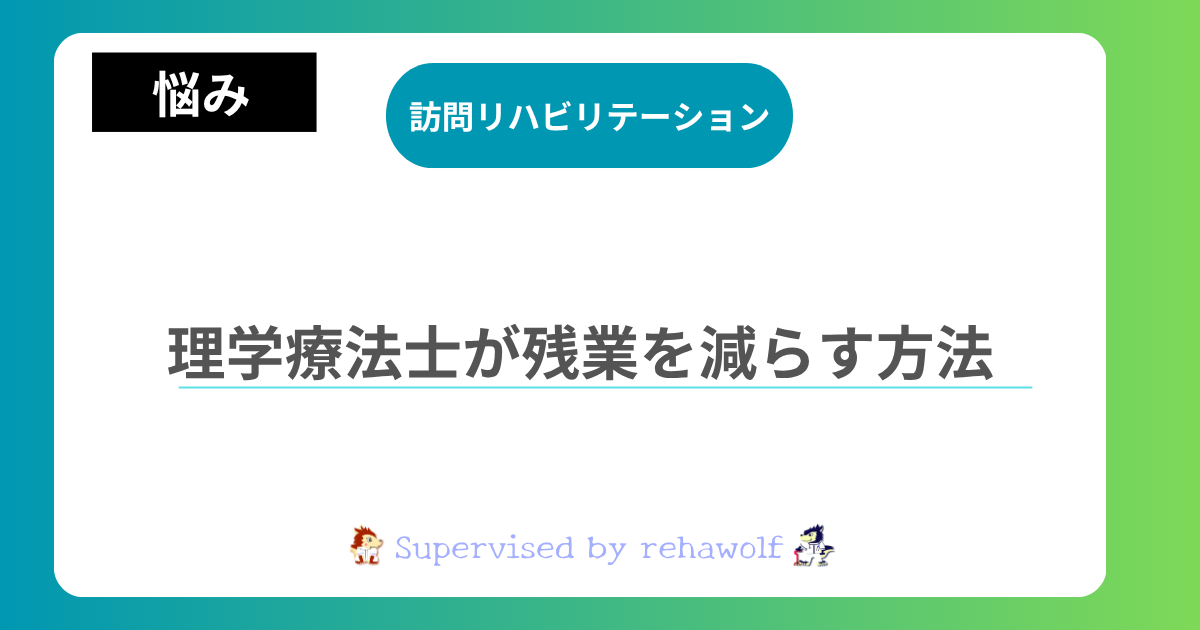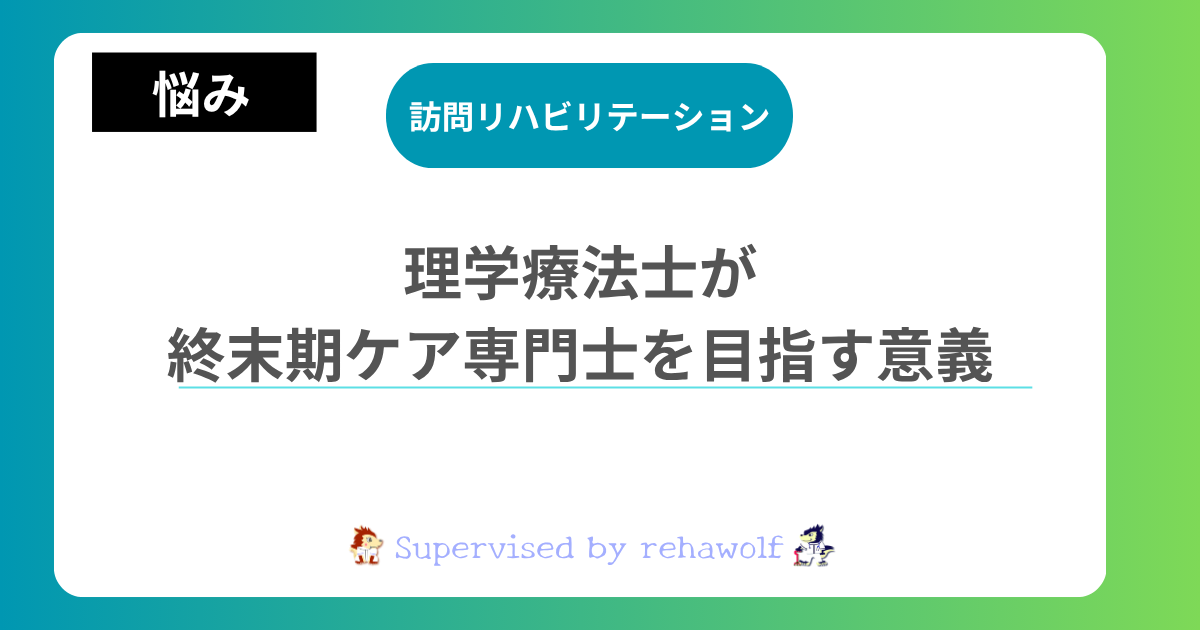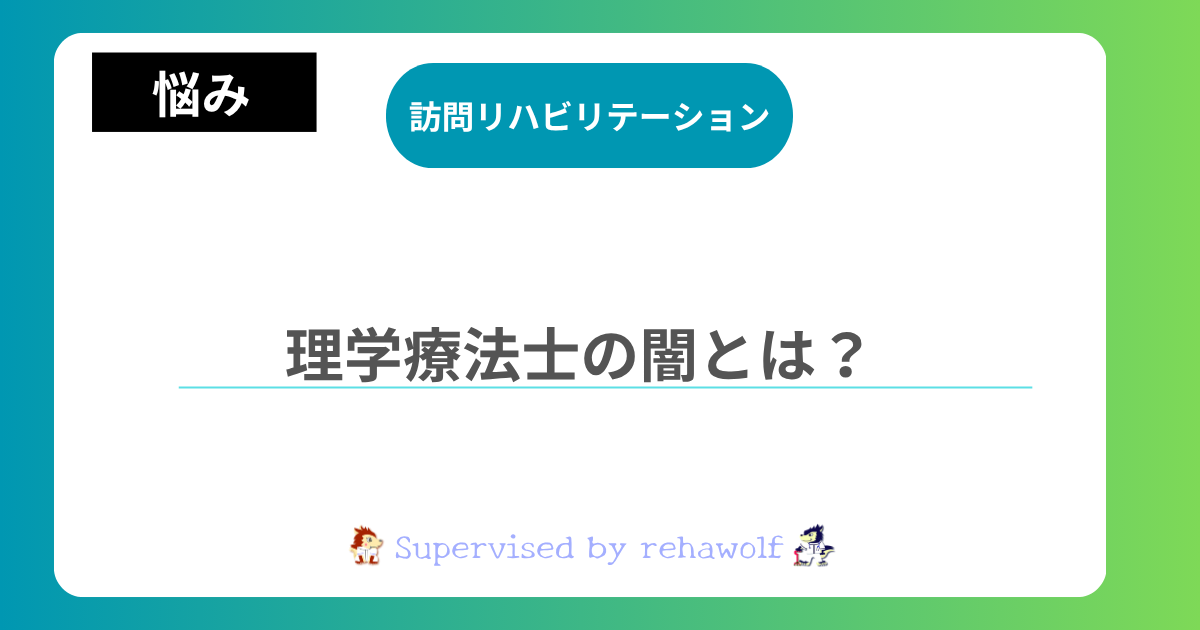理学療法士・作業療法士のストレス事情|原因と解消法を徹底解説
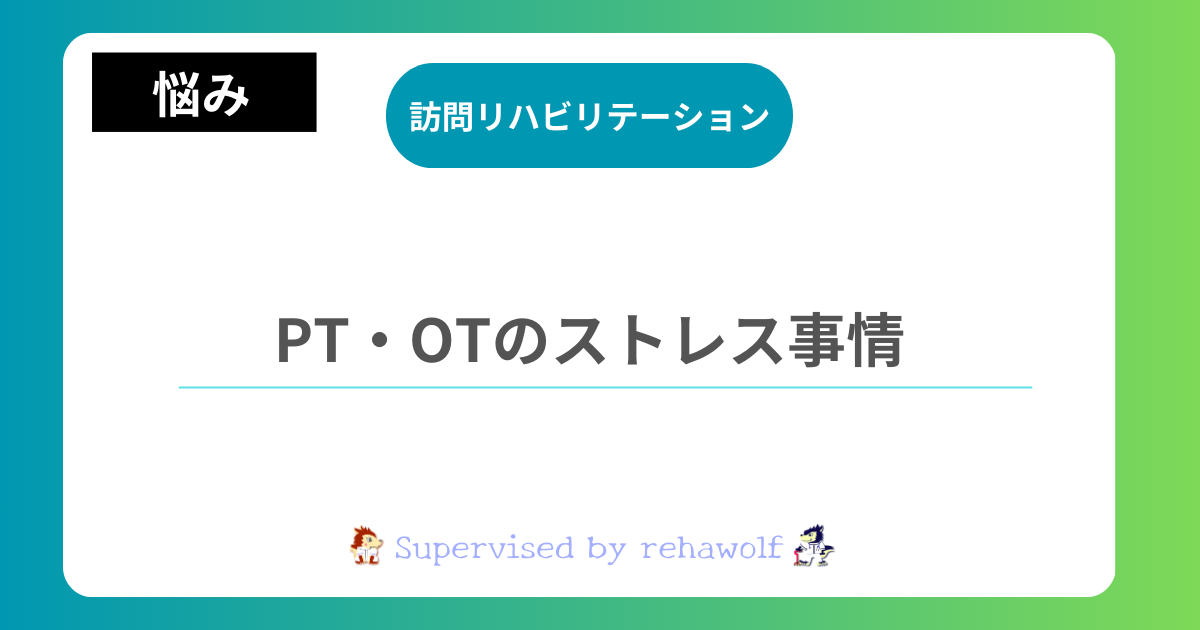
理学療法士(PT)・作業療法士(OT)は、患者の生活機能改善や社会参加を支援する専門職です。
しかし、そのやりがいの大きさとは裏腹に「仕事がしんどい」「ストレスがたまる」と感じる人は少なくありません。
体力的な負担だけでなく、人間関係や制度対応、キャリア形成の不安など、多岐にわたる要因がストレスの原因となっています。
本記事では、PT・OTに多いストレスの原因と解消法を詳しく解説し、ストレスと上手に付き合いながら長く働き続けるためのヒントを紹介します。
理学療法士・作業療法士が抱えるストレスの原因
理学療法士・作業療法士が日常的に感じるストレスは、仕事内容・人間関係・制度対応など複数の要因が重なっています。
身体的な負担によるストレス
リハビリ業務では、移乗介助・歩行練習・物理的な支援など体力を使う場面が多く、腰痛や肩の疲労は代表的な悩みです。特に若手のうちは技術が未熟で、効率の悪い介助を繰り返すことで慢性的な身体の痛みにつながります。こうした身体的負担は、心身のストレス増大にも直結します。
精神的プレッシャーによるストレス
「患者が思うように回復しない」「家族からの要望に応えられない」など、期待に応えられない場面は精神的なプレッシャーにつながります。また、終末期や重度障害の患者を担当する場合は、「自分のリハビリに意味があるのか」と無力感に陥るケースもあります。こうした心理的なストレスは燃え尽き症候群を引き起こすリスクもあります。
人間関係のストレス
理学療法士・作業療法士は、医師・看護師・介護職・ケアマネなど多職種と連携します。そのため、意見の食い違いや役割の認識のズレから人間関係にストレスを感じる人が多いです。また、同じリハ職同士でも、業務分担や臨床方針の違いが摩擦を生むことがあります。
制度・書類業務によるストレス
介護保険や医療保険の制度対応は複雑で、加算要件や報告書・計画書の作成など膨大な書類業務がストレスの要因になります。臨床業務と書類作成の両立に追われ、「患者と向き合う時間が減っている」と感じるセラピストも少なくありません。
ストレスが続くとどうなる?
身体への影響
慢性的な疲労や不眠、肩こり・腰痛など身体症状として現れやすくなります。
心理的な影響
無気力、意欲の低下、イライラ感が増え、業務への集中力が落ちることがあります。
キャリアへの影響
燃え尽き症候群や強いストレスによって離職・転職を考える人も多く、キャリア継続が難しくなるケースもあります。
理学療法士・作業療法士のストレス解消法
身体的ストレスへの対処法
- ボディメカニクスを徹底して介助する
- 装具やリフトを適切に活用する
- 日常的にストレッチや運動を取り入れ、身体をメンテナンスする
精神的ストレスへの対処法
- 成果を「ADLの改善」だけでなく「生活の質の向上」で評価する
- 患者や家族に「できること」「できないこと」を明確に説明し、期待値を調整する
- 定期的にカンファレンスで共有し、一人で抱え込まない
人間関係ストレスへの対処法
- 多職種連携では、専門用語を避け「誰にでもわかる言葉」で伝える
- 自分の主張だけでなく相手の立場を理解する姿勢を持つ
- どうしても改善できない場合は職場環境を変える選択も検討する
制度・書類業務のストレス対策
- 書類作成は「その場で下書きを作る」習慣を持つ
- ICTツールや電子カルテを積極的に活用する
- 制度研修に参加し、正しい知識を効率的にインプットする
ストレスを溜め込まない働き方の工夫
- 定期的に休暇を取り、リフレッシュする
- 子育てや家庭との両立を考え、時短勤務やパート勤務に切り替える
- 勉強会やコミュニティに参加し、悩みを共有する仲間を作る
- 将来的に訪問リハや教育分野など、自分に合った領域へキャリアチェンジする
まとめ
理学療法士・作業療法士が抱えるストレスの原因は、身体的・精神的・人間関係・制度対応と多岐にわたります。
大切なのは、一人で抱え込まず、工夫や環境調整でストレスを減らすことです。
セルフケアを実践し、必要に応じて職場環境を見直すことで、無理なく長く働き続けられます。
リハ職としてのキャリアを守るためにも、ストレス対策を日常的に意識していきましょう。