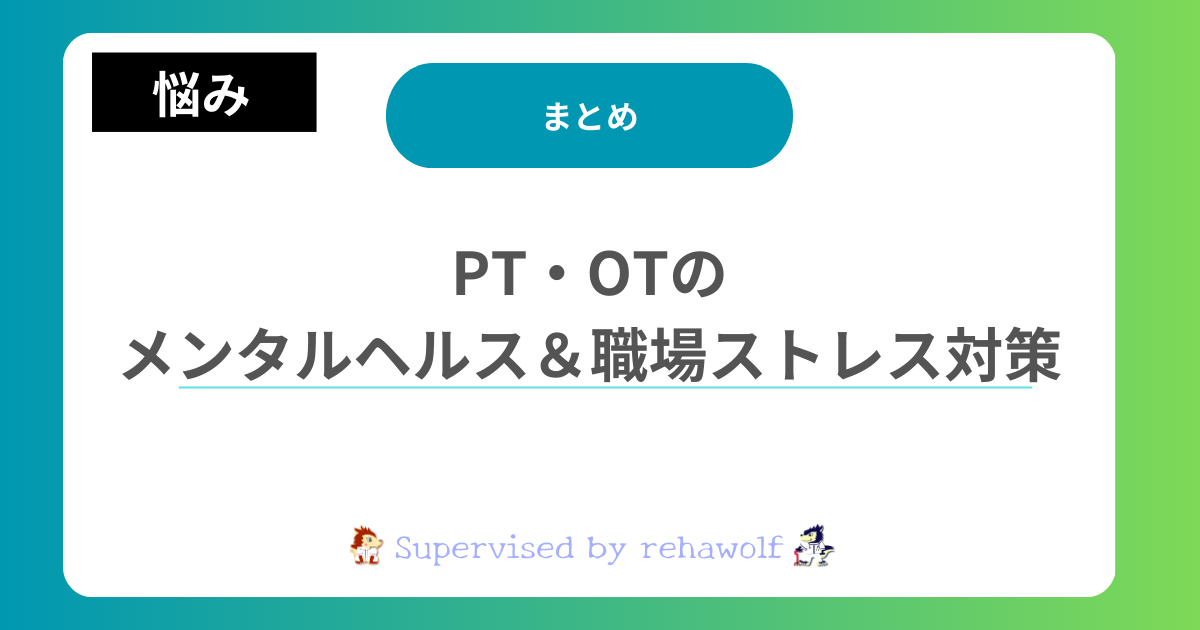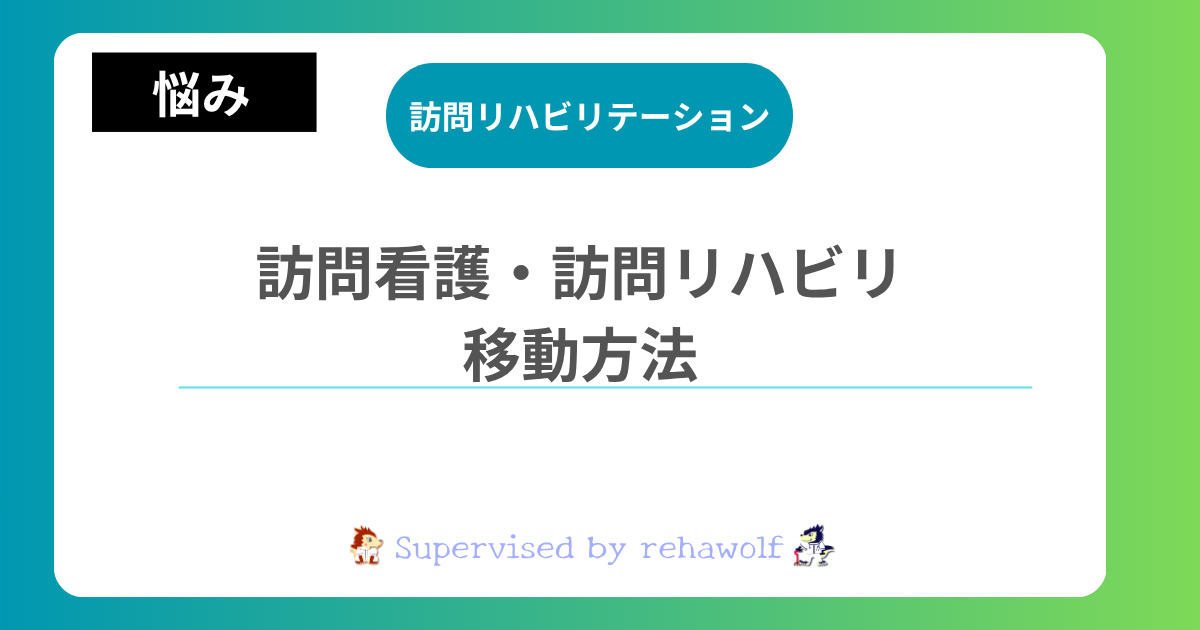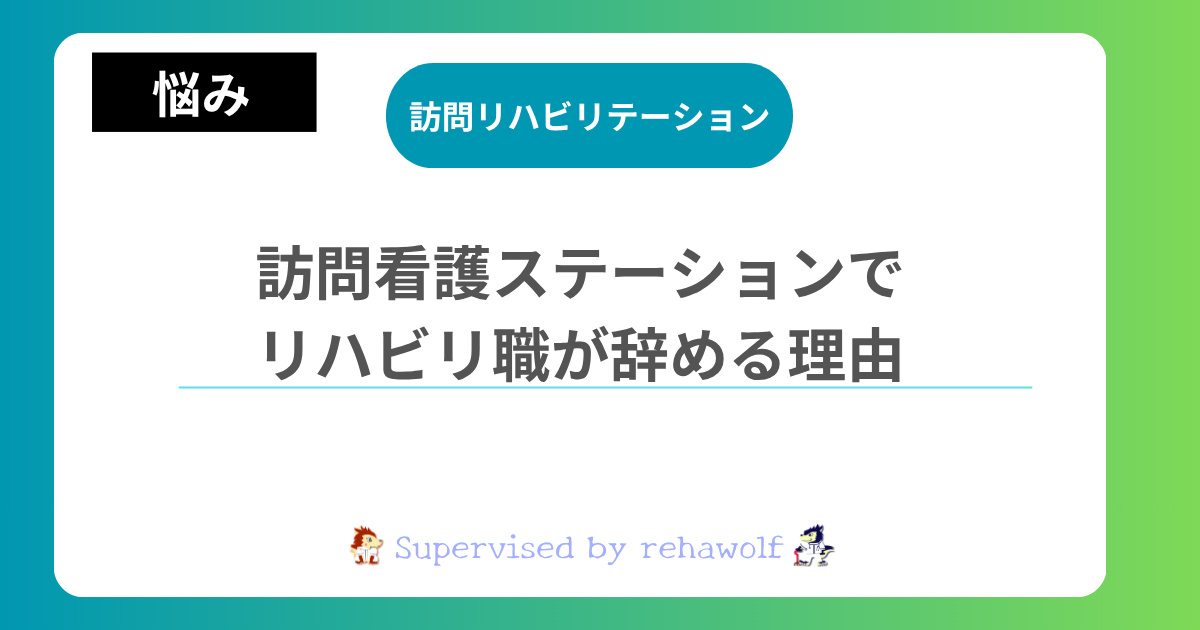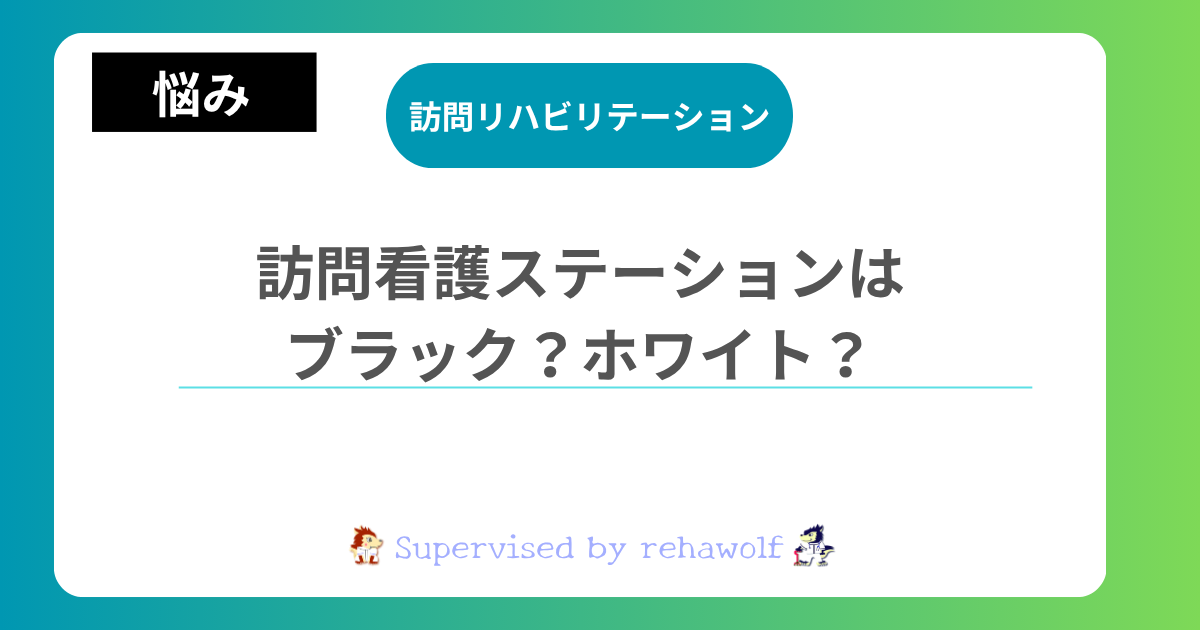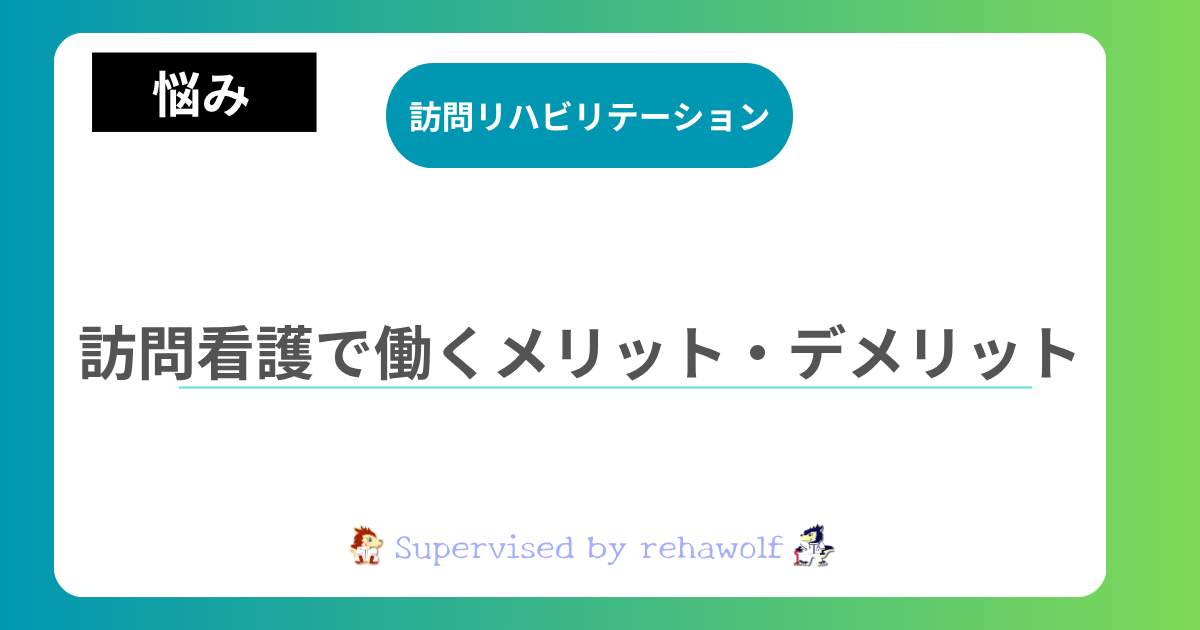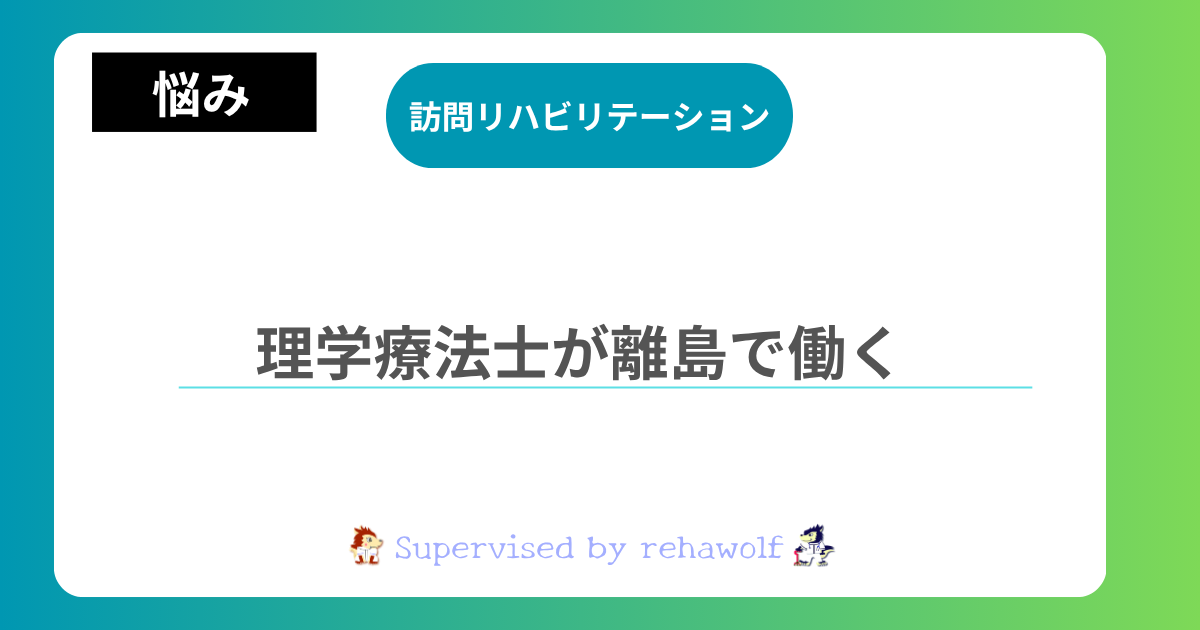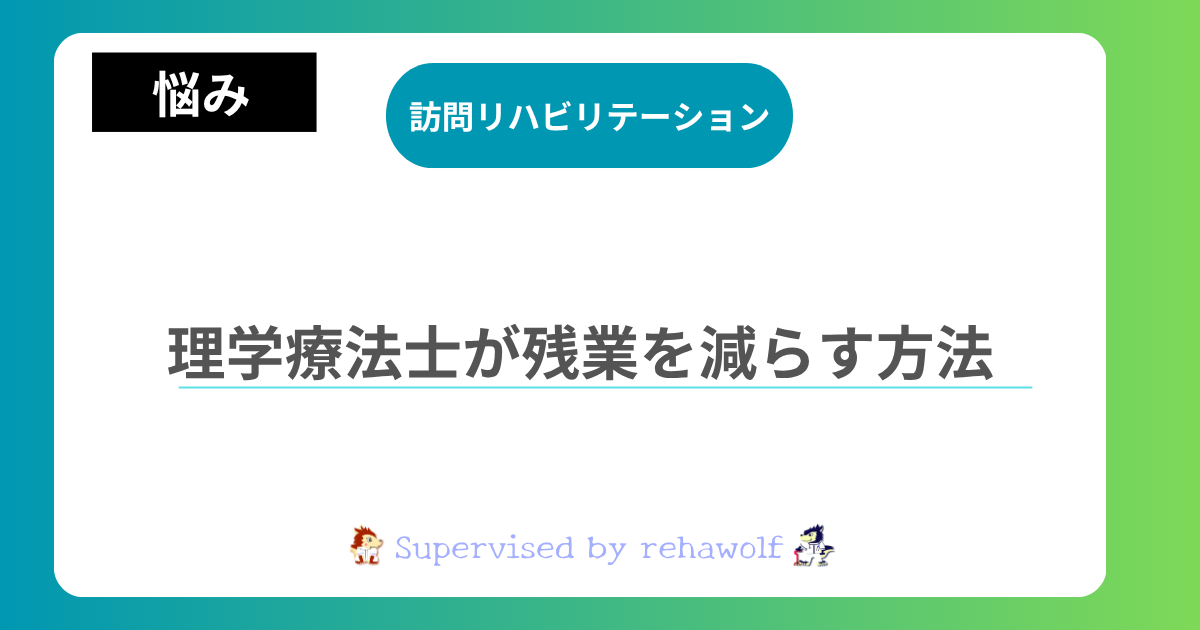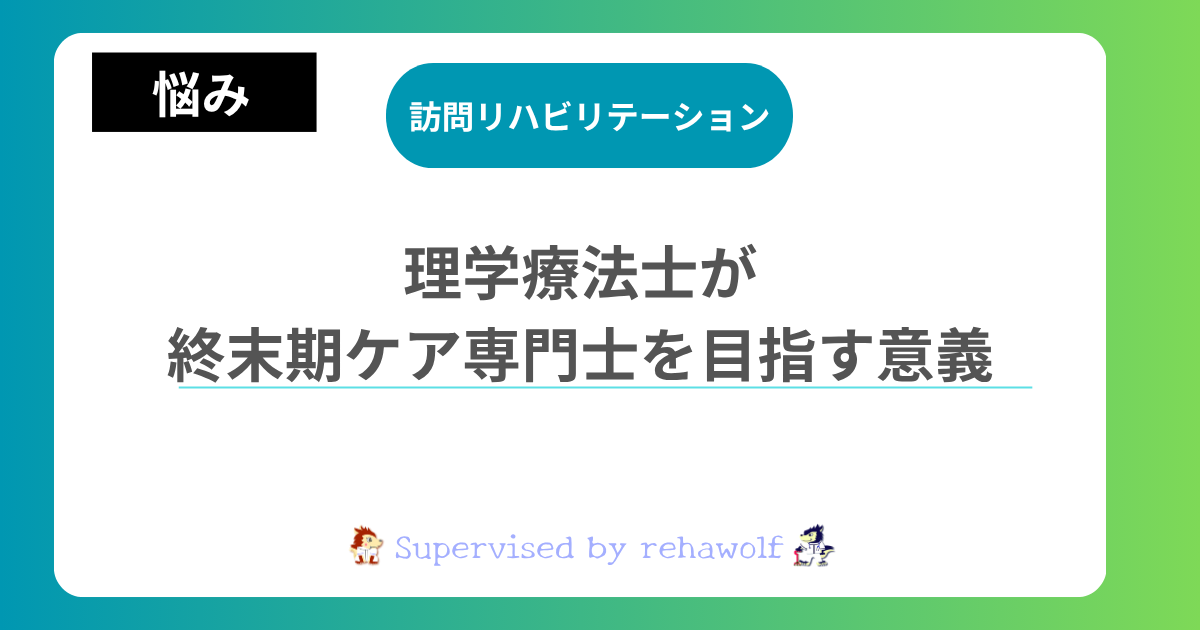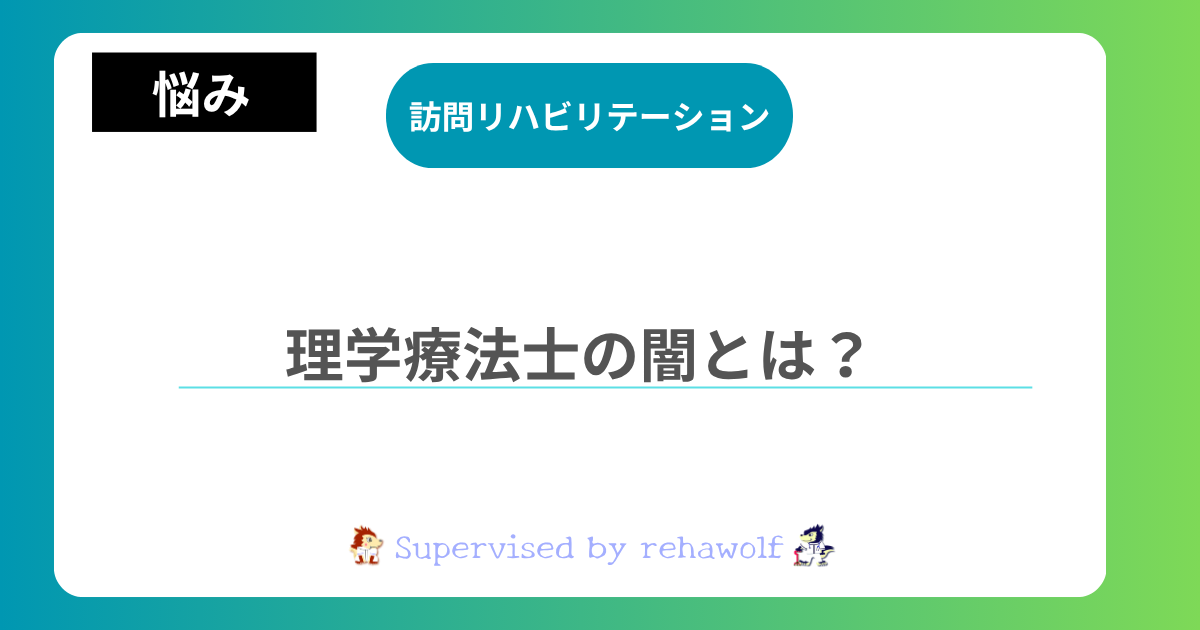理学療法士・作業療法士と燃え尽き症候群(バーンアウト)|原因・症状・対処法を解説
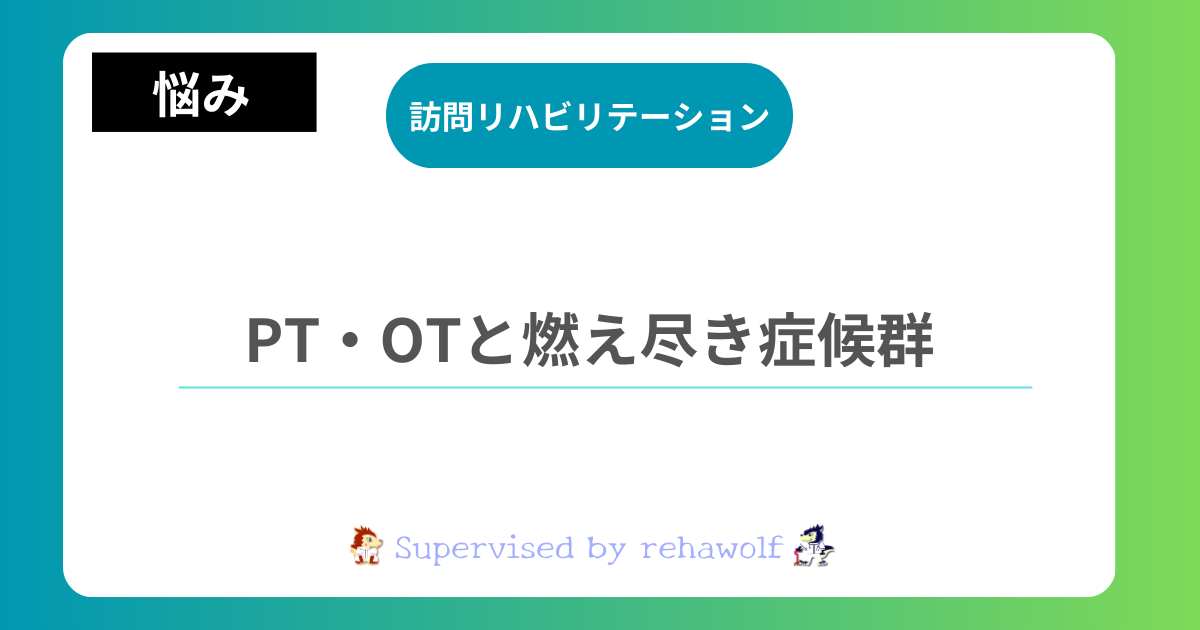
理学療法士(PT)・作業療法士(OT)は、患者の生活機能回復を支える重要な役割を担っています。
しかし、その責任の重さや日々のストレスにより、燃え尽き症候群(バーンアウト) に陥る人も少なくありません。
「仕事にやる気が出ない」「患者対応がつらい」「もう辞めたい」と感じる場合、それはバーンアウトの兆候かもしれません。
本記事では、PT・OTが燃え尽き症候群に陥る原因・症状・対処法を詳しく解説し、長く働き続けるためのヒントを紹介します。
燃え尽き症候群(バーンアウト)とは?
燃え尽き症候群とは、仕事に過度に打ち込み続けた結果、心身が疲弊し、エネルギーが枯渇してしまう状態を指します。
- 強い使命感や責任感を持つ人が陥りやすい
- 医療・介護・教育など「人と向き合う職業」で特に多い
- 無気力・感情の枯渇・職務への無関心が特徴的
理学療法士・作業療法士が燃え尽き症候群になりやすい理由
強い責任感と期待
患者や家族から「歩けるようになりたい」「日常生活を取り戻したい」と大きな期待を寄せられる一方、思うように結果が出ないと自責の念にかられます。
身体的・精神的な負担
毎日の移乗介助や歩行練習など体力的負担が大きく、慢性的な疲労が蓄積します。さらに、終末期や重度障害の患者を担当すると精神的消耗も強くなります。
人間関係のストレス
医師・看護師・介護職・家族との連携の中で摩擦が生じやすく、人間関係のストレスがバーンアウトの引き金になることもあります。
業務量・書類業務の多さ
臨床だけでなく、報告書・計画書・制度対応など書類業務が膨大で「患者と向き合う時間がない」という不満がストレスにつながります。
燃え尽き症候群の症状と兆候
心理的な兆候
- 無気力、仕事への興味ややる気の低下
- 患者への共感が薄れる
- 「もう辞めたい」と頻繁に考える
身体的な兆候
- 慢性的な疲労感
- 睡眠障害や食欲不振
- 頭痛や肩こり、腰痛の悪化
行動の変化
- 遅刻・欠勤が増える
- 記録や報告が疎かになる
- 同僚との関わりを避ける
燃え尽き症候群を防ぐための予防法
1. 目標設定を現実的にする
「歩けるようにする」だけでなく、「安全に移乗できる」「生活動作が自立する」など、小さな目標を積み重ねる。
2. チームで支える
一人で抱え込まず、カンファレンスや相談で共有する。多職種の視点を取り入れることで心理的負担が軽減。
3. 自分の時間を確保する
仕事以外にリフレッシュできる趣味・運動・家族時間を持つ。心身のバランスを取り戻すことが大切。
4. キャリアの見直し
同じ職場で限界を感じるなら、訪問リハや教育、研究分野などへのキャリアチェンジも一つの手段。
燃え尽き症候群から回復するための対処法
- 早めに休養を取る:有給や休職で心身を休める
- 専門家に相談する:産業医・心療内科・カウンセラーを活用
- 小さな成功体験を積む:日々の進歩を記録してモチベーションを回復
- 職場環境を変える:無理のない人員配置や残業の少ない職場へ転職
まとめ
理学療法士・作業療法士は、責任感の強さや業務負担の大きさから燃え尽き症候群(バーンアウト)に陥りやすい職種です。
大切なのは、無理をせず、自分の限界を認めてケアを行うこと。セルフケア・相談・休養・キャリアの見直しを通じて、ストレスを溜め込みすぎない工夫をしましょう。
燃え尽きる前に対策をとることで、リハ職として長く働き続けることが可能になります。