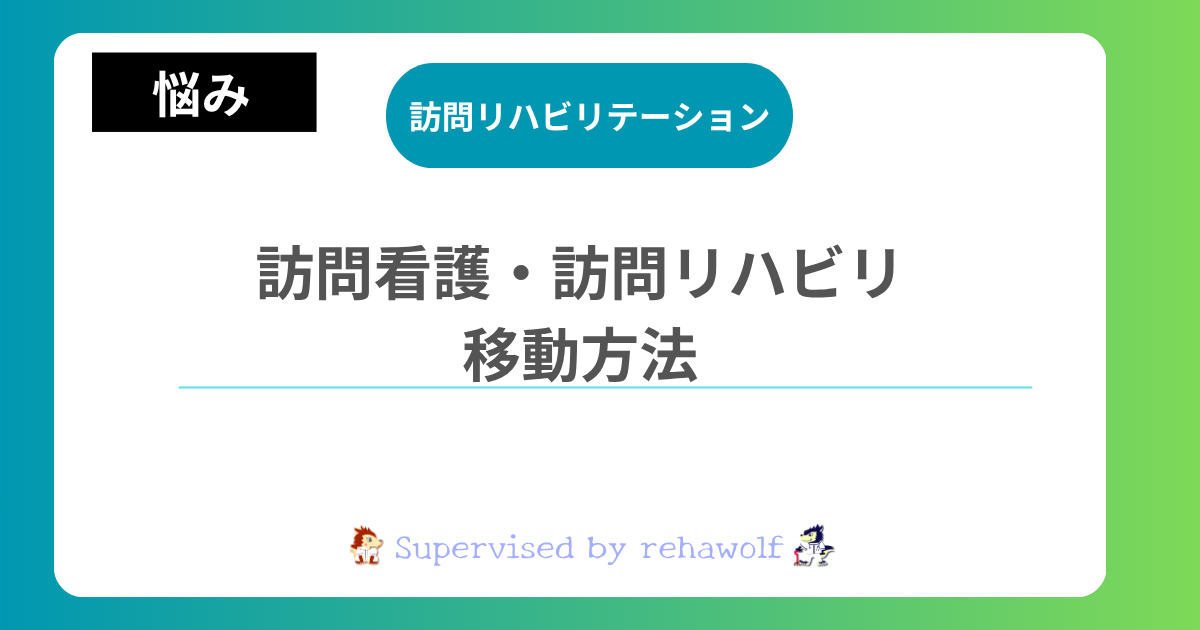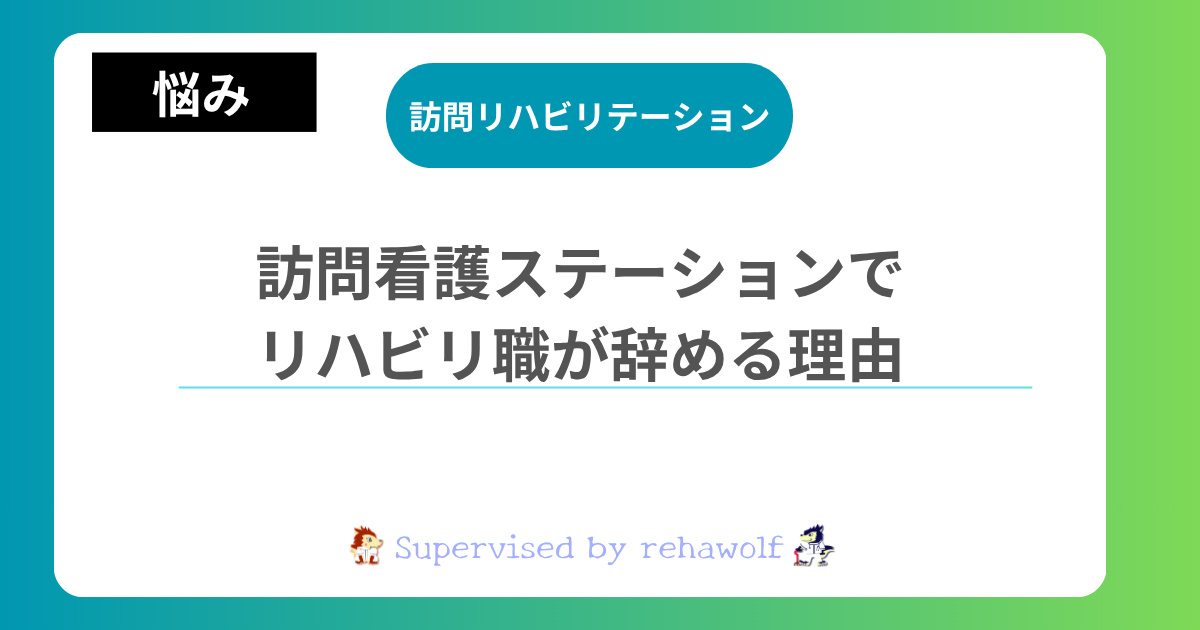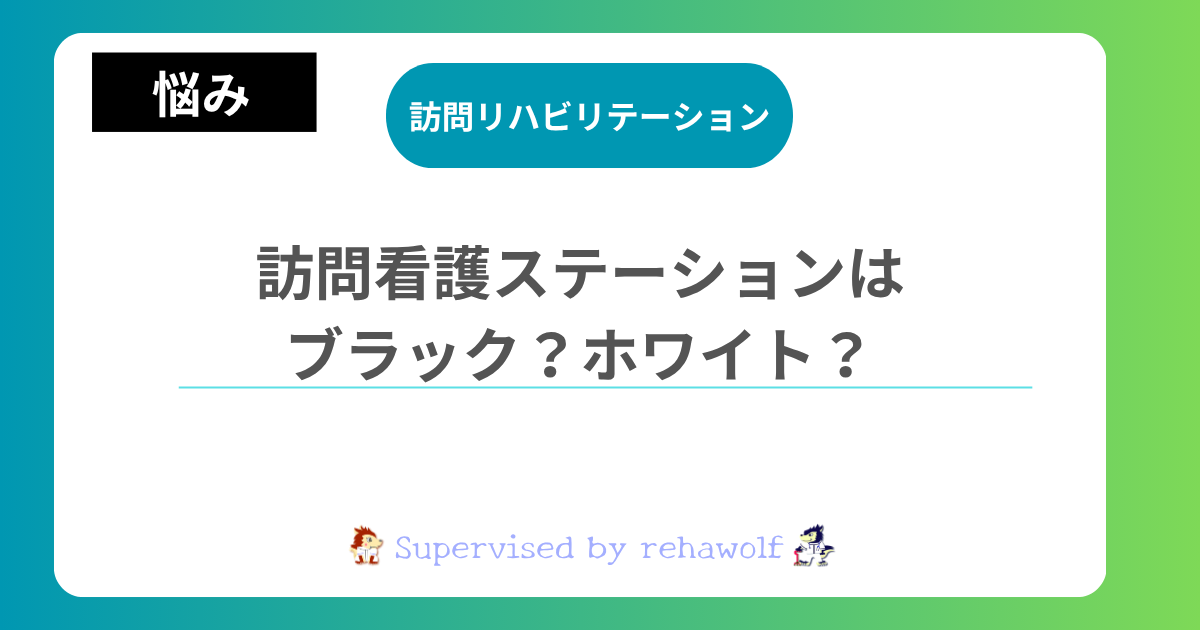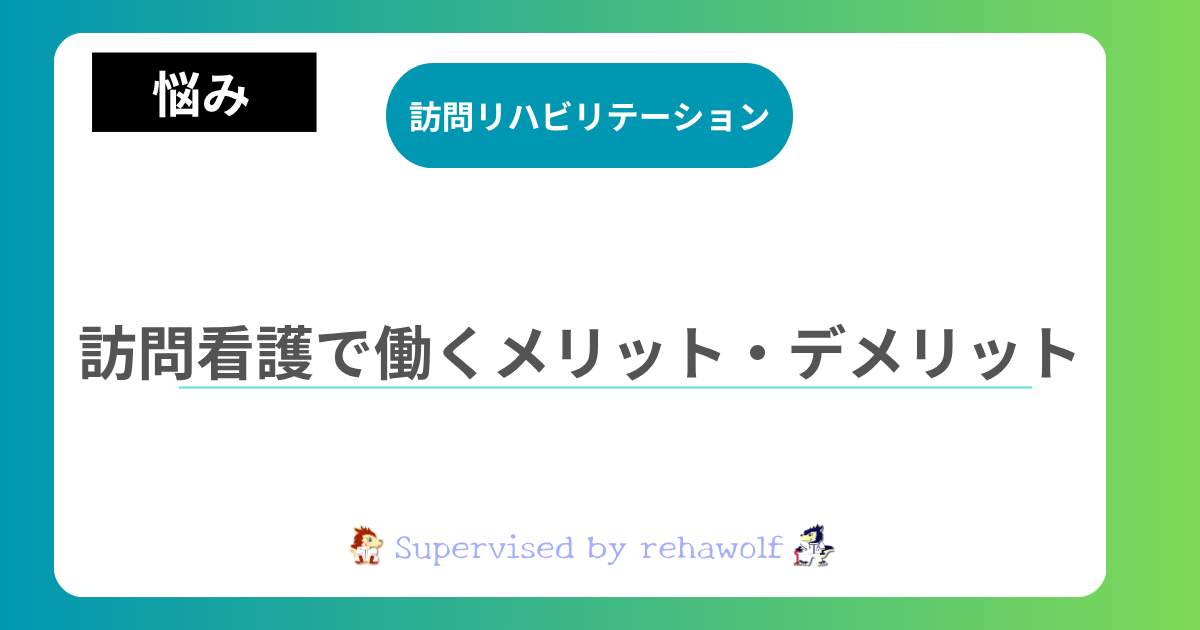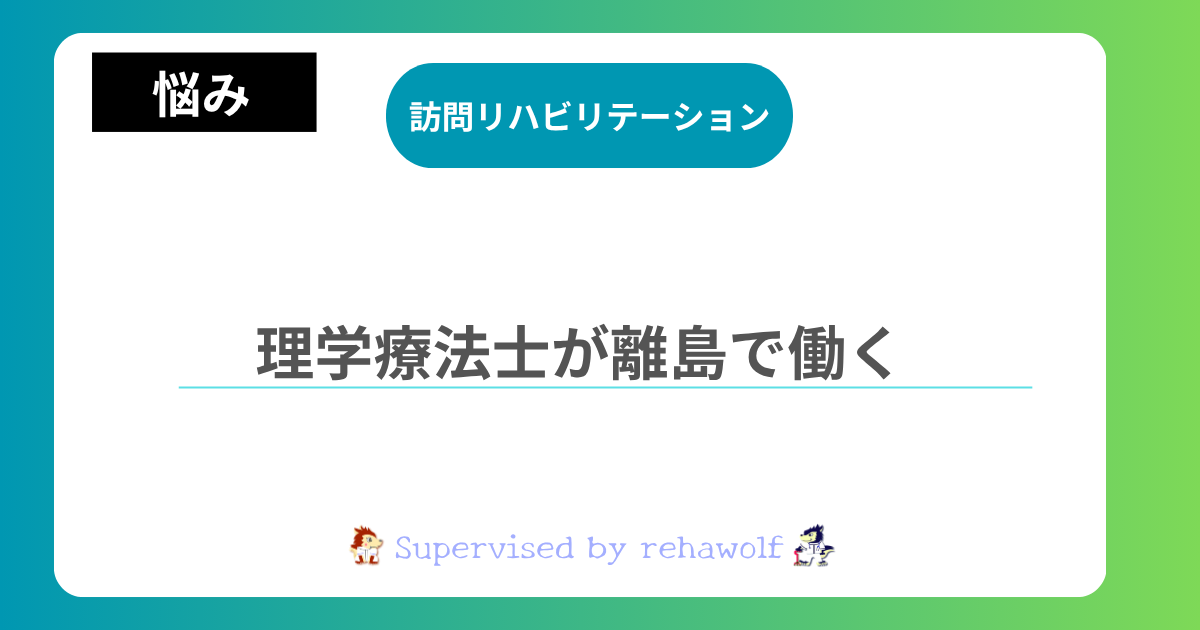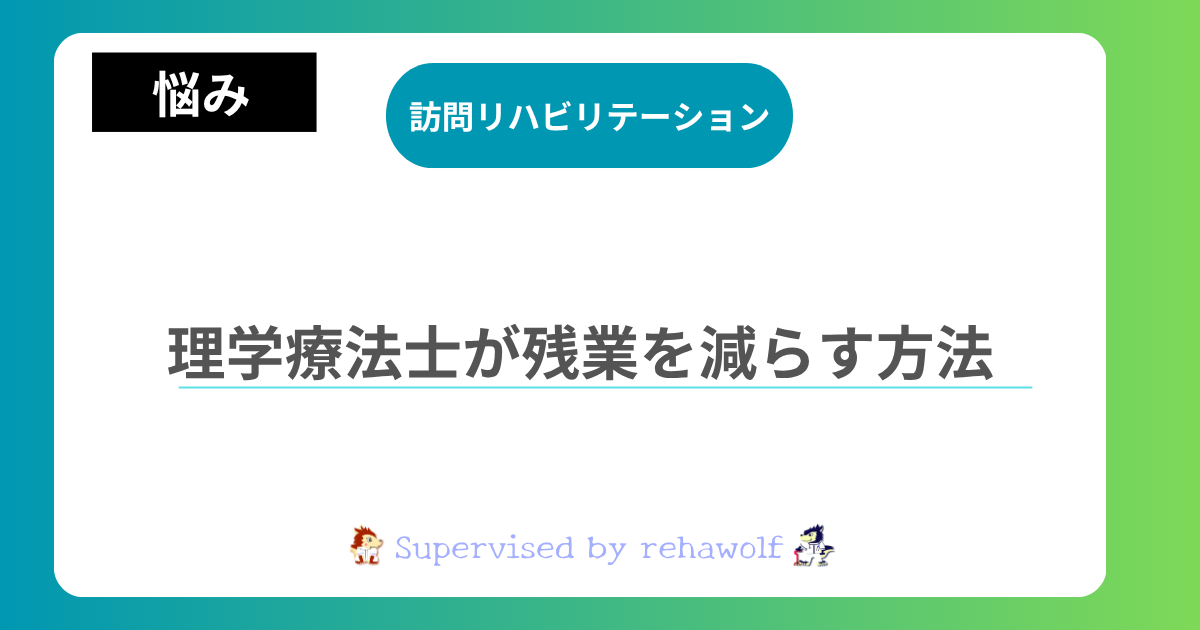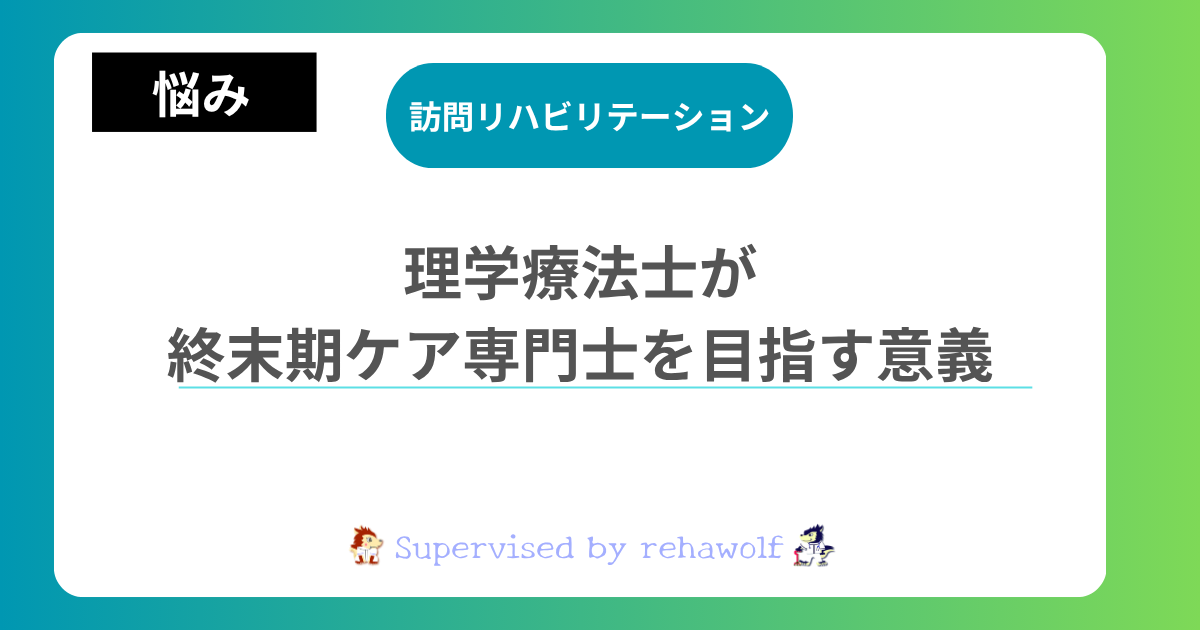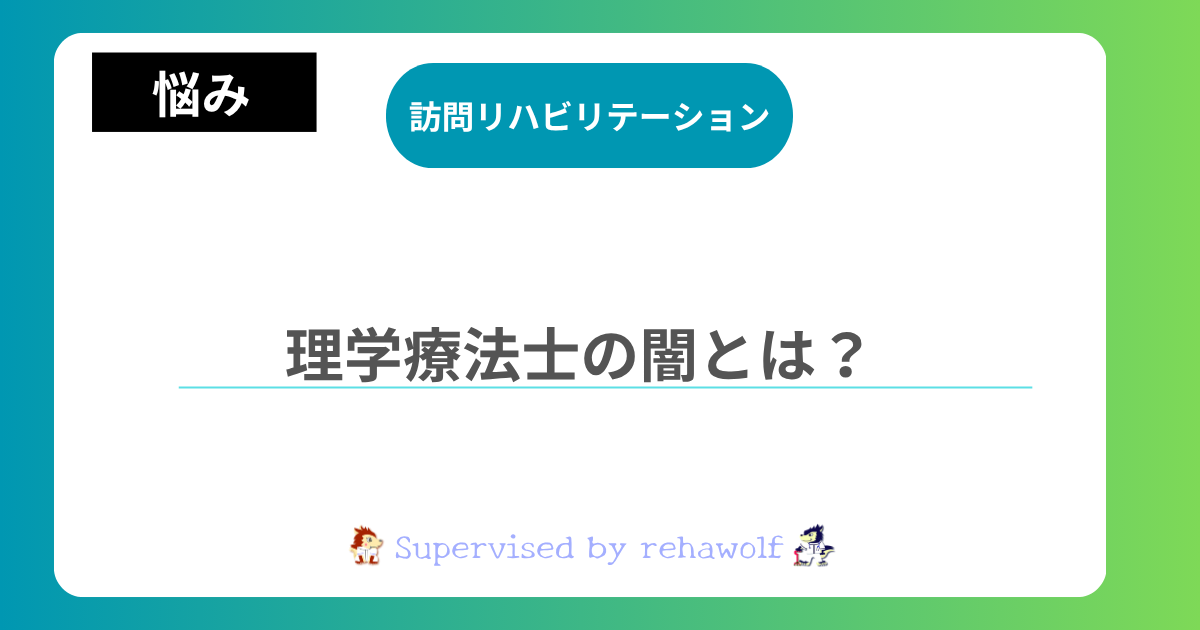理学療法士・作業療法士が就活で落ちるのはなぜ?原因と対策を徹底解説
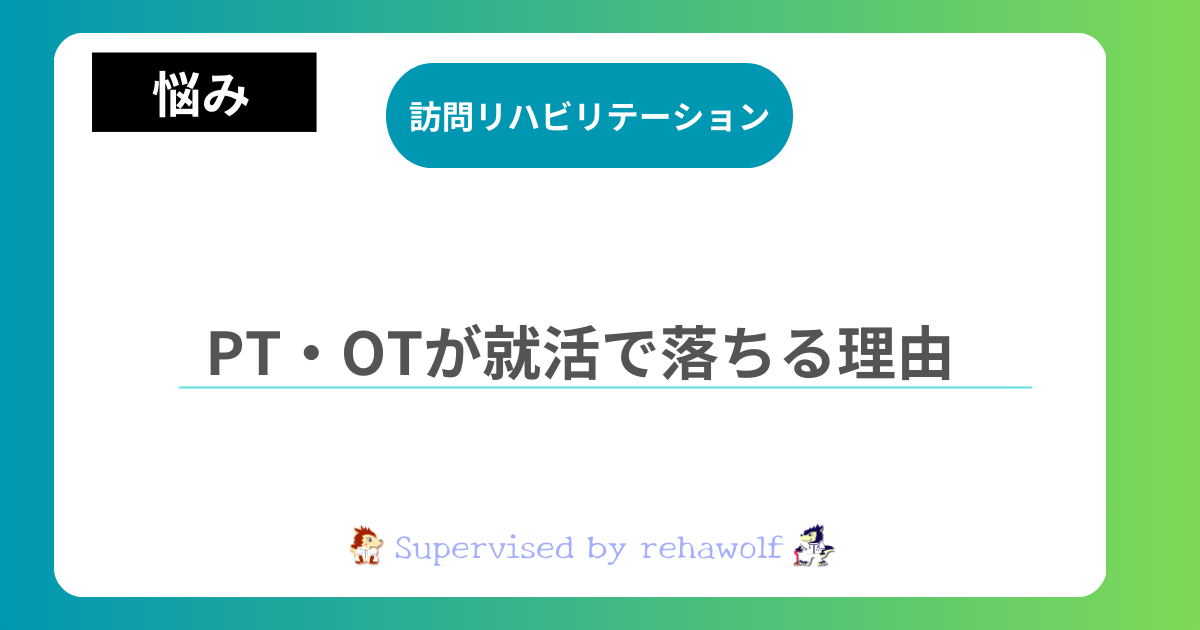
「理学療法士や作業療法士の資格を取れば就職は安泰」と言われた時代もありました。
しかし近年では、就活で不採用が続き「なぜ落ちるのか」と悩む学生や若手セラピストが増えています。
本記事では、理学療法士・作業療法士が就活で落ちる原因を整理し、採用されるために必要な対策を詳しく解説します。
採用担当者が見ているポイントや、自己PR・志望動機の書き方の工夫も紹介しますので、就活中の方はぜひ参考にしてください。
理学療法士・作業療法士でも就活で落ちる時代
かつてはリハビリ職の需要が高く、求人倍率も高水準でした。しかし現在は養成校の増加で新卒セラピストが急増し、地域や施設によっては「採用に競争がある」状況に変化しています。
- 都市部:応募者が集中し、倍率が高い
- 地方:求人が残りやすく、比較的採用されやすい
つまり「どこでも就職できる」わけではなくなり、学生側の準備やアピール力が合否を分けるようになっています。
就活で落ちる主な原因
1. 志望動機が曖昧
「リハビリを通して患者さんを支えたい」といった一般的な志望動機は、誰でも言える内容です。病院や施設の特徴に触れていなければ、熱意が伝わらず不採用につながります。
2. 自己PRが不十分
採用担当者は「一緒に働きたいか」「現場で活躍できるか」を見ています。強みを具体的に伝えられないと、印象が薄くなってしまいます。
3. コミュニケーション力不足
面接での受け答えがぎこちない、表情が硬いなどは大きなマイナス評価につながります。リハビリ職は患者やチームとの信頼関係が重要なため、コミュニケーション力は重視されます。
4. 施設研究が足りない
応募先の理念や特徴を理解していないと、「なぜこの施設なのか」という質問に答えられません。結果として「熱意が足りない」と判断されやすくなります。
5. ビジネスマナーが不十分
挨拶・服装・言葉遣いなどの基本的なマナーが欠けていると、専門職としての信頼性に疑問を持たれます。
採用担当者が見ているポイント
- 患者や利用者に対する姿勢(誠実さ・共感力)
- チームで働ける協調性
- 学び続ける意欲(成長の伸びしろ)
- 勤務条件や勤務地に柔軟に対応できるか
- 組織にフィットする人柄
資格や知識は前提条件であり、それ以上に「人間性」と「協調性」が評価されています。
就活で落ちないための対策
1. 志望動機は具体的に書く
- 施設の特徴(リハビリの強み・対象疾患・教育体制)を調べる
- 自分の経験や将来像とつなげる
例文:
「御院は回復期リハビリに力を入れており、多職種でのチーム医療を重視されています。学生時代に脳卒中患者の実習を経験し、チームで成果を出せた経験があるため、私もその一員として貢献したいと考えています。」
2. 自己PRは強み+エピソードで
- 強み:「傾聴力」「継続力」「協調性」など
- 実例:「実習で患者に寄り添い、小さな成功体験を積み重ねた結果、歩行自立につながった」
3. 面接練習を重ねる
- 学校の先生や友人に模擬面接を依頼する
- 表情・声の大きさ・姿勢をチェックする
- よく聞かれる質問(長所・短所、志望理由、将来のビジョン)を準備する
4. 施設研究を徹底する
- ホームページや求人票で理念や取り組みを確認
- 見学で得た情報を志望動機に盛り込む
- 施設の特色と自分の強みをリンクさせる
5. ビジネスマナーを整える
- 清潔感のある服装・髪型
- 丁寧な言葉遣い
- 姿勢や礼儀を意識する
よくある面接質問と答え方の例
- 「なぜ理学療法士(作業療法士)を目指したのですか?」
→ 原体験や具体的なエピソードを交えると説得力が増す。 - 「当院を志望した理由は?」
→ 施設の特徴に触れ、自分の経験と結びつける。 - 「将来どのようなセラピストになりたいですか?」
→ 専門性を深めたい分野や、地域での役割を具体的に述べる。 - 「学生時代に苦労したことは?」
→ 課題とどう向き合い、成長したかを伝える。
就活に落ちても気にしすぎないことが大切
理学療法士・作業療法士の就活は、必ずしも一回で決まるわけではありません。地域によって倍率や採用基準も異なり、「落ちるのは自分の能力不足」と考える必要はありません。
大切なのは、落ちた経験から改善点を見つけ、次の応募で活かすことです。就活を繰り返すことで面接対応や自己PRが磨かれ、より良い結果につながります。
まとめ
理学療法士・作業療法士が就活で落ちる理由には、
- 志望動機が曖昧
- 自己PRが弱い
- コミュニケーション力不足
- 施設研究不足
- マナーの欠如
といった要因があります。
対策としては、具体的な志望動機・エピソードを交えた自己PR・面接練習・徹底的な施設研究が重要です。
就活に落ちてもそれは「失敗」ではなく、「次につながる経験」です。改善を繰り返しながら、自分に合った職場と出会えるよう前向きに取り組んでいきましょう。