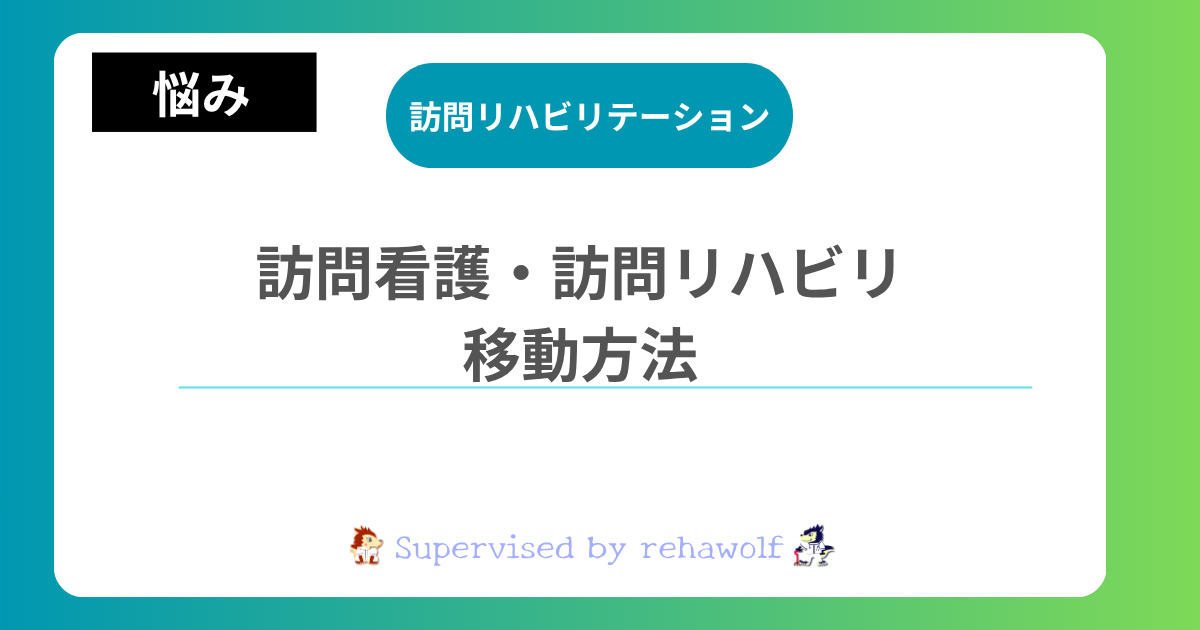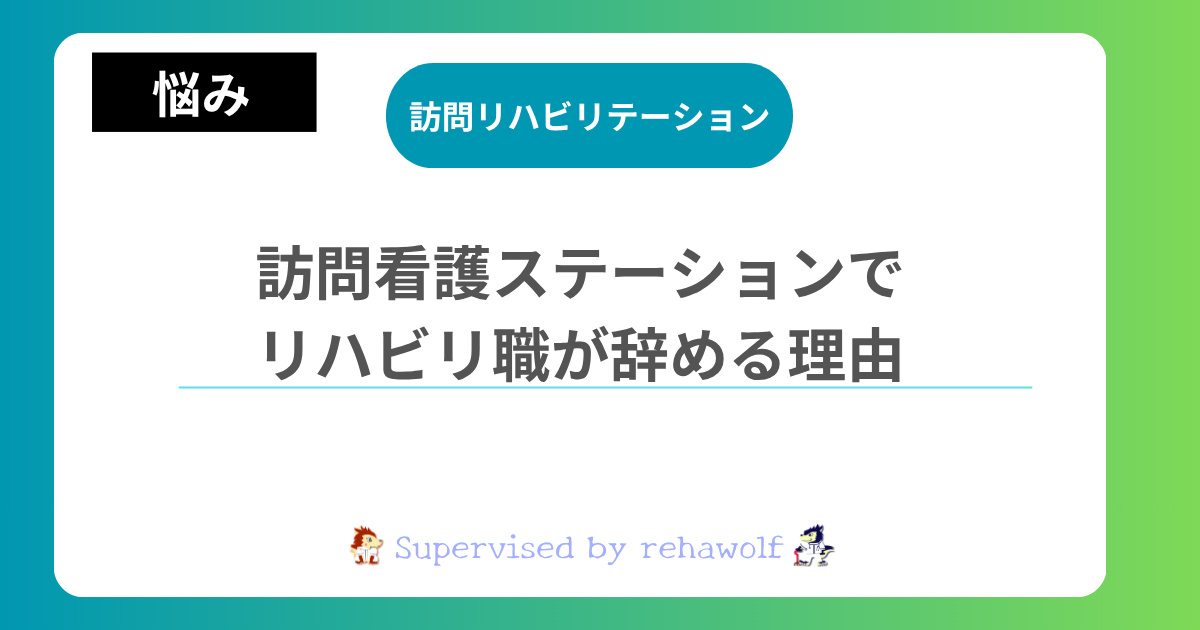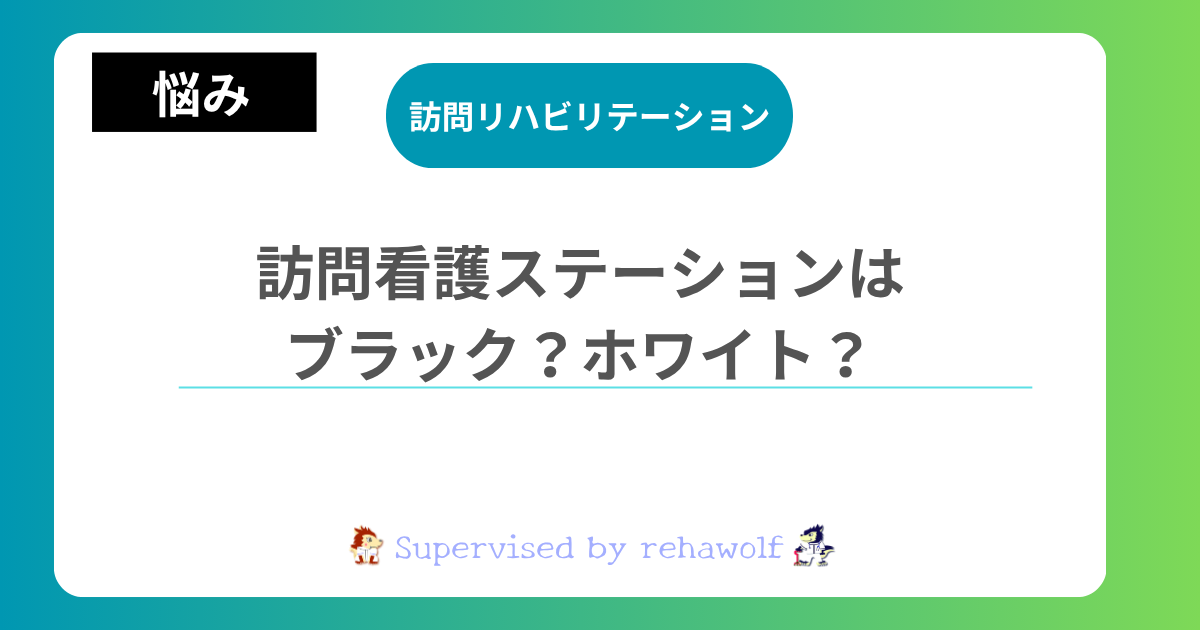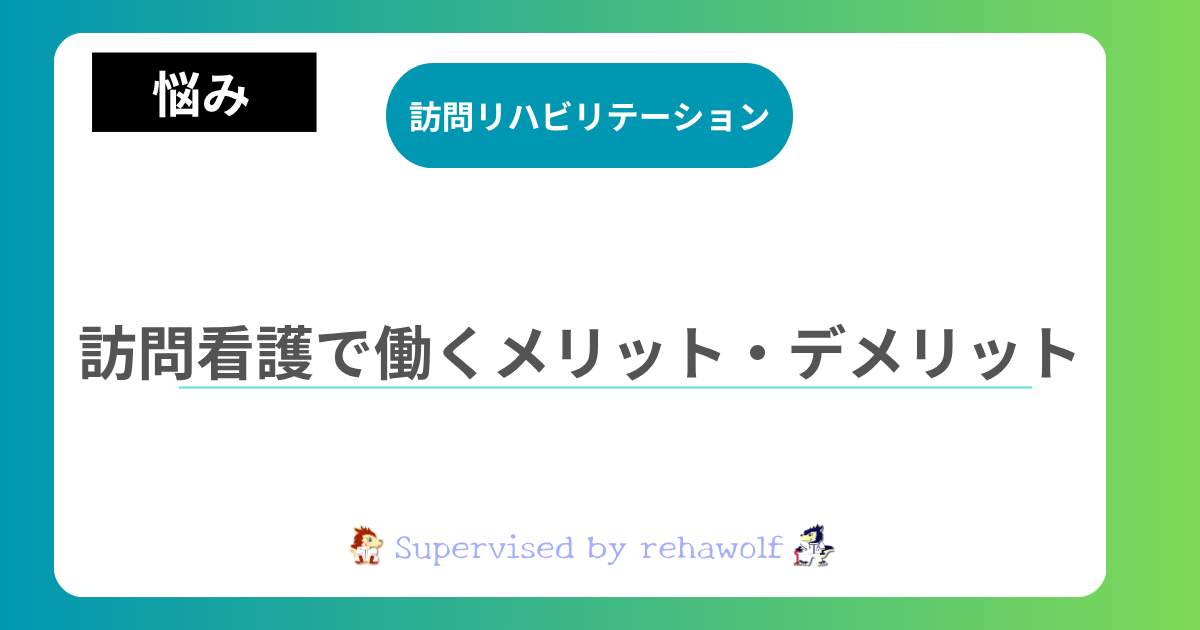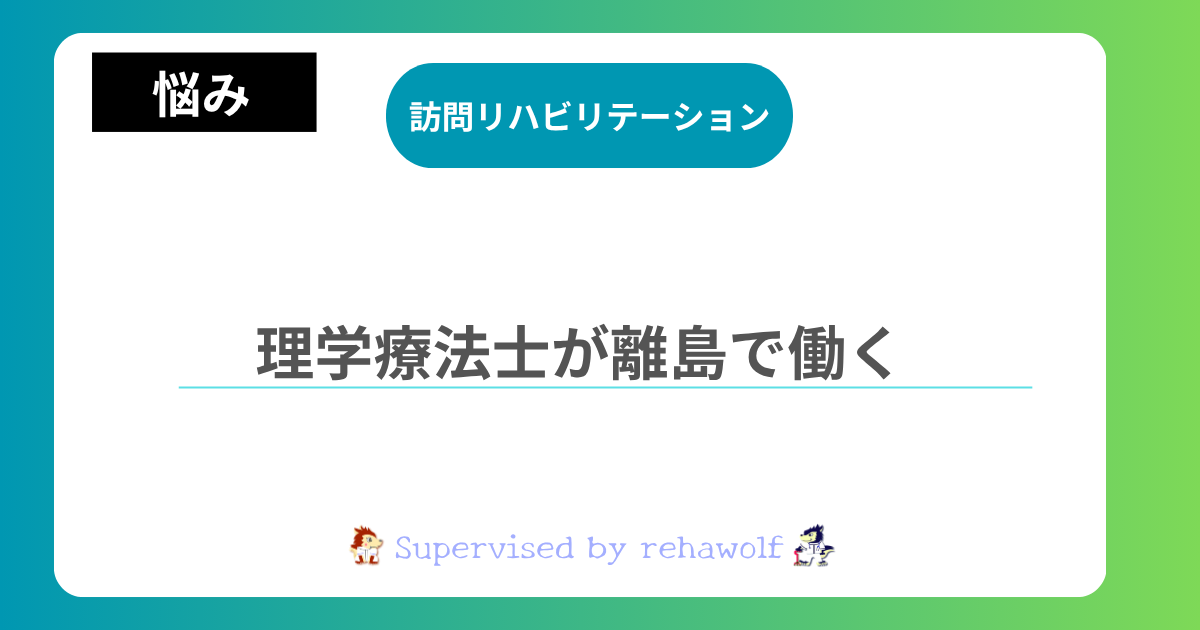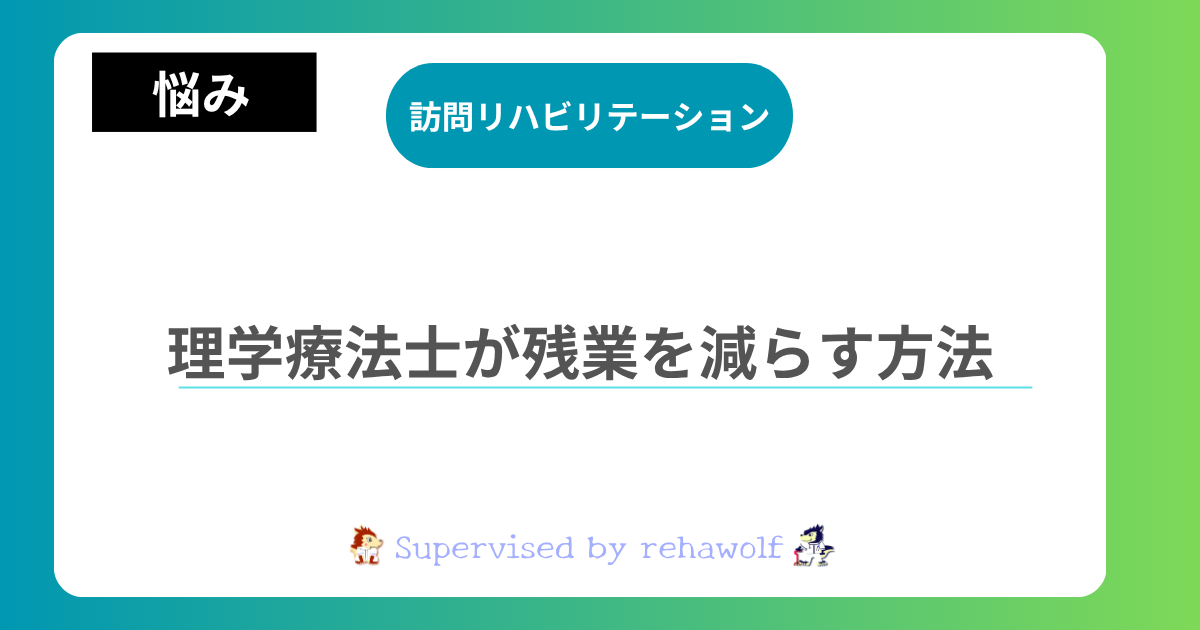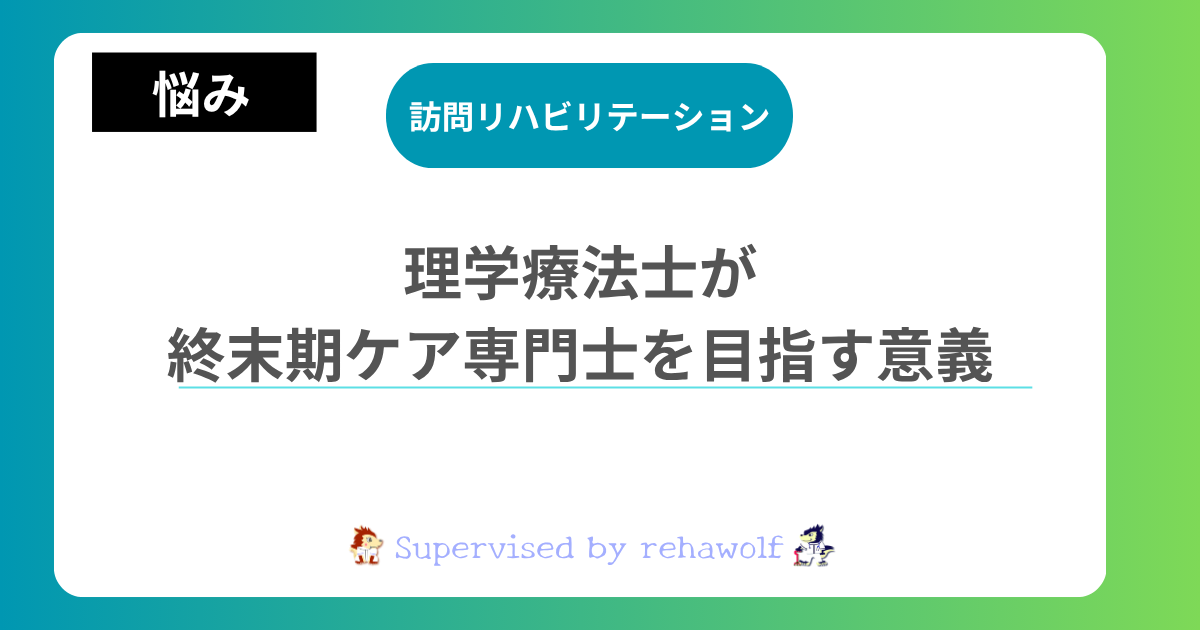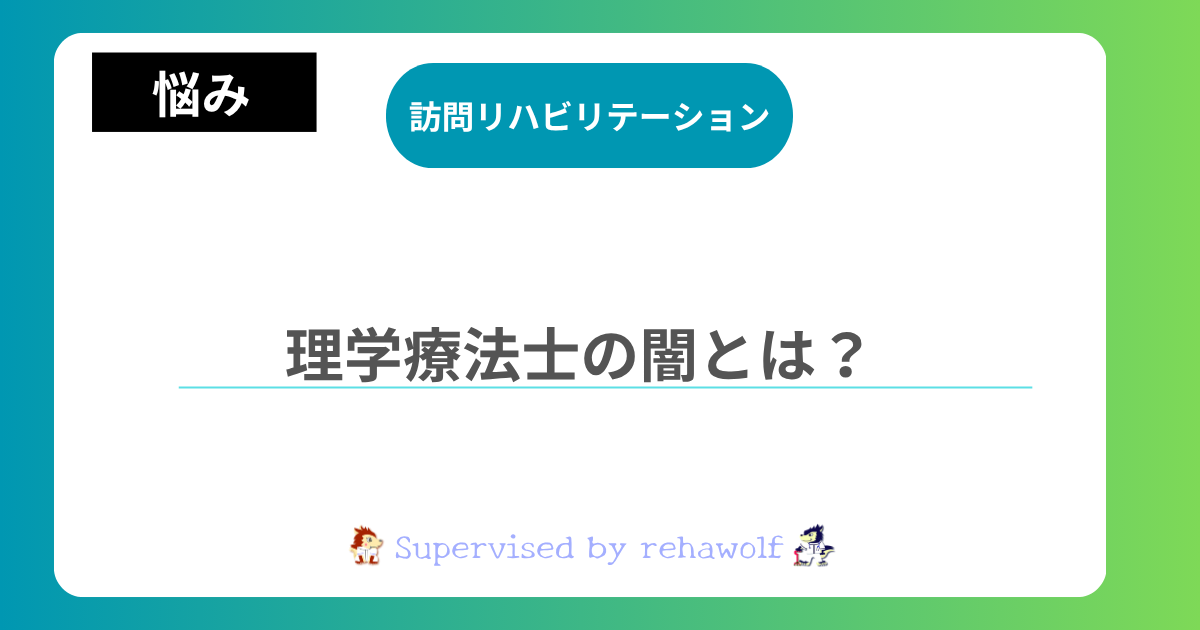訪問リハビリは弔問必要?必要性と注意点を解説
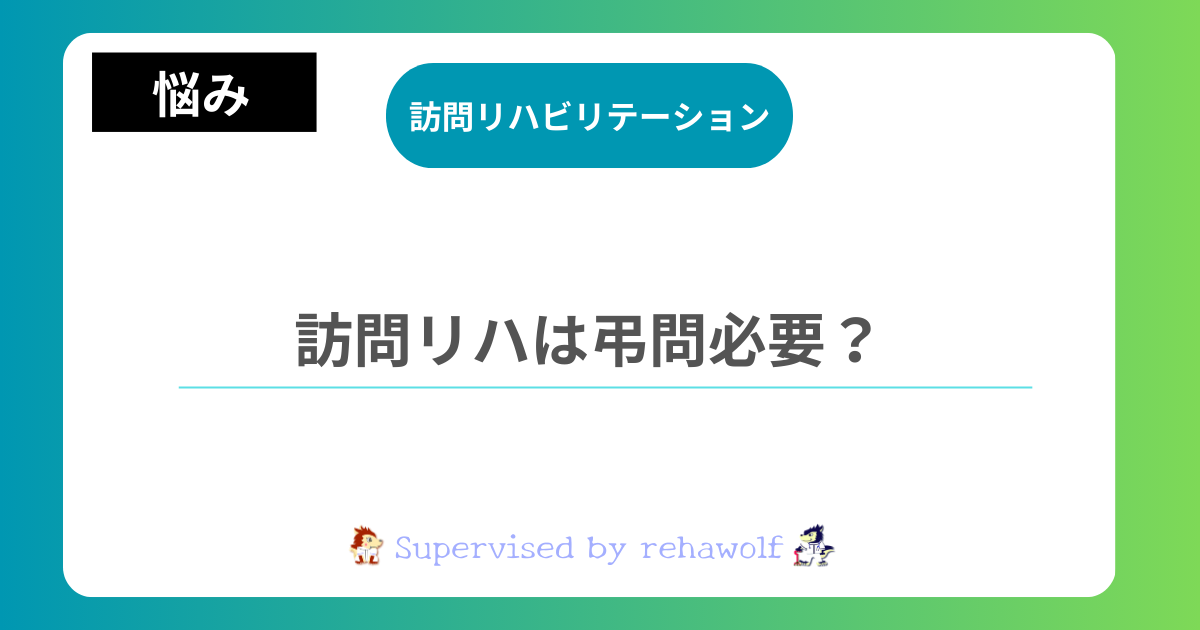
訪問リハビリでは、長期間にわたり利用者と深い関係を築くことが多く、利用者が亡くなった際に弔問が必要かどうか悩むスタッフも多いでしょう。
弔問を望む人もいれば、業務として適切ではないと考える人もおり、その意見はさまざまです。
本記事では、訪問リハビリの利用者に対する弔問が必要かどうか、また弔問する際の注意点について詳しく解説します。
訪問リハビリの利用者に弔問が必要だと思う人の意見
訪問リハビリの利用者に弔問が必要だと思う人の意見を紹介します。
利用者との長期的な関係性があるため
訪問リハビリでは、長期間にわたり利用者の自宅を訪れ、リハビリ支援を続けることが一般的です。そのため、利用者との信頼関係が深まり、まるで家族のように感じることもあります。利用者やその家族から「いつもお世話になっているから、ぜひ来てほしい」と求められることも多く、その気持ちに応えるためにも弔問が必要だと考える人がいます。
また、利用者が亡くなった際には家族から感謝の言葉を受け取ることがあり、「最後まで支えてくれてありがとう」と言われることで、スタッフ自身も感情的に区切りをつけやすいという面もあります。
家族から弔問を望まれるケースが多い
利用者が亡くなった際に、家族から弔問を求められるケースもあります。特に、日頃から家族ともコミュニケーションを取っている場合、利用者本人だけでなく家族とも深い信頼関係が築かれていることが多く、「ぜひ来てください」と依頼されることが少なくありません。
家族からの要望に応えたいという気持ちや、これまでの関係性を考慮して弔問することで、家族にとっても心の支えになると考える人もいます。スタッフとしても、家族の気持ちに寄り添う姿勢が求められるため、弔問の意義を感じるケースが多いようです。
感謝を伝える場として重要だと考える
利用者が亡くなった際に、弔問を行うことは、これまで支援してきたことに対する「感謝」を示す機会と捉える人もいます。リハビリを通じて利用者の生活を支え、その結果として健康状態が改善したり、生活の質が向上したりするケースも多いため、最後に感謝の気持ちを伝えることが大切だという意見です。
訪問リハビリは単なる業務ではなく、人と人との関わりを大切にする仕事だからこそ、最後の別れの場に足を運ぶことは自然な流れであると考えるスタッフも多く見られます。
訪問リハビリの利用者に弔問が不要だと思う人の意見
訪問リハビリの利用者に弔問が不要だと思う人の意見を紹介します。
業務外の対応であり負担が大きい
訪問リハビリはあくまで業務であり、プライベートでの関与を避けるべきだと考える人もいます。特に、業務外の弔問が増えると、スタッフの精神的・肉体的な負担が大きくなることが懸念されます。弔問が義務化されると、他の利用者支援にも支障が出る可能性があり、業務としての線引きが必要だという意見です。
事業所としての対応が不明確で困惑する
事業所として弔問を行うかどうかが不明確な場合、スタッフ個人の判断に任されるケースもあります。事業所の方針が明確でないと、弔問の要不要を判断する際に困惑することが多くなります。個々の判断で対応していると、統一性がなくトラブルの元になる可能性もあり、組織としての指針が必要だという意見が根強いです。
遺族の負担を考慮する必要がある
利用者が亡くなった際、遺族は多忙で精神的に不安定な状態にあります。そこに職員が訪問することで、逆に負担をかけてしまうリスクも考慮するべきです。特に、突然の訪問や過度な弔問は遺族にとって迷惑となるケースもあり、むしろ配慮すべきだという意見も多く見られます。
訪問リハビリスタッフが弔問する場合の注意点
訪問リハビリスタッフが弔問を行う場合には、以下の点に注意する必要があります。
- 事前に家族へ確認を取る
- 勝手に訪問するとかえって迷惑となるため、家族に相談してから決めましょう。
- 個人として行うのか、事業所として行うのかを明確にする
- 事業所の指針がある場合は従い、個人判断で行う際は自己責任であることを理解しておくことが大切です。
- 適切な服装とマナーを守る
- 弔問時の服装や言葉遣いには十分に配慮し、遺族の気持ちに寄り添った対応を心がけましょう。
- 短時間での訪問を心掛ける
- 長居すると遺族に負担をかけるため、短くても丁寧な対応を心がけましょう。
まとめ
訪問リハビリにおける弔問の必要性には賛否があり、その判断は状況や家族の意向によって異なります。利用者との関係が深ければ、弔問を望む気持ちも理解できますが、業務としての適切さや家族の負担を考慮することも重要です。弔問を行う際には、家族への確認を怠らず、適切なマナーを守ることが求められます。
事業所としての方針を明確にし、スタッフが迷わないようガイドラインを整備することも大切です。弔問に関しては、感情だけでなく業務としてのバランスを保ち、冷静に対応することが求められます。