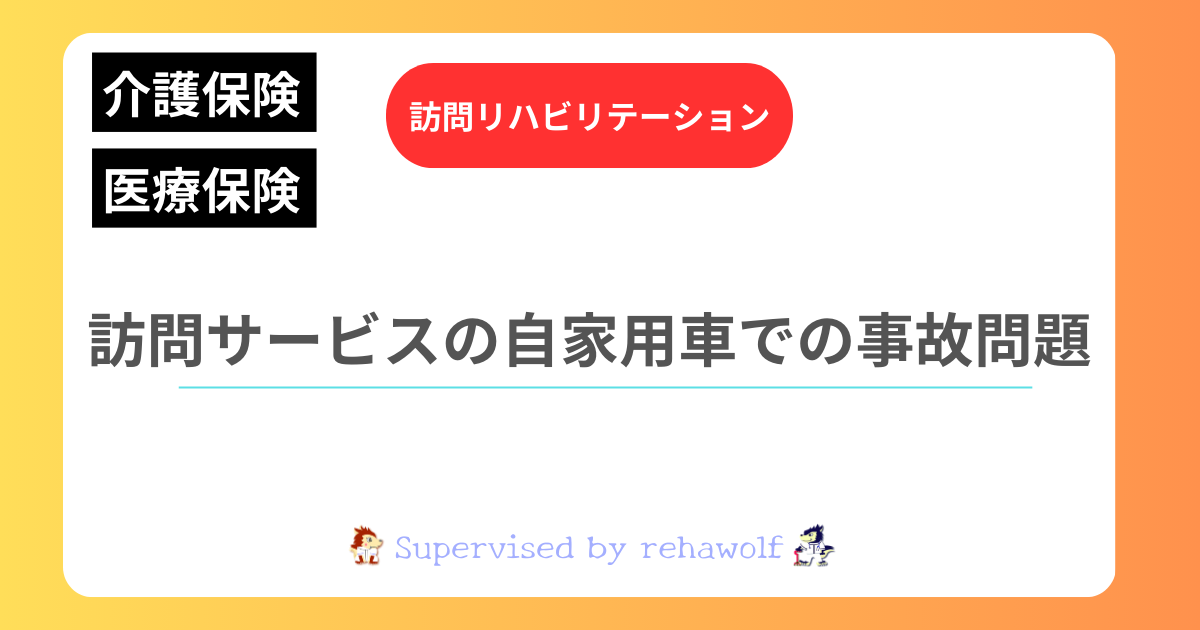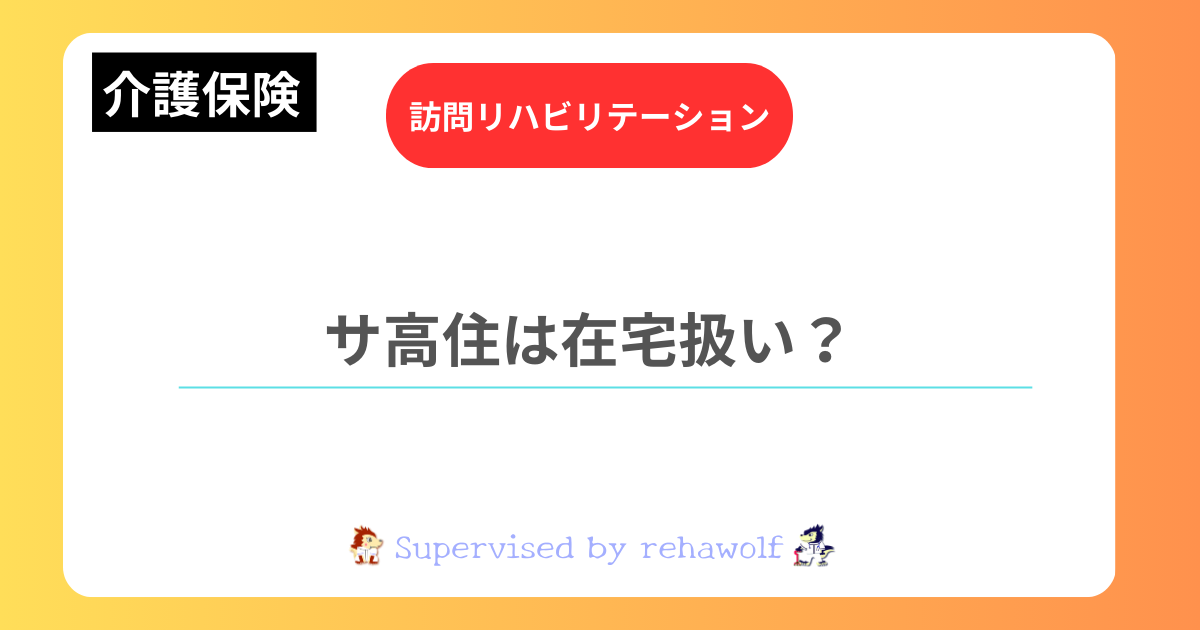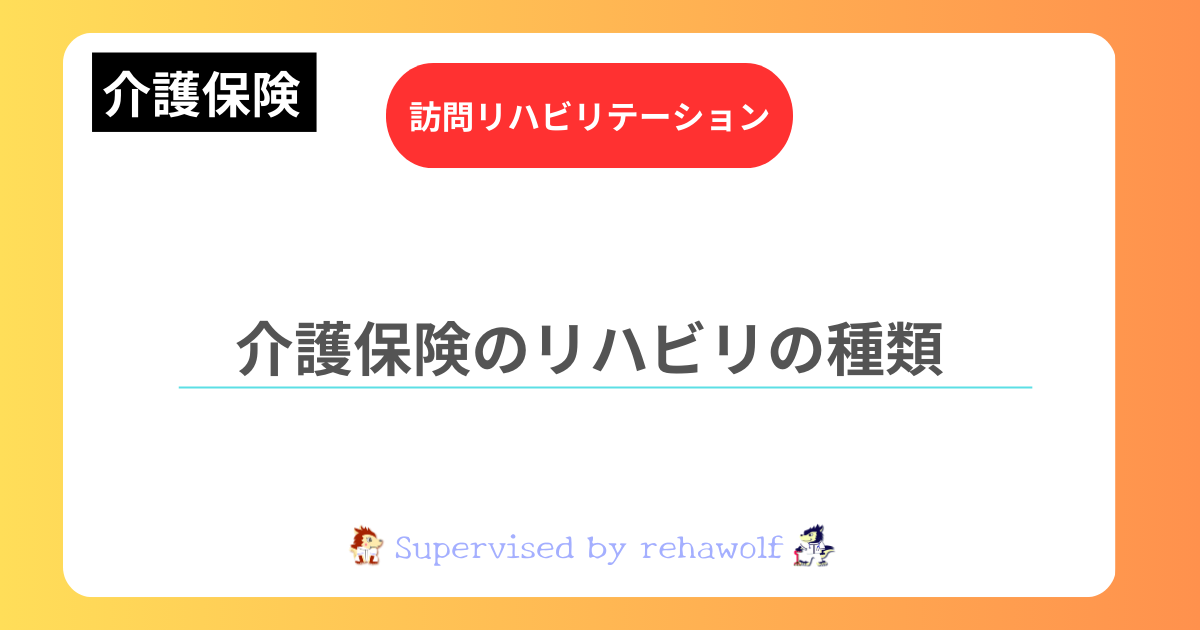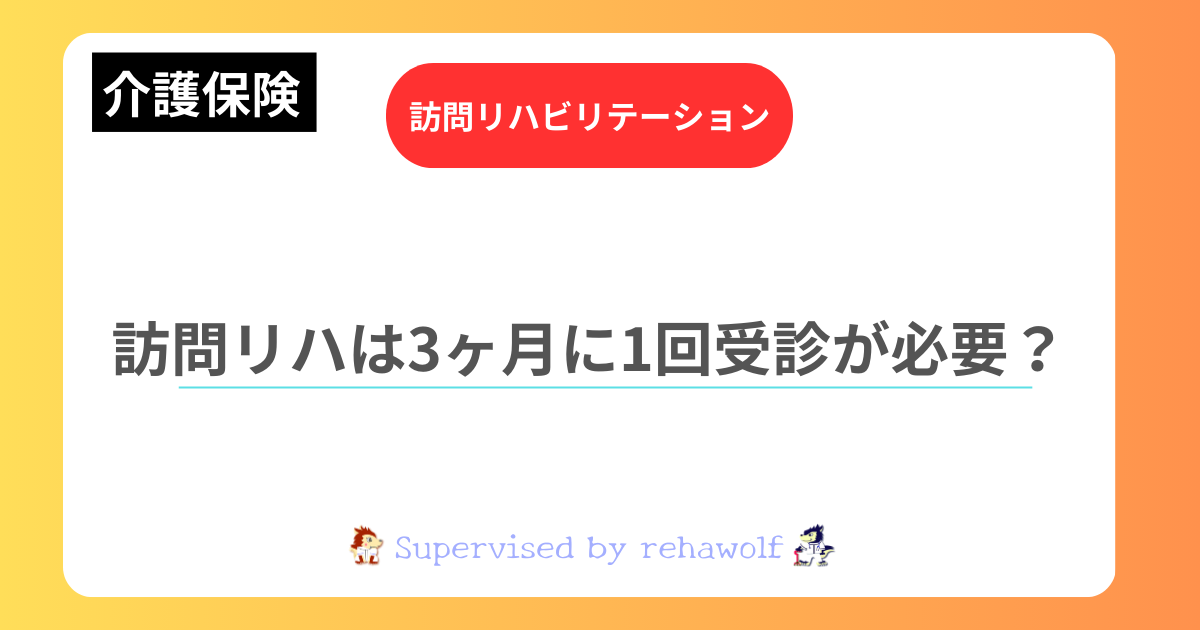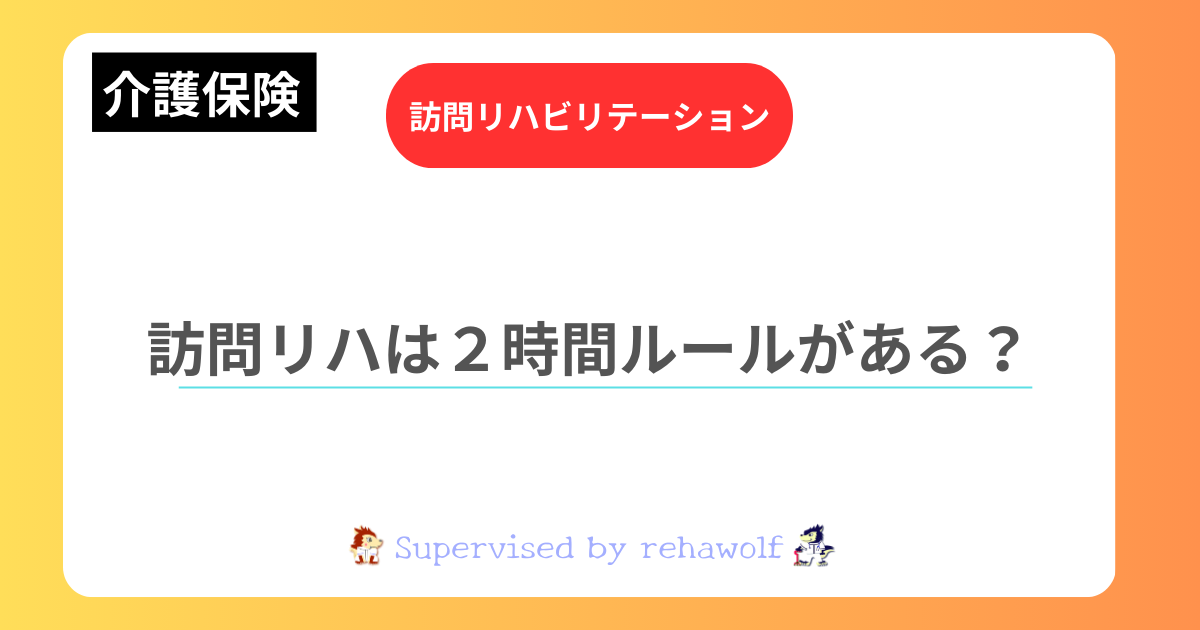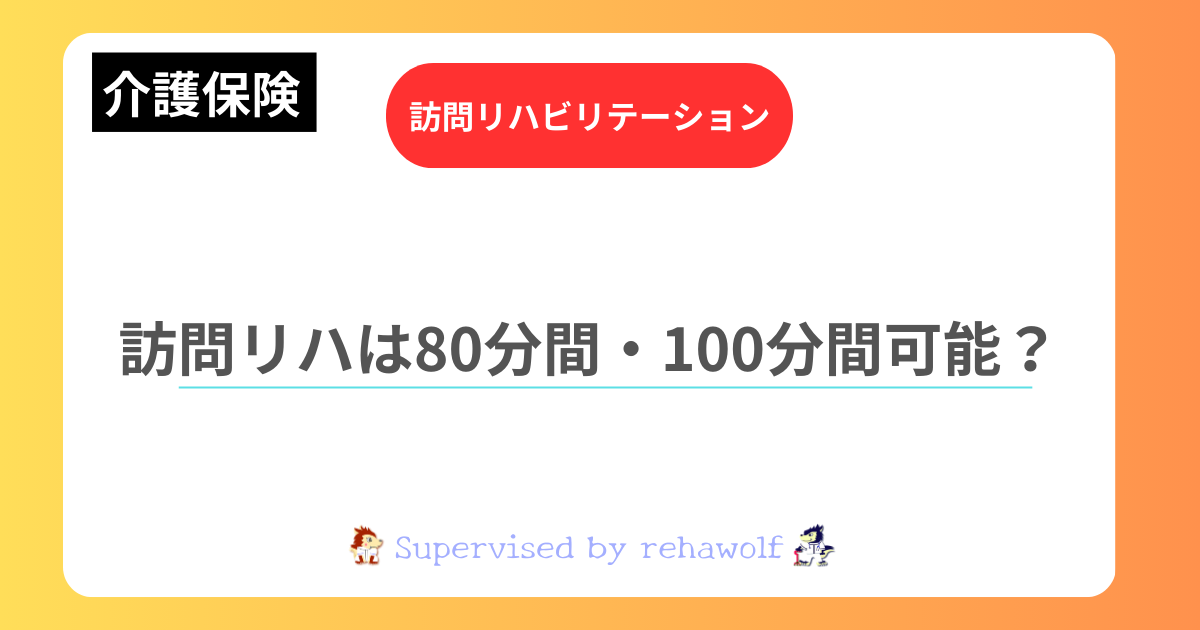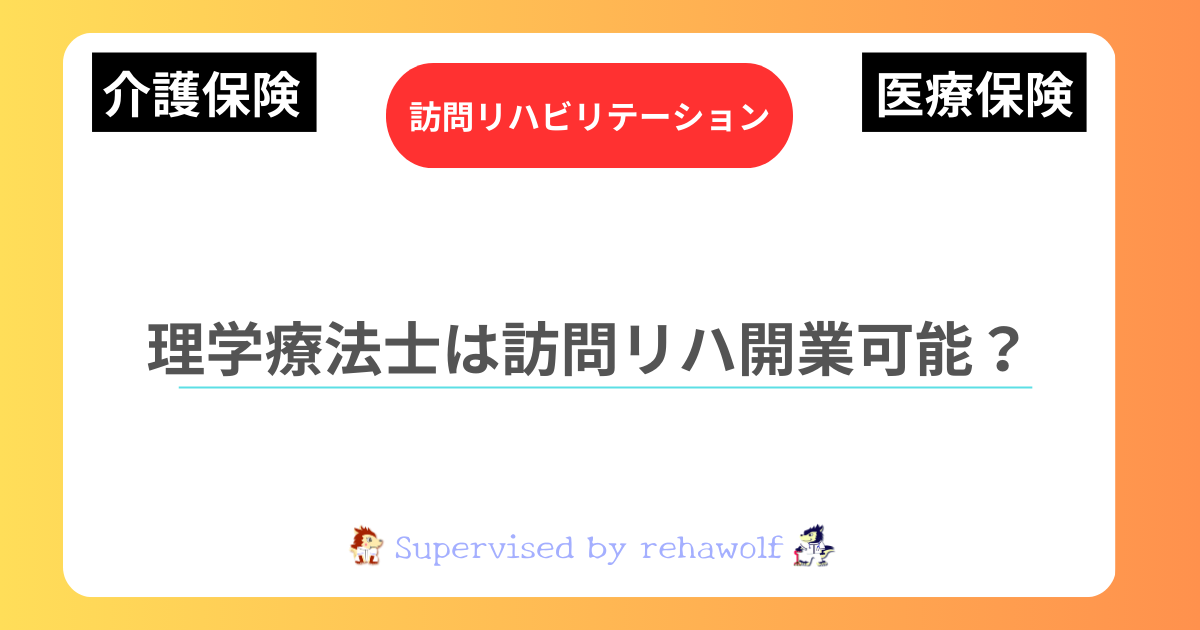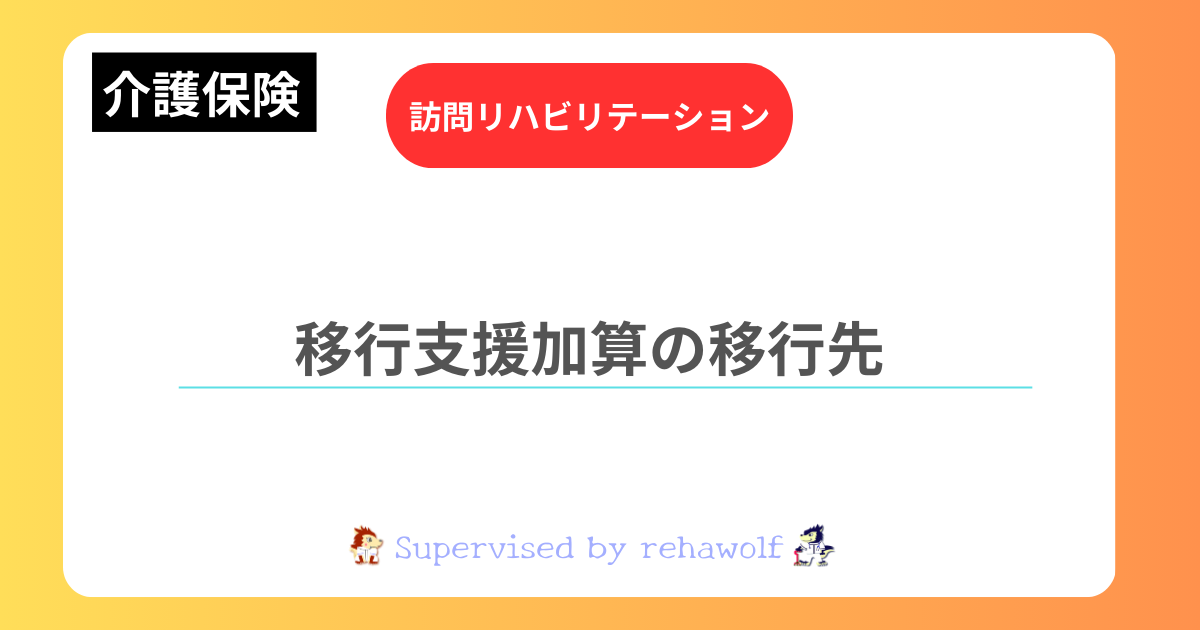訪問リハビリと通所リハビリは併用可能?併用禁止?わかりやすく解説
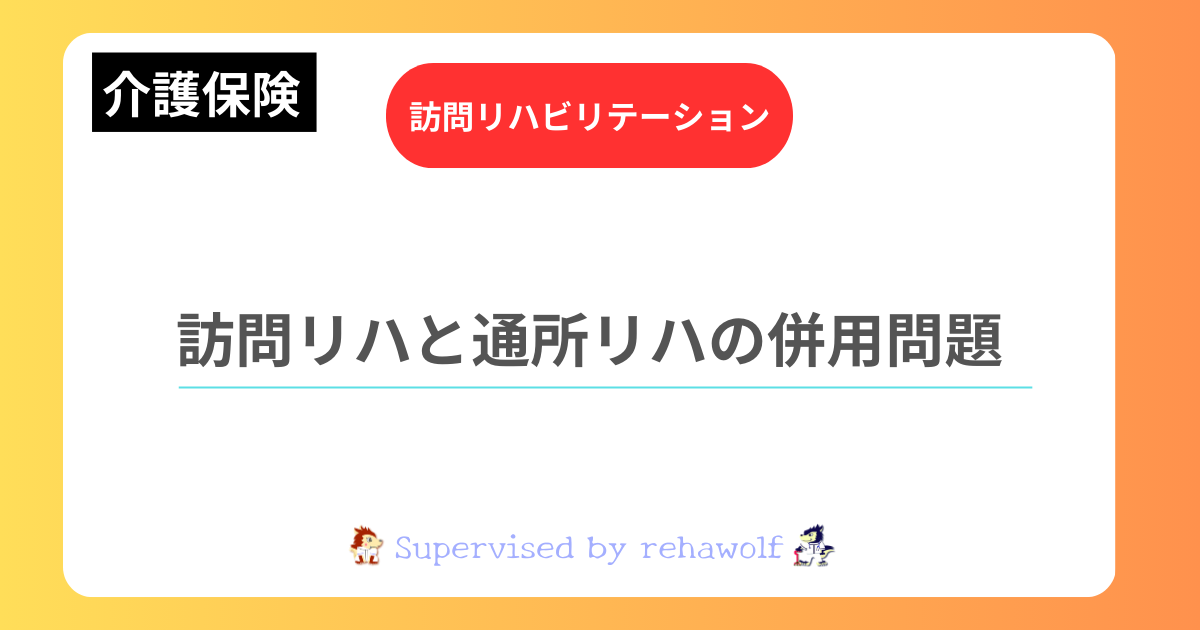
訪問リハビリテーションや通所リハビリテーション(デイケア)を運営していたり、ケアプランを作成しているケアマネジャーは一度は『訪問リハビリと通所リハビリは併用できるの?』と悩んだことがあると思います。
結論、訪問リハビリと通所リハビリは併用可能です。
しかし、その根拠を正しく説明できる人もあまりいないと思います。
この記事を読めば、自信を持って『訪問リハビリと通所リハビリは併用可能です!』と言えるようになります。
この記事を読むとわかることは以下の通りです。
- 訪問リハビリと通所リハビリが併用可能という根拠がわかる
- 訪問リハビリと通所リハビリの厚労省の根拠がわかる
- 訪問リハビリと通所リハビリの併用する主な理由がわかる
- 訪問リハビリと通所リハビリを併用するときのケアプランの書き方がわかる
- 訪問リハビリと通所リハビリを同日に2サービス利用できるかがわかる
- 訪問リハビリと通所リハビリを要支援者も併用できるかがわかる
この記事では『訪問リハビリテーションと通所リハビリテーション(デイケア)の併用問題』について、誰でもわかりやすい内容で紹介します。
ぜひ、事業所運営に役立てていただければ嬉しいです。
訪問リハビリと通所リハビリは併用可能?禁止?
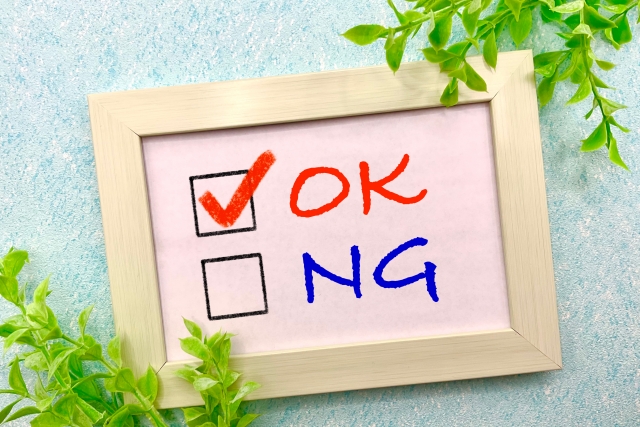
訪問リハビリと通所リハビリは併用することが可能です。
ひと昔前は、「通所介護(デイサービス)と訪問リハビリは併用可能だけど、通所リハビリ(デイケア)と訪問リハビリは併用不可能」という時代もありました。
よって、ひと昔前のケアマネジャーは『併用ダメ!』という人もいるかもしれませんね。
現在は、訪問リハビリと併用が不可能な介護サービスはありませんので、しっかりと正しい知識を身につける必要があります。
訪問リハビリと通所リハビリの併用可能な厚生労働省の根拠
訪問リハビリと通所リハビリが併用可能という厚生労働省の根拠について示していきます。
まず、『訪問リハビリと通所リハビリは併用可能です。』という文章は厚労省からは出ておりません。
逆に、『訪問リハビリと通所リハビリは併用不可能です。』という文章も厚労省からは出ておりません。
全ての法令において「これはOK」「これはNG」という表現は当然ありません。
ですので、「NG」と明記されていない限りは、通常OKと捉えることが一般的だと思います。
そもそもの話をします。
そもそも、訪問リハビリテーションは通院困難な人に提供するサービスです。
原則、通所系サービスを利用する必要がありますが、条件によっては訪問リハビリテーションが利用可能となります。
それを正しく理解しておきましょう。
訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、指定通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指定訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきということである。
出典)厚生労働省
上記を前提とした後に厚労省から出ている下記のような文章を見ると、厚生労働省は訪問リハビリテーションと通所リハビリテーション(デイケア)の併用を許しているということがわかります。
Q.サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
A.居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議を実施しても差し支えない。出典)介護サービス関係Q&A
【訪問リハ及び通所リハを同一事業者が提供する場合の運営の効率化】
訪問・通所リハビリテーションの両サービスを、同一事業者が提供する場合の運営の効率化を推進するため、リハビリテーション計画、リハビリテーションに関する利用者等の同意書、サービス実施状況の診療記録への記載等を効果的・効率的に実施できるよう見直す。(運営基準事項)出典)厚生労働省
訪問リハビリと通所リハビリの併用理由はどのようなものがあるのか?
訪問リハビリと通所リハビリの併用理由はさまざまです。
原則、自宅環境でしかできないことを実施するのが訪問リハビリです。
ここでは一例を紹介します。
- 訪問リハビリ:実際に自宅の浴槽を用いた入浴動作練習
- 通所リハビリ:入浴動作獲得のための筋力練習
- 訪問リハビリ:自宅の生活環境下での転倒予防のための生活動線の歩行練習
- 通所リハビリ:自宅環境を想定した歩行練習、筋力練習
- 訪問リハビリ:自宅環境下でのトイレ動作練習
- 通所リハビリ:トイレ動作獲得のための筋力練習やバランス練習
訪問リハビリと通所リハビリの併用をケアプランにどう書けば良いか?
訪問リハビリと通所リハビリを併用するときのケアプランの記載例を紹介します。
気をつけるポイントとしては、通所リハビリでもできることは通所リハビリで実施して、訪問リハビリでは訪問リハビリでしかできないことを明確にすることが大切です。
訪問リハビリでしかできないことの代表例は『自宅環境下で・・・・・』です。
ケアプランに訪問リハビリの必要性を記載するときは『自宅環境下での・・・・』を付け加えると良いと思います。
ケアプランの一例を紹介します。
例1: 在宅での生活動作向上を目指す場合
背景:
利用者は片麻痺があり、在宅生活を続けるために日常生活動作(ADL)の向上を希望。訪問リハビリでは自宅環境でしか実現できない具体的な訓練や指導を提供し、通所リハビリで集中的な機能訓練を行う計画。
ケアプラン記載例:
目標:
自宅でトイレや着替えの動作を自立して行えるようにする。
<訪問リハビリ内容>
・実際の自宅トイレやベッドを使用して移動や移乗の方法を訓練。
・自宅環境に適した安全対策や動作指導を提供。
・家族が日常的に行う介助方法を、現場で具体的に指導。
<通所リハビリ内容>
・下肢筋力やバランス機能向上のための運動療法。
・集団プログラムでの社会交流を通じた意欲向上。
例2: 退院後の生活に向けた準備をする場合
背景:
利用者は大腿骨骨折術後の退院患者で、在宅復帰を目指してリハビリ中。訪問リハビリでは自宅の間取りや環境を踏まえた訓練を行い、通所リハビリで集中的な機能訓練を併用。
ケアプラン記載例:
目標:
歩行器を使って屋内を安全に移動できるようにする。
<訪問リハビリ内容>
・居室内や廊下での歩行訓練を実施し、家具や動線に合わせた動き方を指導。
・玄関や浴室などの移動が困難な場所での実践的な動作練習を実施。
・転倒防止のため、利用者宅の具体的なリスク箇所を特定し、改善案を提案。
<通所リハビリ内容>
・骨折後の筋力回復を目的とした個別リハビリ。
・歩行訓練および階段昇降訓練を実施。
例3: 認知症ケアを重視した場合
背景:
利用者は軽度の認知症があり、身体機能維持と認知機能の低下を防ぐため、訪問リハビリで自宅環境に即した指導を行い、通所リハビリで集団プログラムを併用。
ケアプラン記載例:
目標:
日常生活をスムーズに行い、認知機能を維持する。
<訪問リハビリ内容>
・利用者が毎日使用するキッチンや居室で、物の配置や動作の効率化を指導。
・自宅で実際に行う動作(食事準備や片付け)を介して、認知機能を刺激。
・家族とともに、安全に暮らすための環境改善や生活習慣の工夫を提案。
<通所リハビリ内容>
・軽い有酸素運動や指先を使ったアクティビティで認知機能を刺激。
・他の利用者との交流を通じた社会性の維持。
訪問リハビリと通所リハビリを同日に両方利用できるのか?
訪問リハビリと通所リハビリを同日に利用することも可能です。
例えば下記のような利用方法があります。
【訪問リハビリと通所リハビリの同日利用例】
火曜日のAMに通所リハビリテーションに通い、火曜日のPM(15:00〜16:00)に訪問リハビリテーションを利用する。
介護保険制度では、例外を除き、サービス提供時間が重なっていなければサービスを同じ日に受けることも可能とされています。
訪問リハビリと通所リハビリは要支援者も併用できるのか?
訪問リハビリと通所リハビリは要支援者も併用して利用することも可能です。
ただし、要支援者は介護保険の限度額などが少ないため、限度額的に併用できない場合もあります。
また、注意点として、訪問リハビリテーションを利用する要支援者すべてに当てはまることですが、利用してから3ヶ月経過してサービスを継続する場合は『事業所の医師が利用者に対して3月以上のリハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーションの継続利用が必要な理由、その他介護サービスの併用と移行の見通しをリハビリテーションの見通し・継続理由に記載する。』というルールもあります。