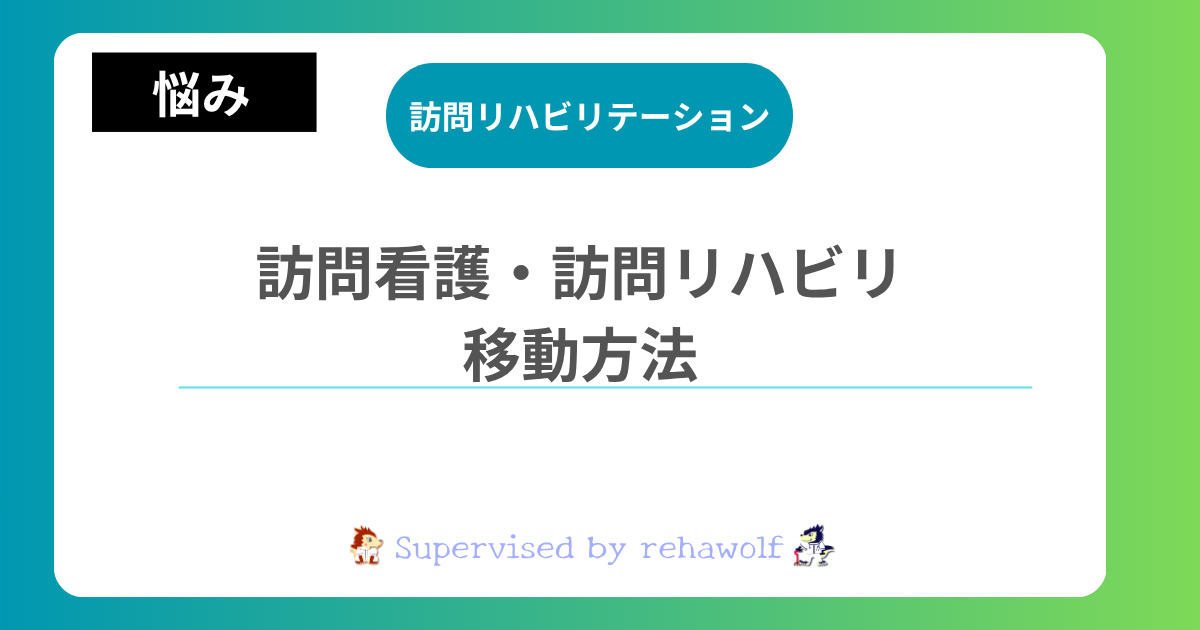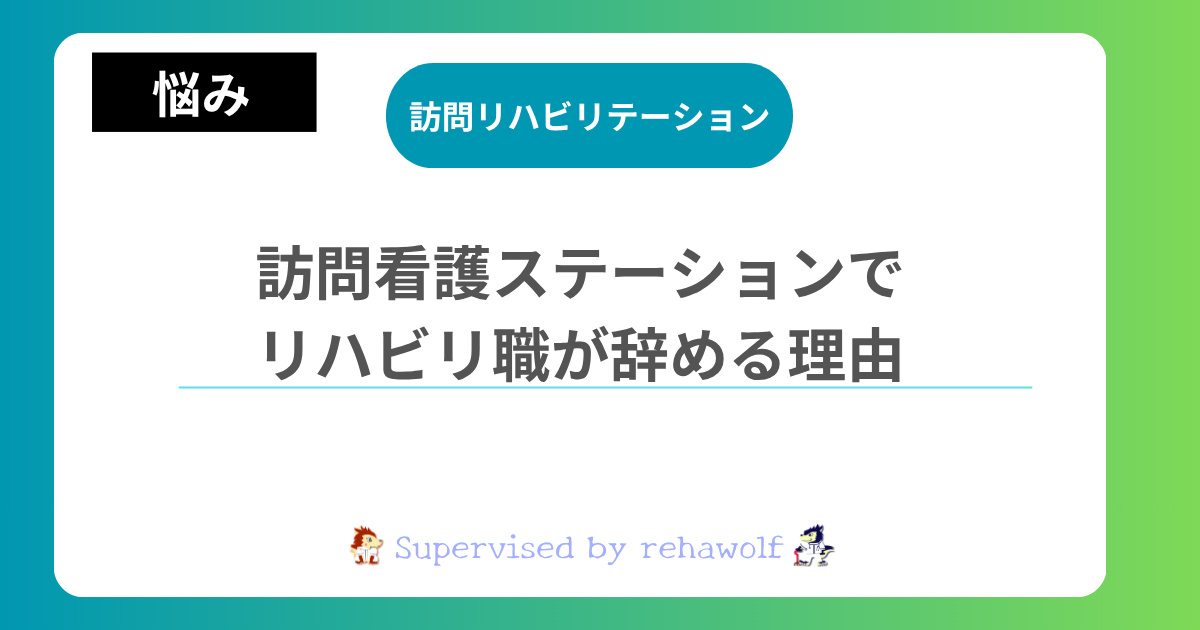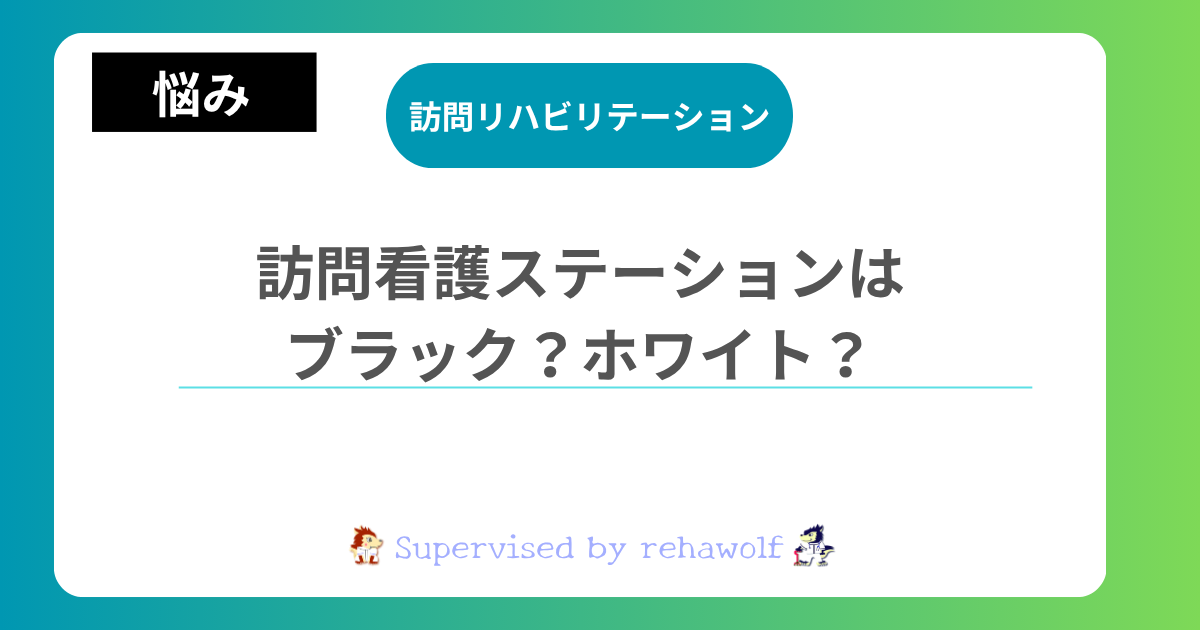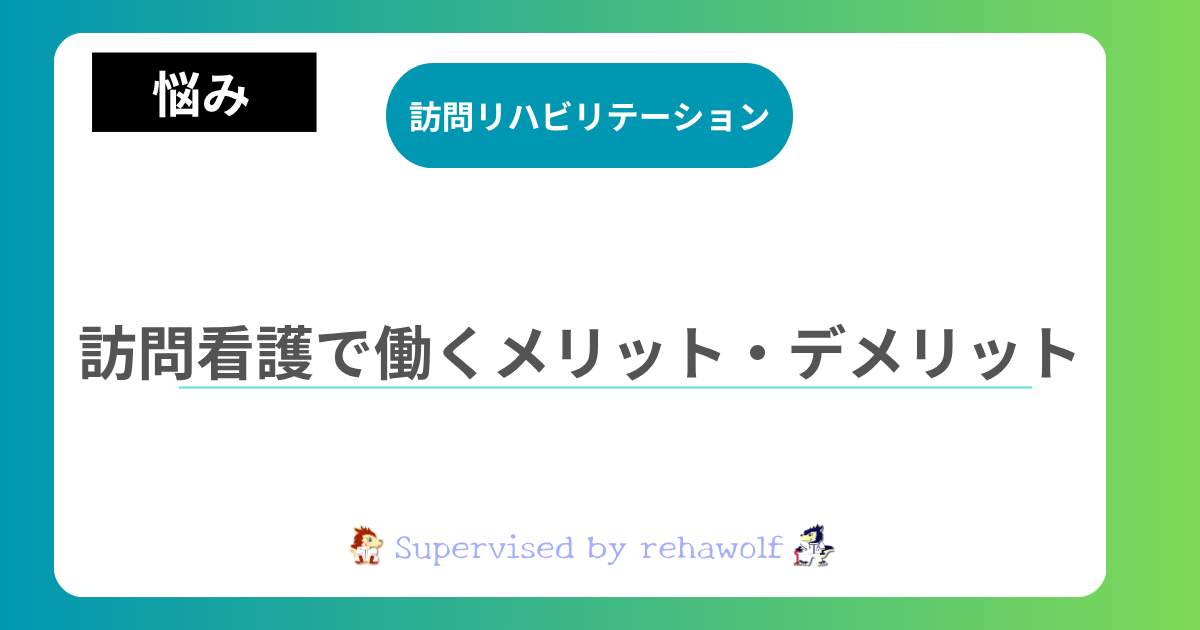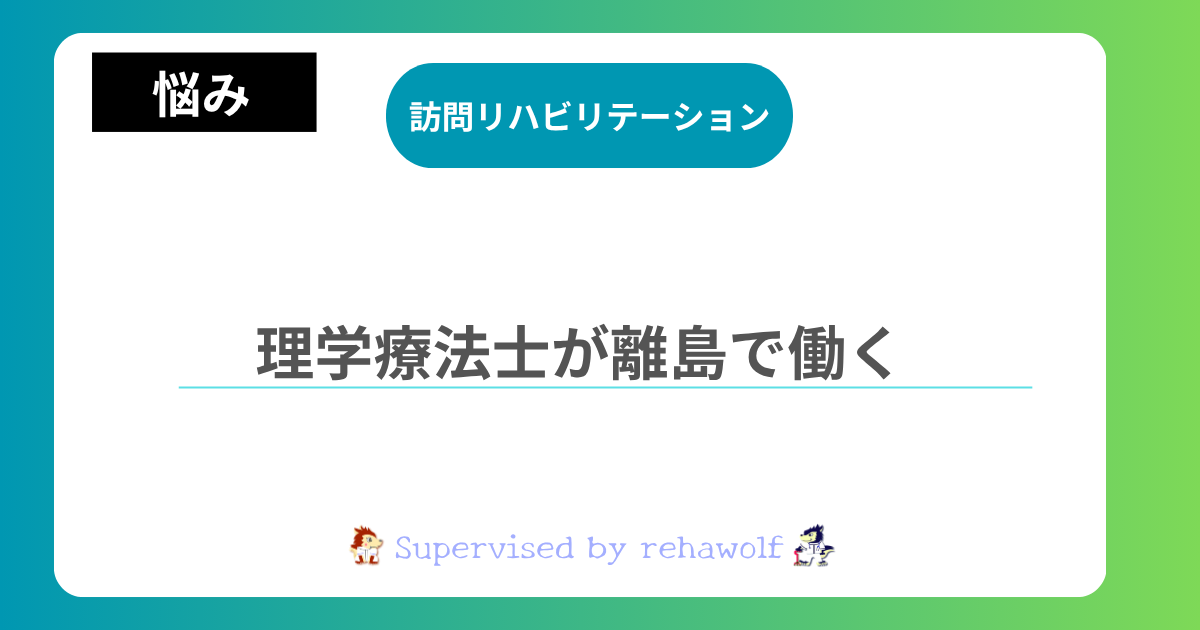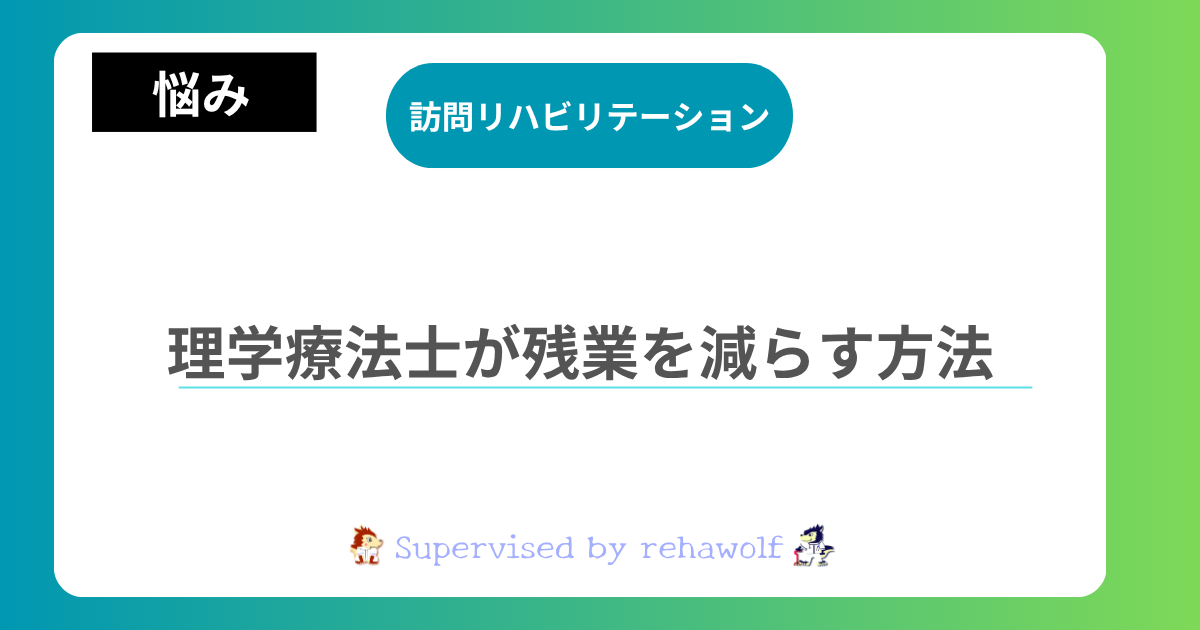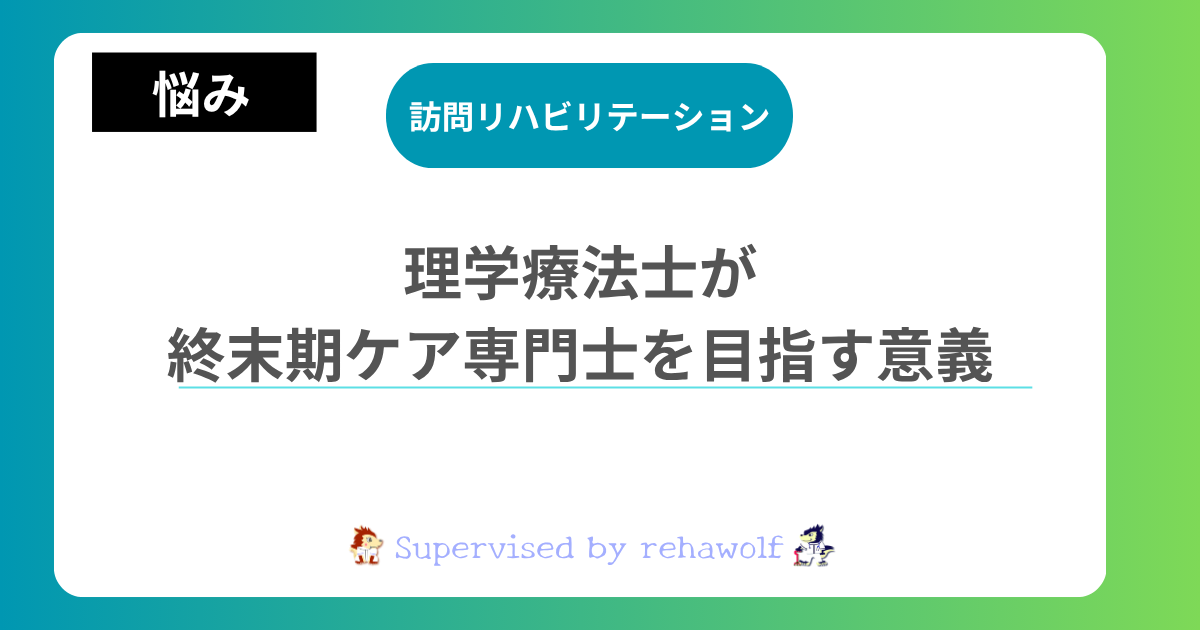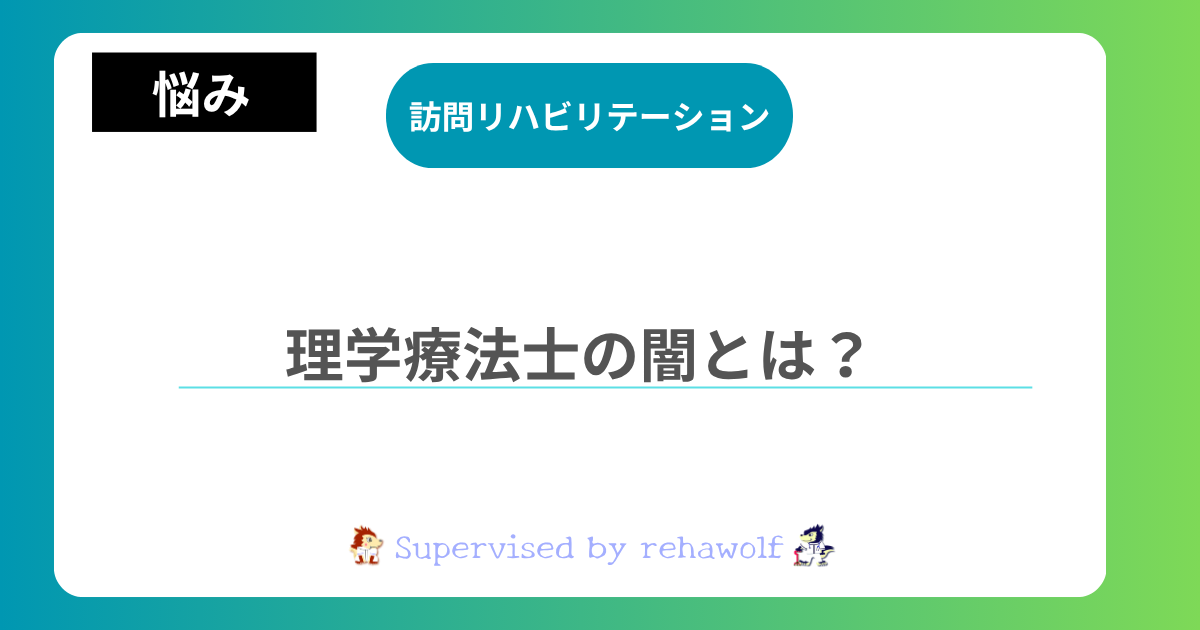訪問リハビリの人件費率とは?医療・介護事業運営に欠かせない指標
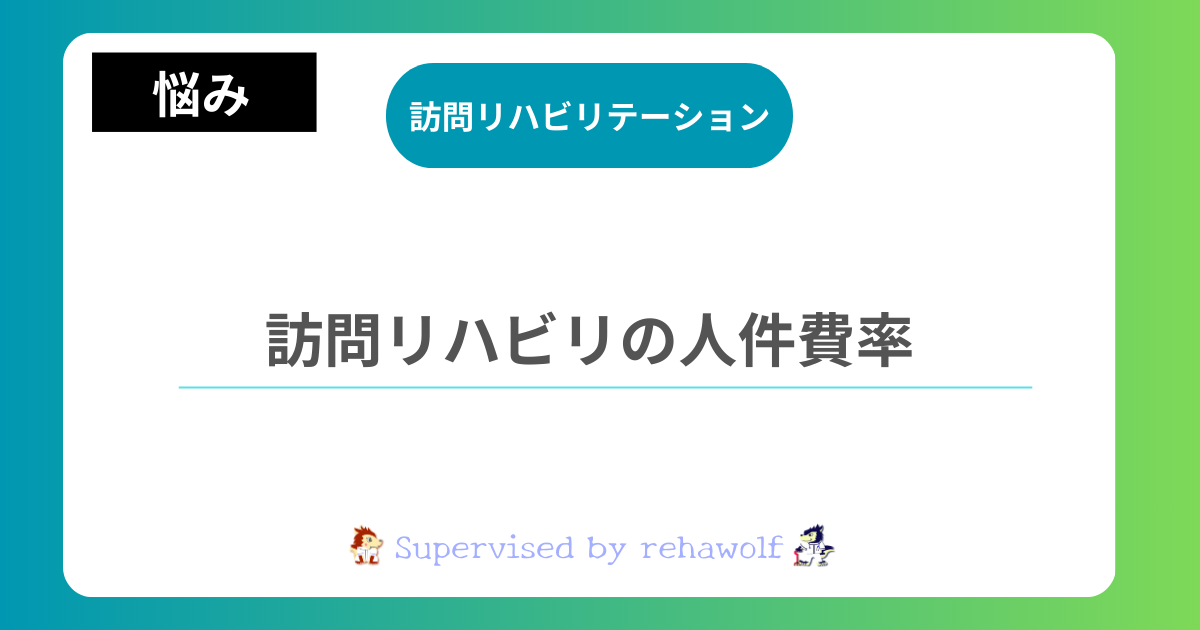
訪問リハビリテーションは、医療保険や介護保険を通じて自宅に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問し、在宅での生活機能向上を支援するサービスです。
その運営にあたって欠かせないのが「人件費率」という指標です。
人件費率とは、事業で得られる収益(売上)に対して人件費が占める割合を示したものです。
訪問リハビリは専門職の人件費が大きな割合を占めるため、この数値を把握することは経営の安定に直結します。
本記事では、訪問リハビリにおける人件費率の目安、算出方法、改善のポイント、他職種との比較まで詳しく解説します。
これから訪問リハ事業を立ち上げたい方や経営改善を検討している事業者の参考になる内容です。
訪問リハビリにおける人件費率の目安はどれくらいか?
訪問リハビリにおける人件費率は、一般的に 50%〜70%程度 が目安とされています。これは、収益の半分以上が人件費に使われていることを意味します。特に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といった国家資格者は給与水準が比較的高く、加えて訪問リハは1対1でのサービス提供が基本であるため、稼働時間に比例して人件費が膨らみやすい特徴があります。
一方で、訪問リハは医療・介護報酬で安定した収益が見込めるサービスでもあるため、人件費率が高いからといって必ずしも経営が不安定になるわけではありません。むしろ、人件費率がある程度高いということは専門職を十分に配置し、質の高いサービスを提供している証でもあります。しかし、人件費率が70%を超えて80%近くになると、収益が圧迫され、事業継続にリスクが生じるため注意が必要です。
人件費率の算出方法と具体例
人件費率の計算式はシンプルで、
人件費率(%)= 人件費 ÷ 売上高 × 100
で算出できます。
例えば、訪問リハビリ事業所の月間売上が500万円で、給与や賞与、社会保険料を含む人件費が300万円だった場合、
300万円 ÷ 500万円 × 100 = 60%
となります。この場合、人件費率は60%で、基準値の範囲内です。
ただし、注意すべきは「どこまでを人件費に含めるか」という点です。給与や賞与のほか、退職金積立、法定福利費(社会保険料や労働保険料)、交通費、研修費用を含めるかどうかで数字は変わります。経営判断のために人件費率を用いる際は、経費区分を明確にしておくことが重要です。
訪問リハビリの人件費率が高くなりやすい理由
訪問リハビリは、他の介護サービスに比べて人件費率が高くなる傾向があります。その理由は大きく以下の3つです。
1. 高度専門職によるマンツーマン対応
訪問リハビリでは、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が利用者一人ひとりにマンツーマンで対応します。介護職員による集団対応が可能なデイサービスと比べると、提供時間に対して必要な専門職数が多く、人件費がかかります。
2. 訪問業務に伴う移動時間の存在
利用者宅への訪問には移動時間が発生します。この時間は収益を生み出さないため、勤務時間に対する実稼働率が下がり、結果として人件費率が高くなります。効率的なスケジュール管理が不可欠です。
3. 人材確保の競争が激しい
理学療法士や作業療法士は需要が高く、特に都市部では採用競争が激化しています。そのため、給与水準を一定以上に設定しなければ人材が確保できず、必然的に人件費率が上昇します。
他の介護サービスとの人件費率比較
訪問リハビリだけでなく、介護業界全体の人件費率を比較すると特徴がより明確になります。
- 訪問リハビリ:50〜70%
- 訪問看護:50〜65%
- デイサービス:40〜55%
- 特養・老健などの施設系:35〜50%
このように、訪問リハビリはデイサービスや施設系に比べて人件費率が高い水準で推移します。これは「専門職による個別サービス」という性質を反映したものであり、事業運営上の特徴といえます。
人件費率を適正に保つための工夫
人件費率を下げすぎると人材流出やサービス低下につながるため、単純に削減するのではなく「適正水準でコントロールする」ことが大切です。そのために有効な工夫をいくつか紹介します。
稼働率の向上
訪問リハの利益率を左右する最大の要因は「稼働率」です。移動時間を短縮するように利用者宅を効率的にルート化し、1日の訪問件数を増やす工夫が必要です。キャンセル発生時の代替訪問の仕組みを整えることも有効です。
多職種連携による利用者増加
医師、ケアマネジャー、訪問看護師との連携を強化し、新規利用者の紹介を増やすことで稼働率を改善できます。特にリハビリは医師の指示が必要なため、医療機関との関係構築が重要です。
パート・非常勤の活用
フルタイム職員だけでなく、パートや非常勤スタッフを柔軟に配置することで、人件費を変動費化できます。利用者数の波に応じて調整できるため、固定費を抑えやすくなります。
ITシステム導入による効率化
訪問スケジュール管理、記録の電子化、経路最適化アプリなどを導入すれば、移動や事務作業にかかる時間を削減し、実働時間を増やせます。結果として人件費率の改善につながります。
人件費率だけにとらわれない経営の視点も大切
人件費率は重要な経営指標ですが、それだけに注目するのは危険です。質の高いリハビリサービスを提供し続けるためには、優秀な人材を確保し、適切な給与を支払う必要があります。人件費率を下げるために給与を削減すると、人材流出やモチベーション低下を招き、結果的にサービス低下や利用者減少につながります。
経営者は「人件費率を適正に保ちながら、質の高いサービスを維持する」というバランスを意識することが求められます。さらに、加算の活用や利用者単価の向上など「収益を増やす視点」もあわせて持つことが、持続可能な運営につながります。
まとめ
訪問リハビリにおける人件費率は、一般的に50〜70%程度が目安です。専門職によるマンツーマン対応、移動時間の存在、人材確保競争といった要因により、人件費率は高くなる傾向があります。しかし、それは同時に「質の高いサービスを提供している証」でもあります。
経営上は稼働率向上、システム導入、柔軟な人材配置などの工夫で適正な範囲に収めることが大切です。人件費率だけを下げるのではなく、収益拡大とサービス品質向上の両立を目指すことが、訪問リハビリ事業を長期的に安定させるポイントといえるでしょう。