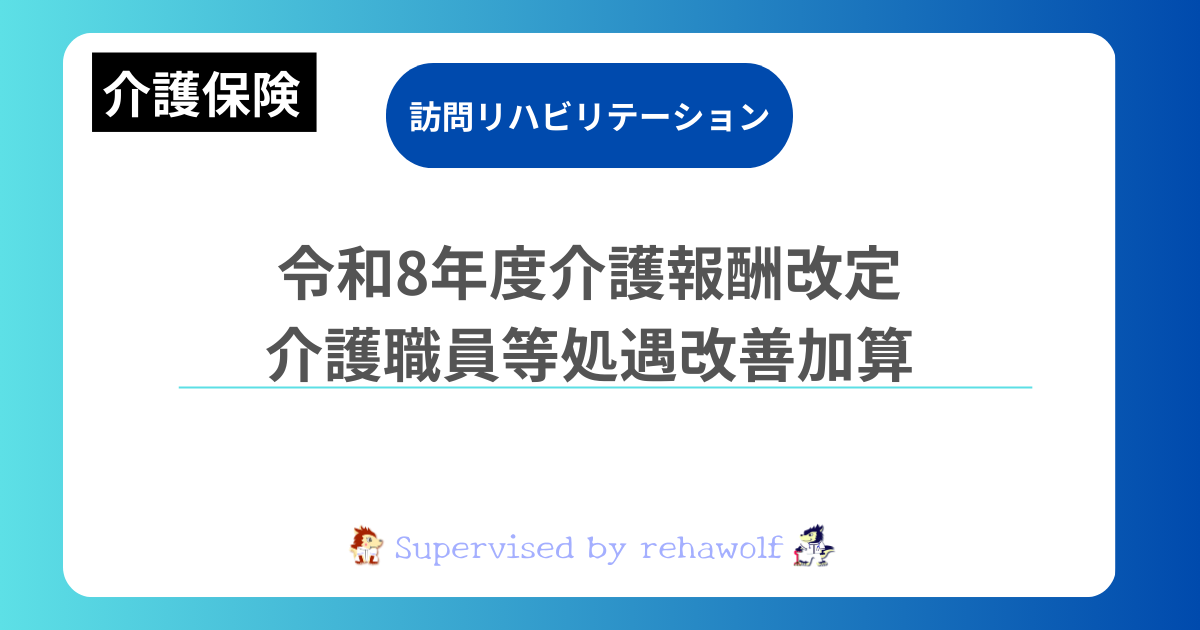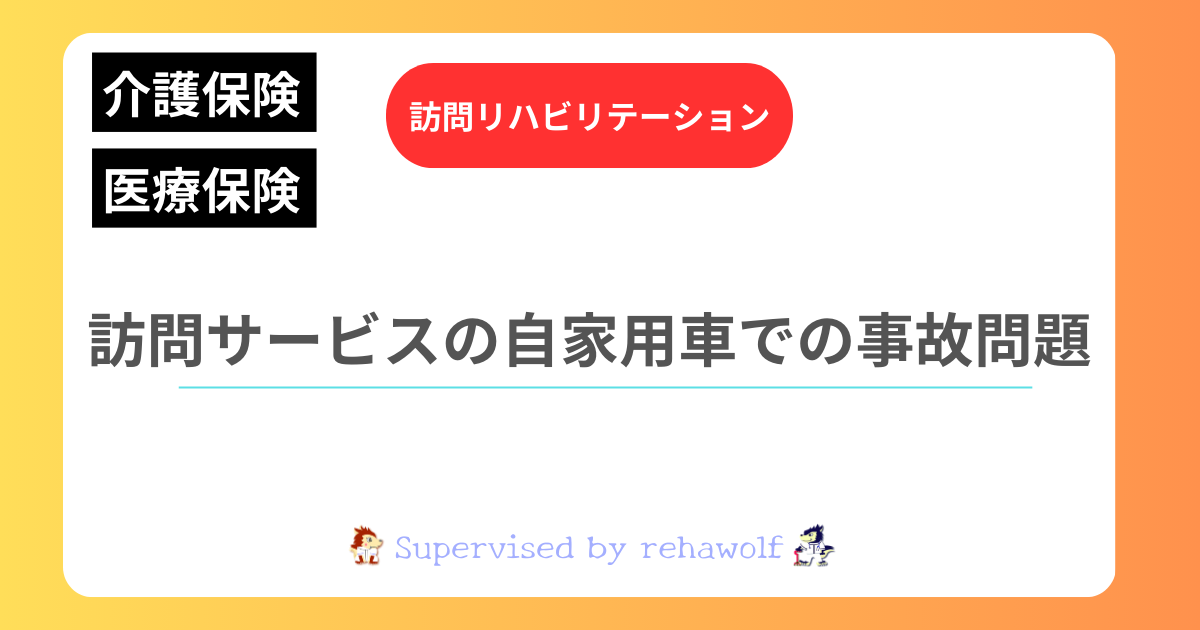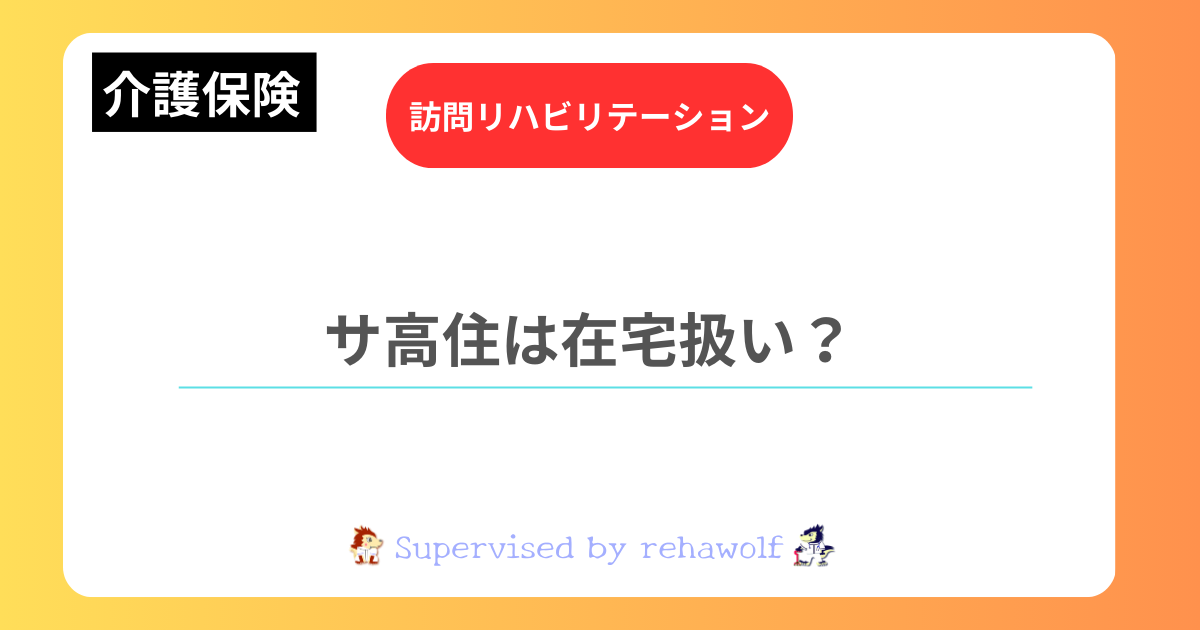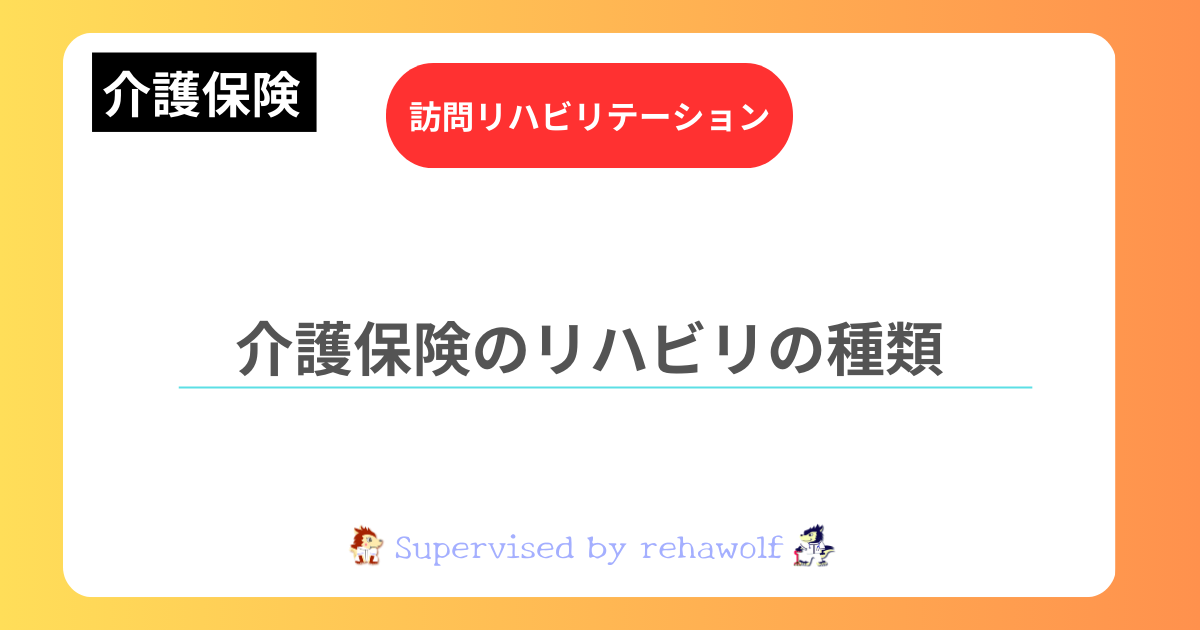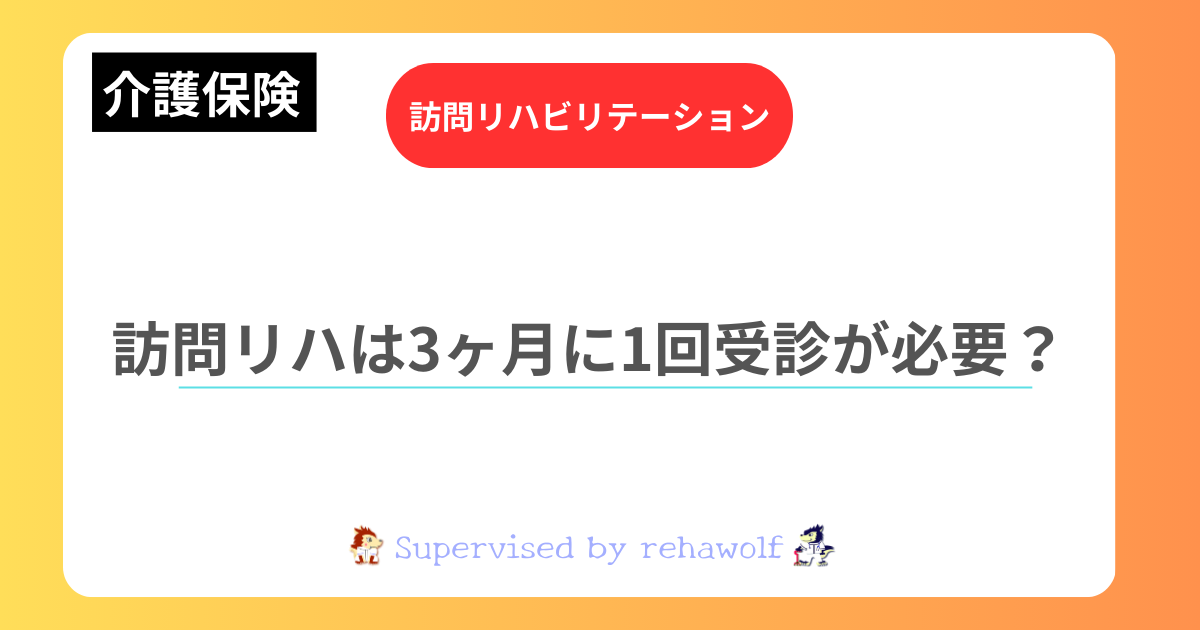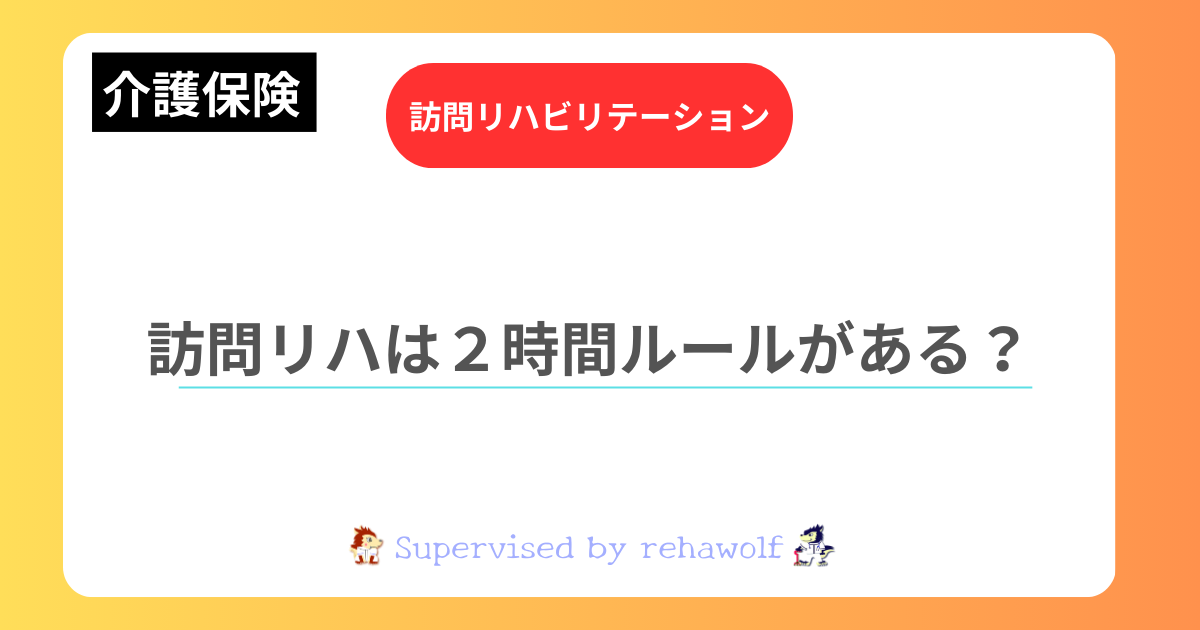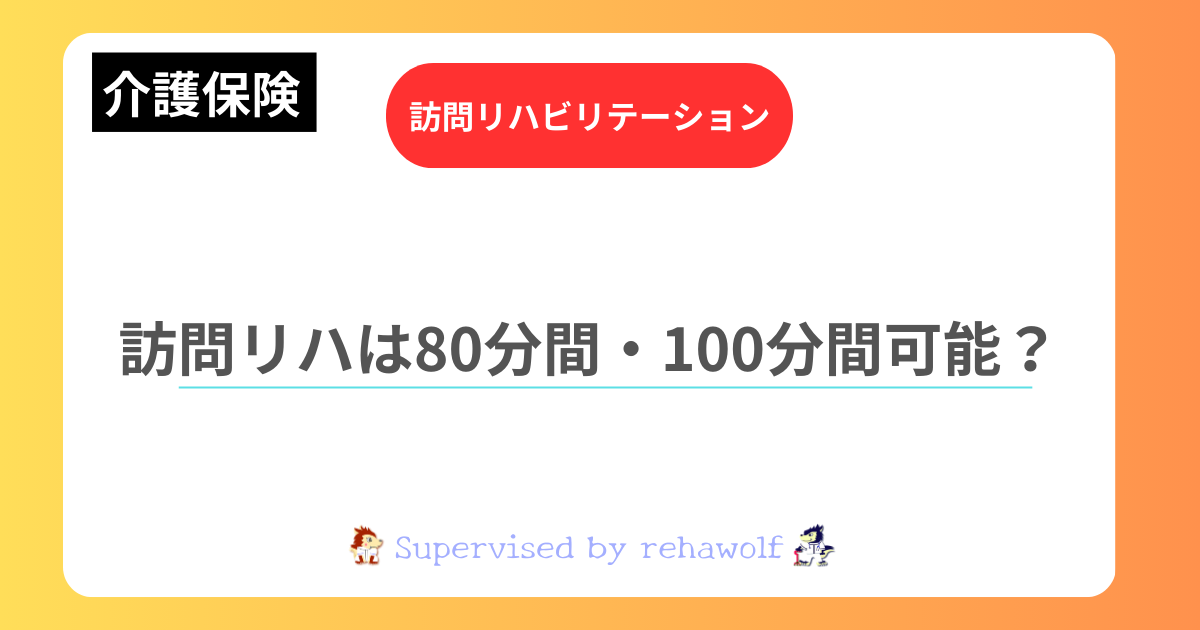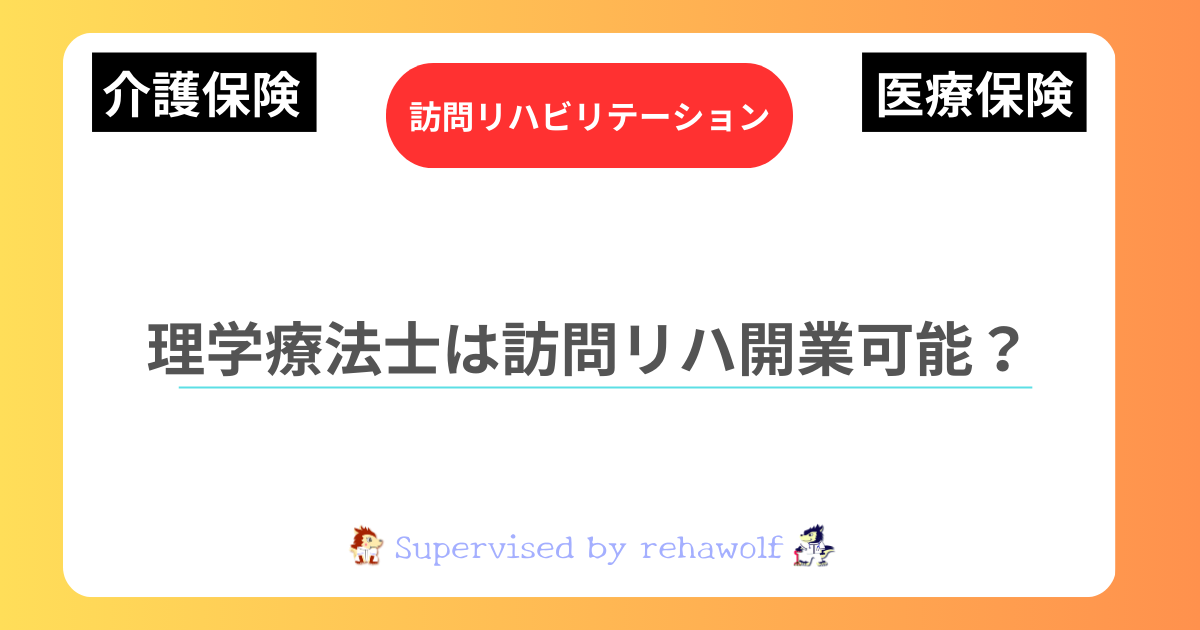訪問リハビリの報告書とは?頻度や書き方、書式についても解説
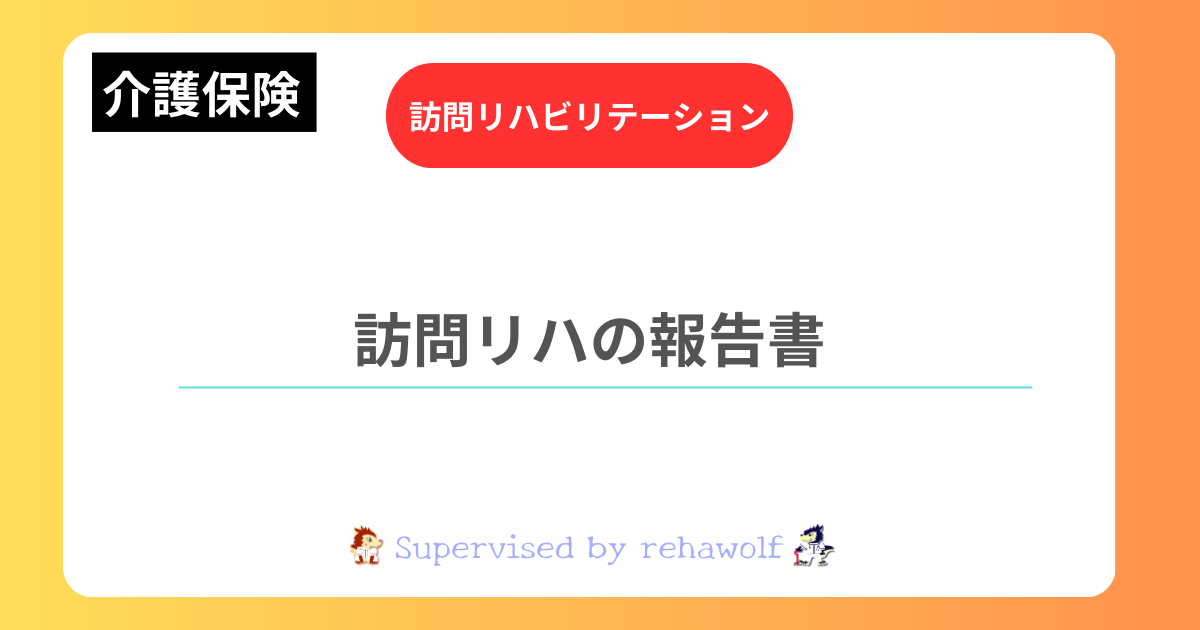
「訪問リハビリを始めたけど、報告書のルールってあるのかな?」
「訪問リハビリの報告書の頻度や書き方、書式について知りたい!」
このような疑問がある人もいるのではないでしょうか?
この記事では訪問リハビリの報告書について下記のことがわかります。
- 訪問リハビリの報告書の基本ルールがわかる
- 訪問リハビリの報告書の頻度や渡す相手がわかる
- 訪問リハビリの報告書の書式がわかる
- 訪問リハビリの書き方の例がわかる
この記事を読んで『訪問リハビリの報告書について』マスターしましょう!
訪問リハビリの報告書とは
訪問リハビリの報告書とは、利用者さんの訪問リハビリの様子をまとめて報告するものです。
訪問リハビリテーションの報告書は法的なルールはありません。
ルールはありませんが、他職種連携・他職種協働のためには報告書は必要な相手には渡すべきだと私は思います。
報告書を渡す相手は下記が代表的ですが、必要に応じて変更する必要があります。
・ケアマネジャー(介護支援専門員)
・主治医(かかりつけ医)
・事業所の医師
訪問リハビリの報告書はケアマネや主治医に渡す必要があるのか?
上述したように、訪問リハビリの報告書は法的なルールで義務化はされていません。
よって、ケアマネジャーにも主治医(かかりつけ医)にも渡す必要はありません。
ただし、訪問リハビリテーションはケアマネジャーが作成したケアプランの下にリハビリ計画書を作成して、提供しているわけですので、ケアプランを作成しているケアマネジャーには報告書を送ることをお勧めします。
また、情報提供を受けている主治医(かかりつけ医)においても診療情報提供をいただいているわけですので、その医師には報告書を送る必要があると私は思います。
法的なルールがあるから作成するのではなく、利用者さんにとって良いことは何なのかという視点で判断すると良いかと思います。
訪問リハビリの報告書の頻度
訪問リハビリテーションの報告書の頻度についてはは、月一回程度が良いと思います。
また、それ以外に必要に応じて電話やFAXなどでのリアルタイムな情報提供は必要だと思いますが、定期的な報告書については月一回くらいが妥当ではないでしょうか。
訪問リハビリの報告書の書き方(記入例)
訪問リハビリの報告書は以下の点に気をつけて書きましょう。
・簡潔に記載する
・リハビリ職だけわかる専門用語は使用しない
・毎月同じことを書かない。(同じことを書くくらいなら変化なしなどの記載の方が良い)
・ケアマネジャーや医師の相手の気持ちに立って記載する
・月の出来事を時系列に並べて書く
・曖昧な表現はしない
・事実だけ書く
・「ですます調」or「である調」に統一する
・誤字脱字を確認する
訪問リハビリの報告書の書式
訪問リハビリの報告書の書式は規定のものはありません。
下記のような項目を記載してオリジナルで作成することをおすすめします。
1. 基本情報
- 利用者氏名
- 生年月日、年齢、性別
- 主治医名およびケアマネジャー名
- 報告対象期間(例:〇年〇月分)
2. 訪問リハビリの目的と目標
- 現在のリハビリの目的
- 短期および長期目標
3. 利用者の状態、リハビリの状況、評価など
- 健康状態の変化(体調の良否、疾患の進行具合など)
- 精神状態や意欲(例:リハビリへの参加意欲の有無)
- 家庭や生活環境の変化(介護状況、支援体制など)
- リハビリの実施状況
- 利用者の状態や動作能力の変化
- 前回の目標に対する達成度
- 利用者や家族の満足度や意見
- 利用者が抱える課題(体力低下、家族の負担増など)
- 環境的・心理的な障害
4. 特記事項
- 特に留意すべき事項(例:転倒リスクの増加、症状の急変の可能性)
- 緊急対応や医師への報告事項があれば記載
5. 作成者情報
- 担当者名
- 職種
- 所属(訪問リハビリ事業所名)
- 連絡先