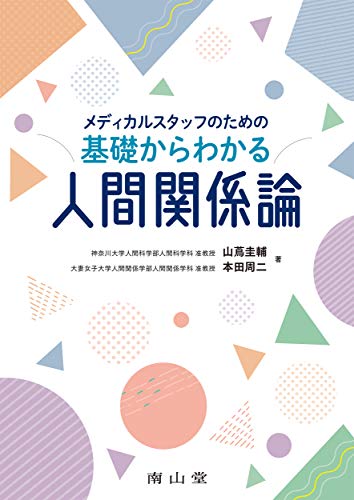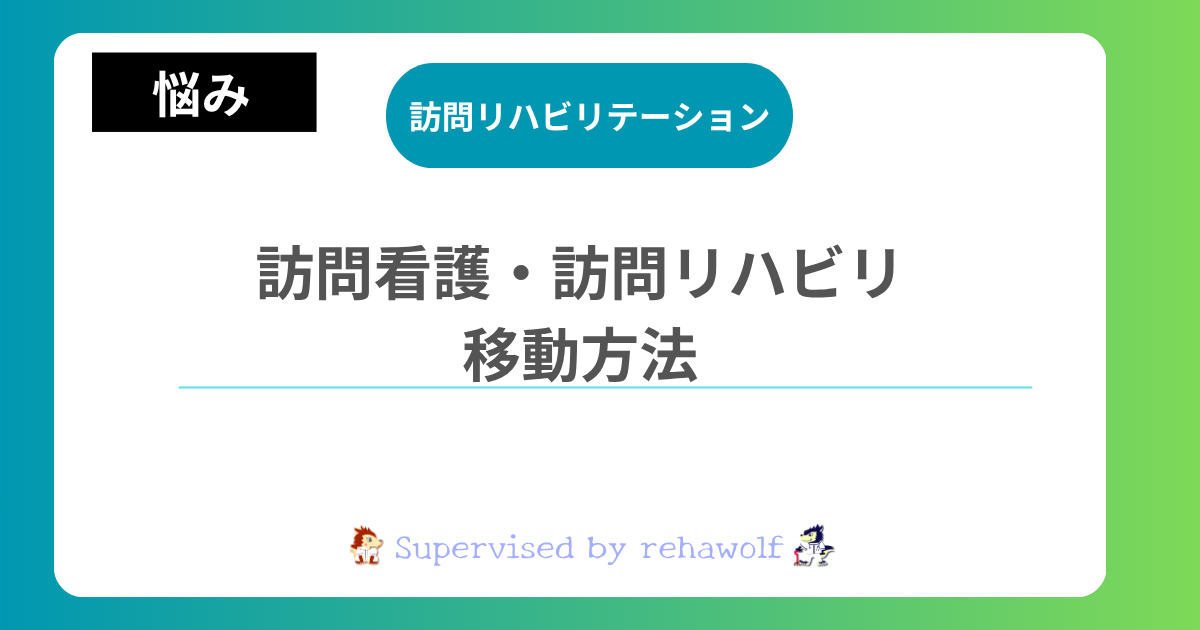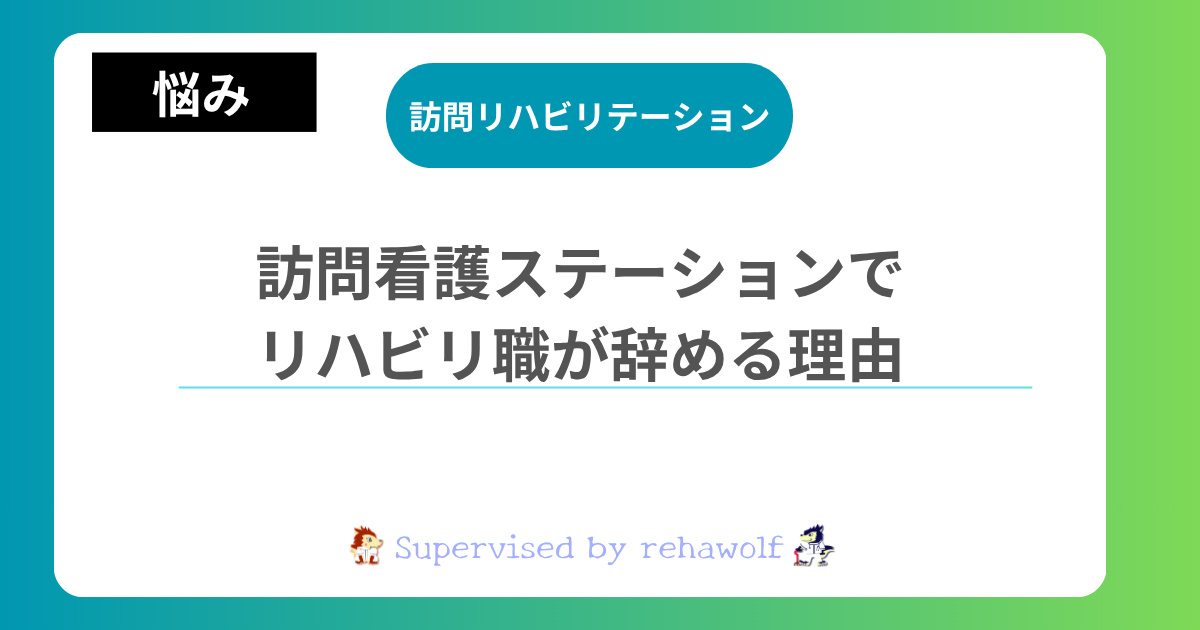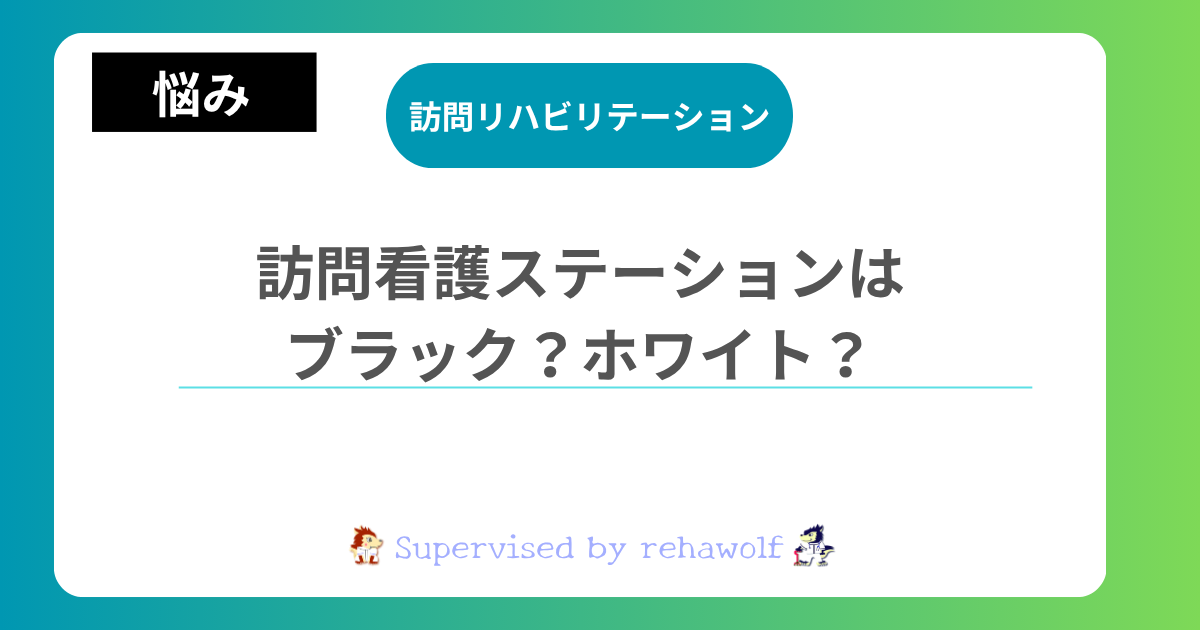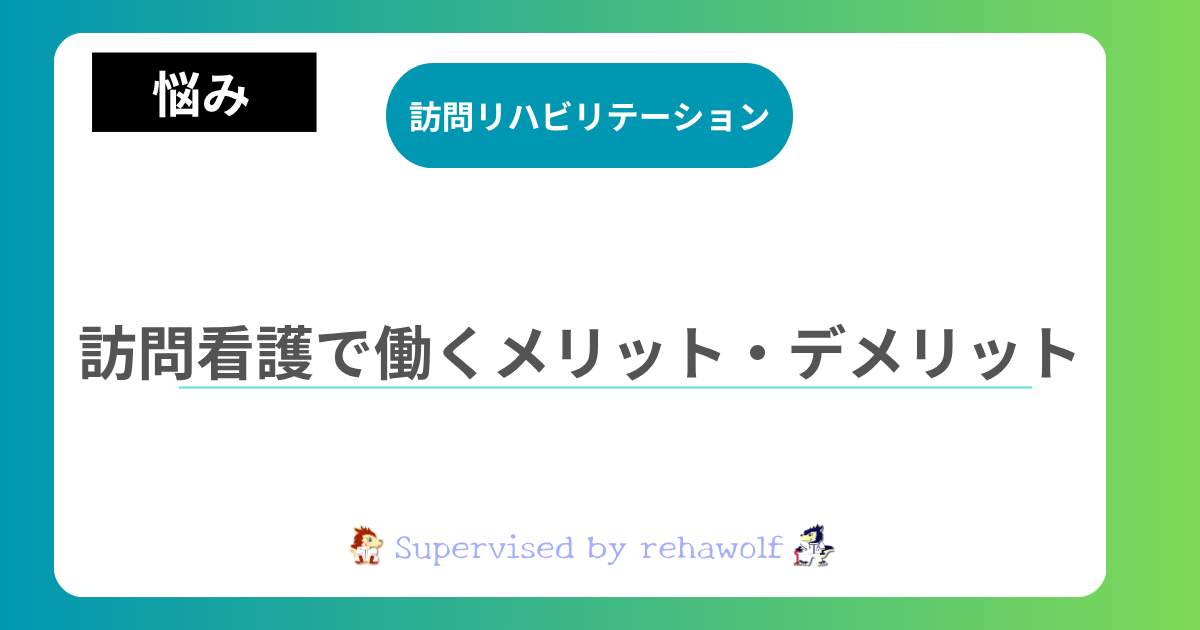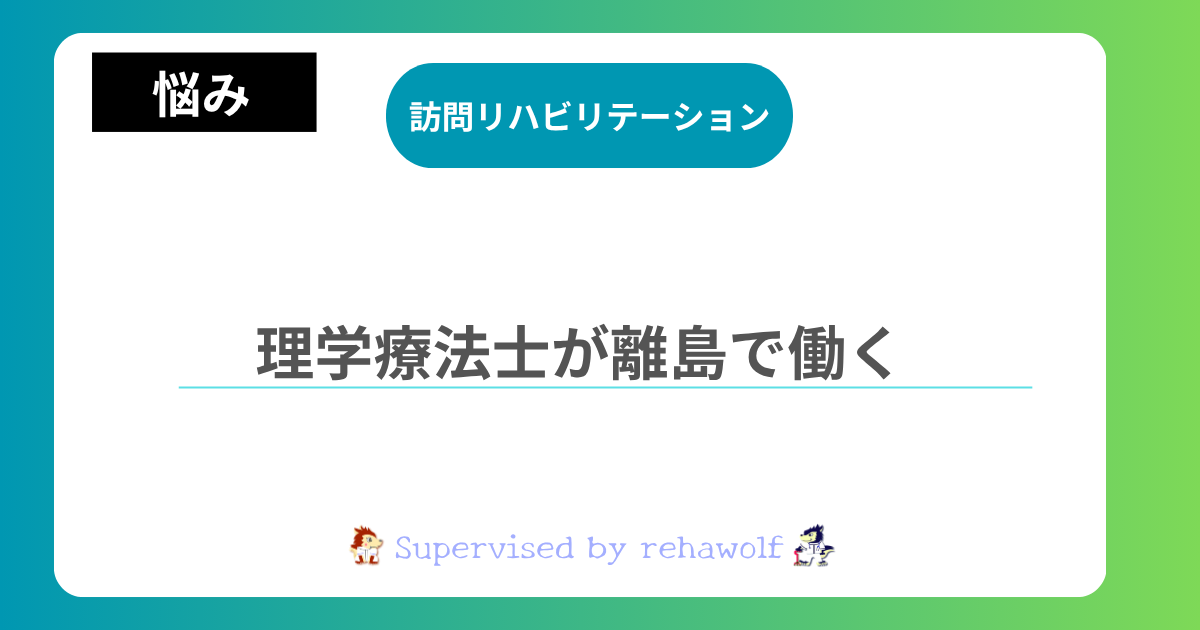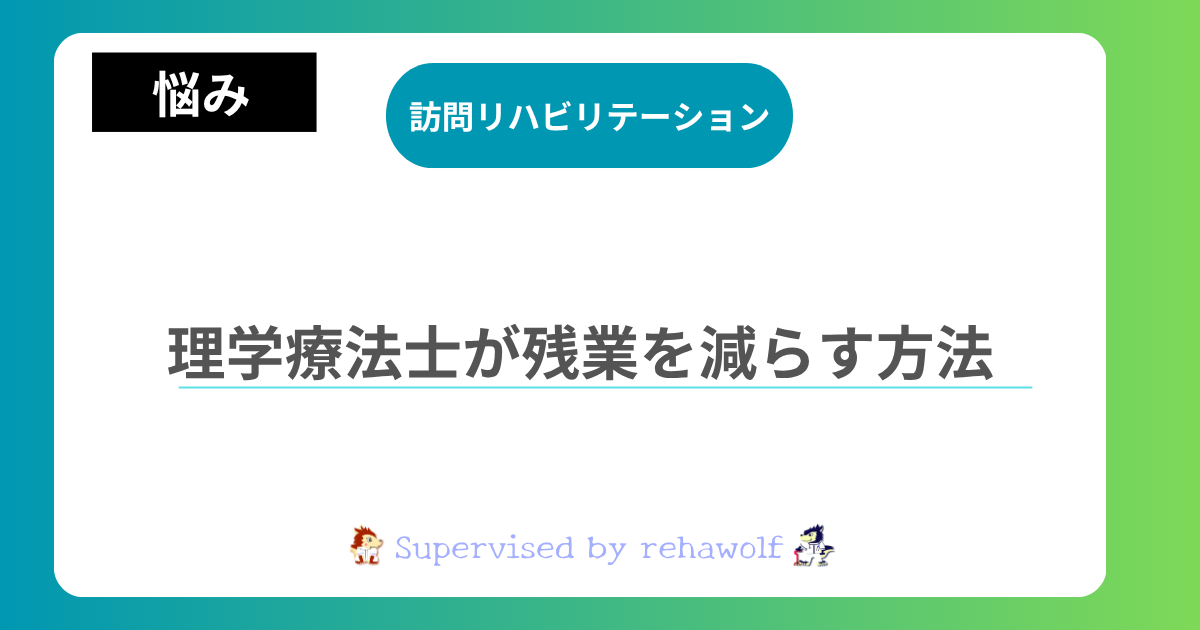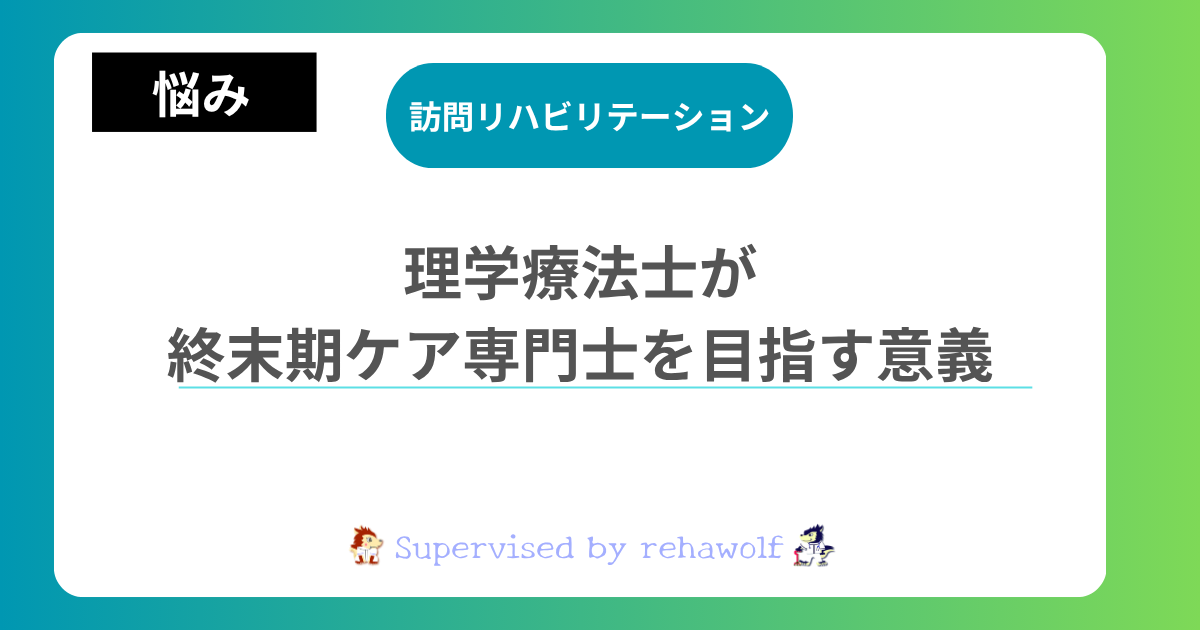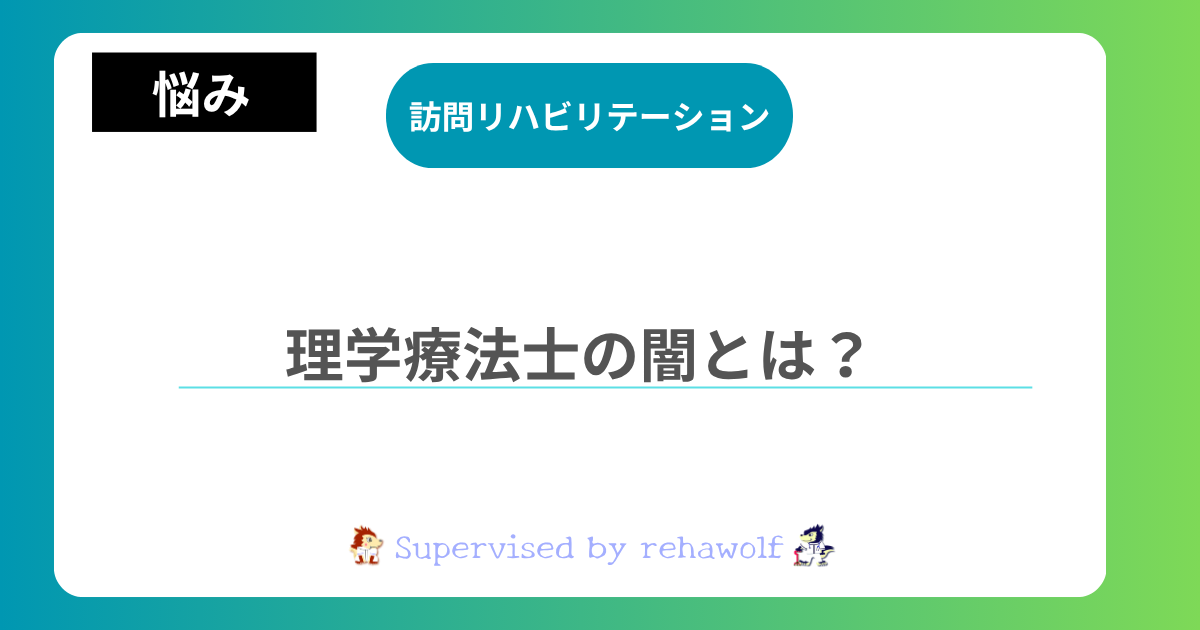理学療法士の人間関係は大変?よくある悩みと解決法を解説
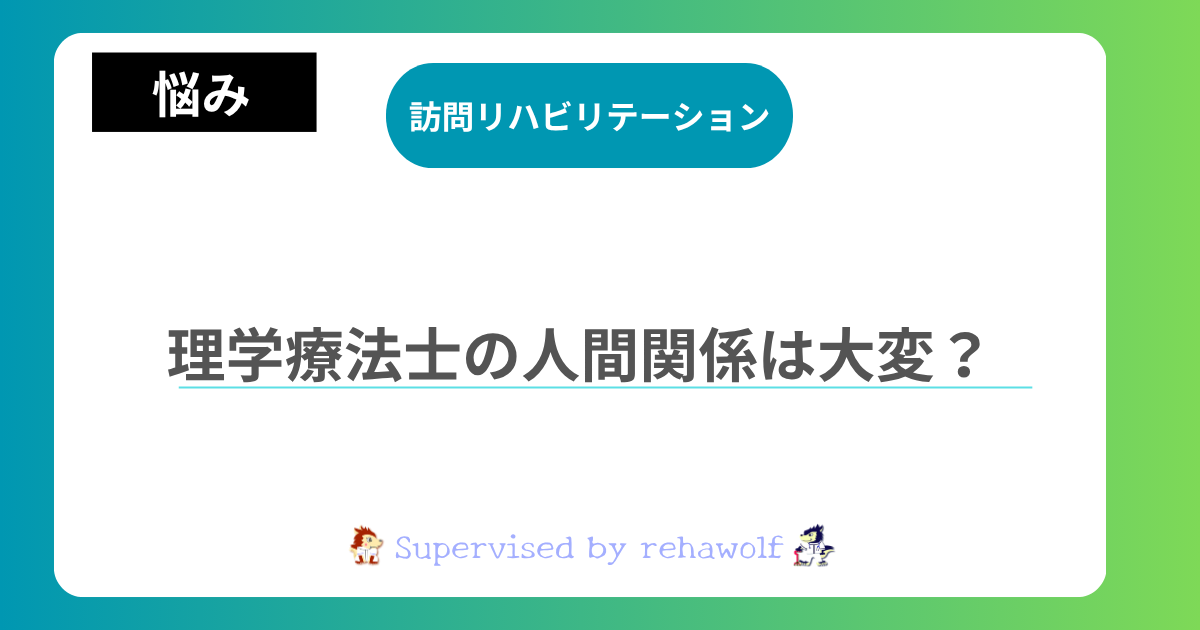
理学療法士(PT)として働くうえで避けて通れないのが「職場の人間関係」です。
患者さんや利用者との関わりだけでなく、看護師や介護職、医師など多職種との連携が必須のため、人間関係に悩む理学療法士は少なくありません。
実際に「仕事内容より人間関係の方がきつい」と感じて転職を考える人もいるほどです。
この記事では、理学療法士が抱えやすい人間関係の悩みとその原因、解決のヒントをわかりやすく紹介します。
理学療法士の職場でよくある人間関係の悩み
1. 上司・先輩との関係
新人PTにとって最もストレスになりやすいのが先輩や上司との関係です。「指導が厳しすぎる」「質問しづらい雰囲気」「期待に応えられない」と感じ、萎縮してしまうケースもあります。
2. 他職種との連携
理学療法士は医師、看護師、介護職、管理栄養士などと日常的に連携します。立場や考え方の違いから意見がぶつかり、「リハの必要性を理解してもらえない」「看護師と役割の境界が曖昧」といった摩擦が起きやすいのです。
3. 同僚との競争意識
同期や同年代のPTと比べて「自分の評価が低い」「症例数で差を感じる」など、比較からくる人間関係のギクシャクもあります。
4. 患者・家族との関わり
患者さんやその家族とのコミュニケーションに悩むことも。「リハビリの成果を求められすぎる」「説明がうまく伝わらない」といった場面でストレスを感じます。
なぜ理学療法士は人間関係に悩みやすいのか
- チーム医療での役割の違い:理学療法士の立場や意見が軽視されることもある
- 上下関係の厳しさ:医療機関は縦社会の傾向が強い
- 成果が見えにくい:患者の回復は時間がかかるため、他職種から理解されにくいことがある
- 人と接する時間が多い:患者・家族・職員など常に誰かと関わるため、ストレスが蓄積しやすい
人間関係の悩みを軽減する方法
1. コミュニケーション力を高める
相手の立場を理解し、話をよく聞くことは人間関係の基本です。特に多職種連携では「専門用語をかみ砕いて説明する力」が求められます。
2. 信頼関係を築く
小さな約束を守る、報連相を欠かさないなど、日常の積み重ねが信頼を作ります。信頼があれば多少の意見の違いも乗り越えやすくなります。
3. 比較しすぎない
同期や同僚と比較して焦るのではなく、自分の成長を振り返ることが大切です。患者さんの変化や自分ができるようになったことに目を向けましょう。
4. 外部のコミュニティを持つ
職場以外の勉強会やオンラインコミュニティに参加すると、視野が広がり、悩みを共有できる仲間が見つかります。
5. 無理をしない働き方を選ぶ
どうしても人間関係が辛い場合は、転職や勤務形態の変更も選択肢の一つです。訪問リハやデイサービスは病院より人間関係のストレスが少ない場合もあります。
人間関係の悩みがキャリアに与える影響
人間関係のストレスは、離職や燃え尽き症候群につながるリスクがあります。
しかし逆に、円滑な人間関係を築ければ、仕事のやりがいや成長にも直結します。
理学療法士は患者や家族だけでなく多職種と協力してこそ成果が出る職業のため、人間関係スキルは専門性と同じくらい重要です。
まとめ
理学療法士の職場はチーム医療・多職種連携が基本であり、人間関係に悩みやすい環境でもあります。上司・同僚・他職種・患者家族との関係に悩むのは珍しくありませんが、コミュニケーション力や信頼関係の構築で改善できる部分も多くあります。
それでも辛い場合は働き方を変える選択もあり、訪問リハや介護施設など人間関係のストレスが少ない現場に転職する人も増えています。
理学療法士として長く働くためには「専門技術」だけでなく「人間関係を築く力」も欠かせません。
悩みを一人で抱え込まず、解決策を探してみましょう。