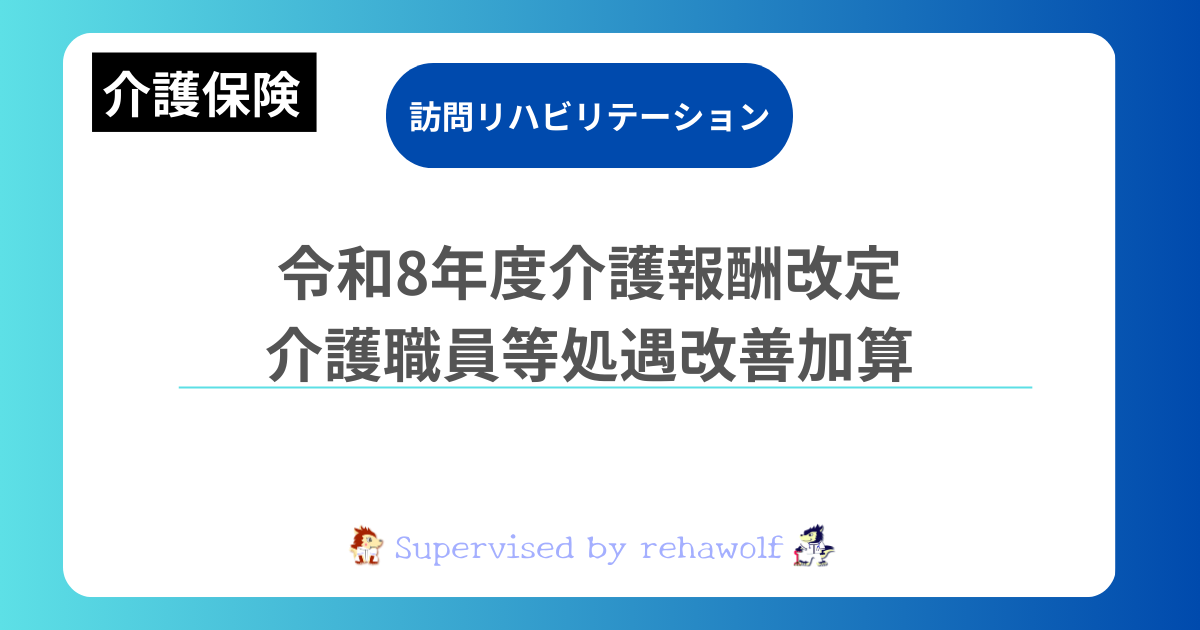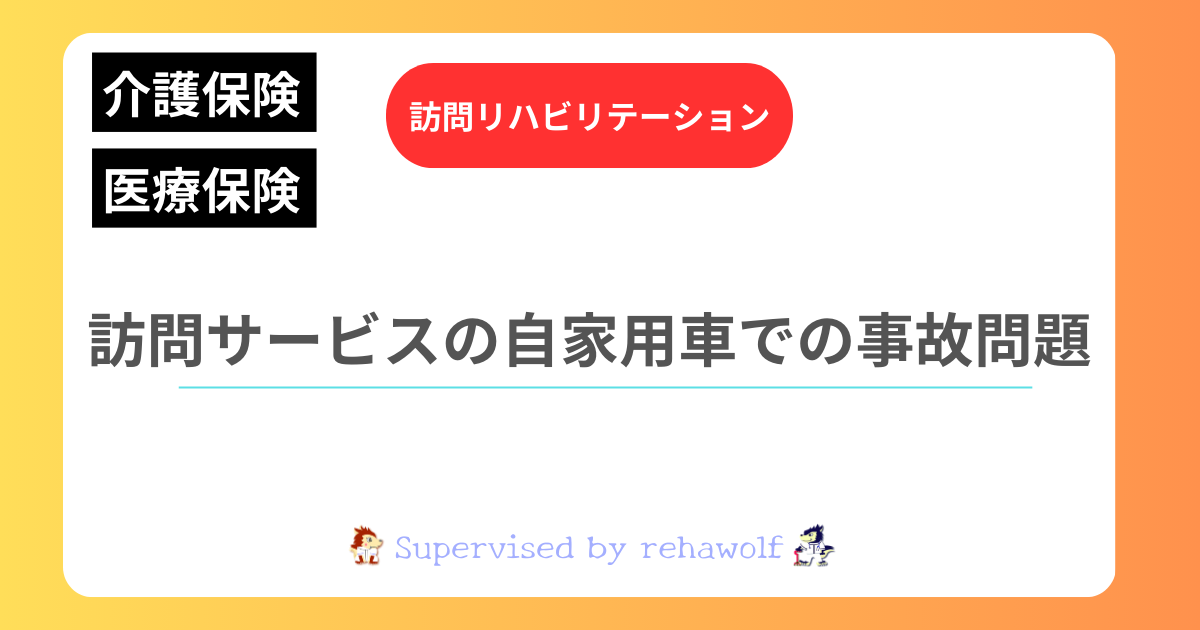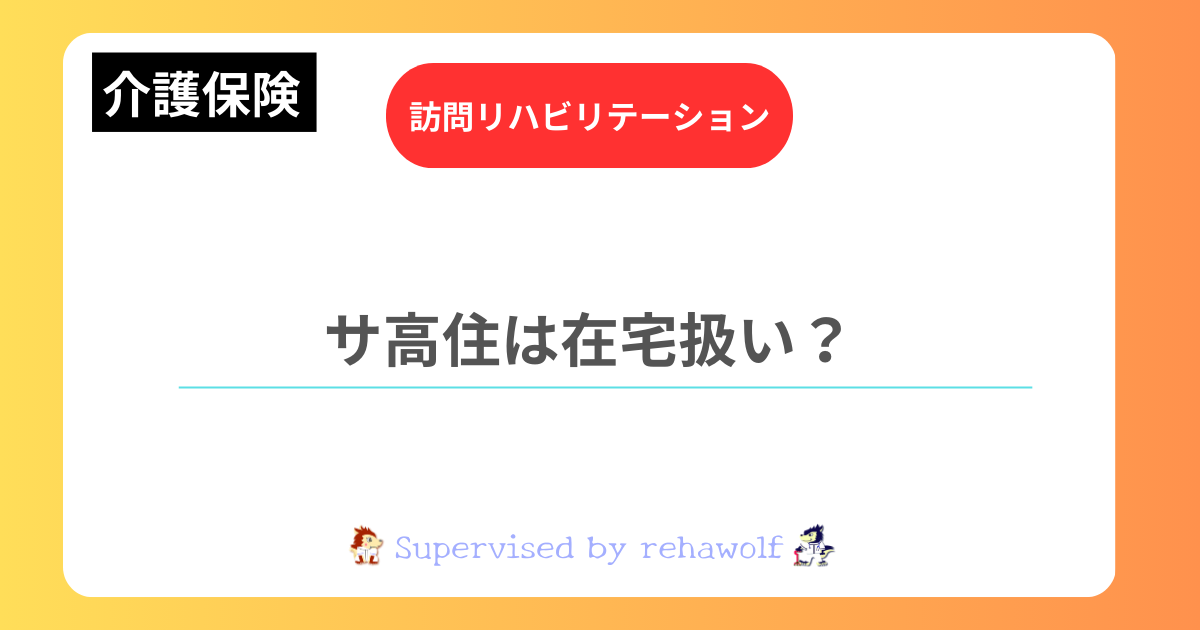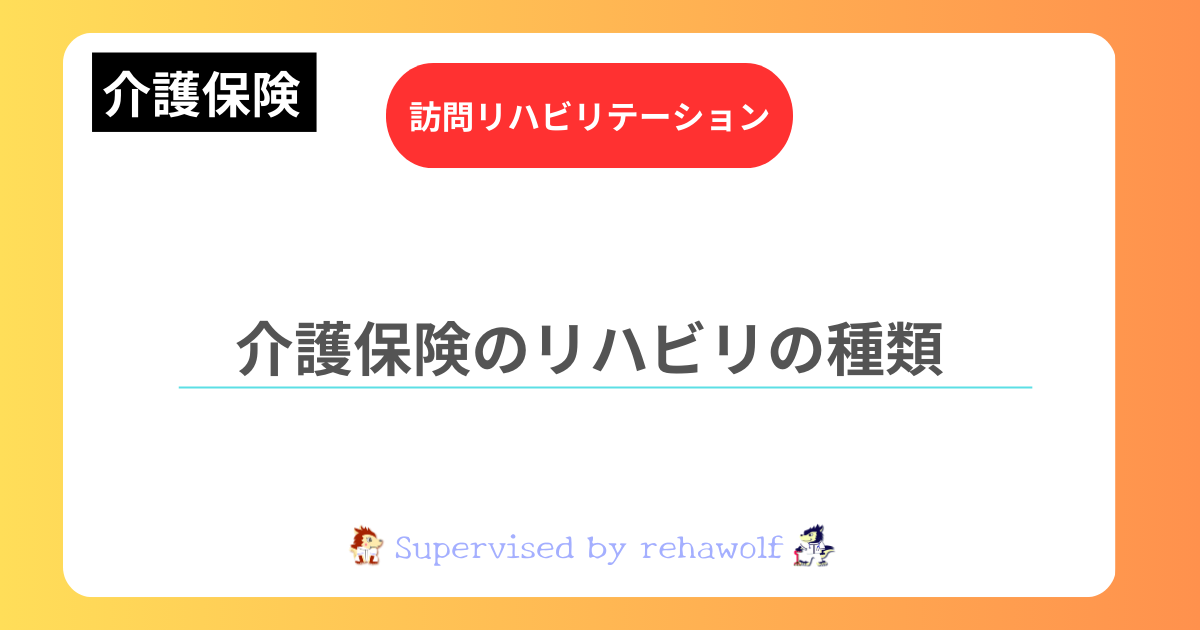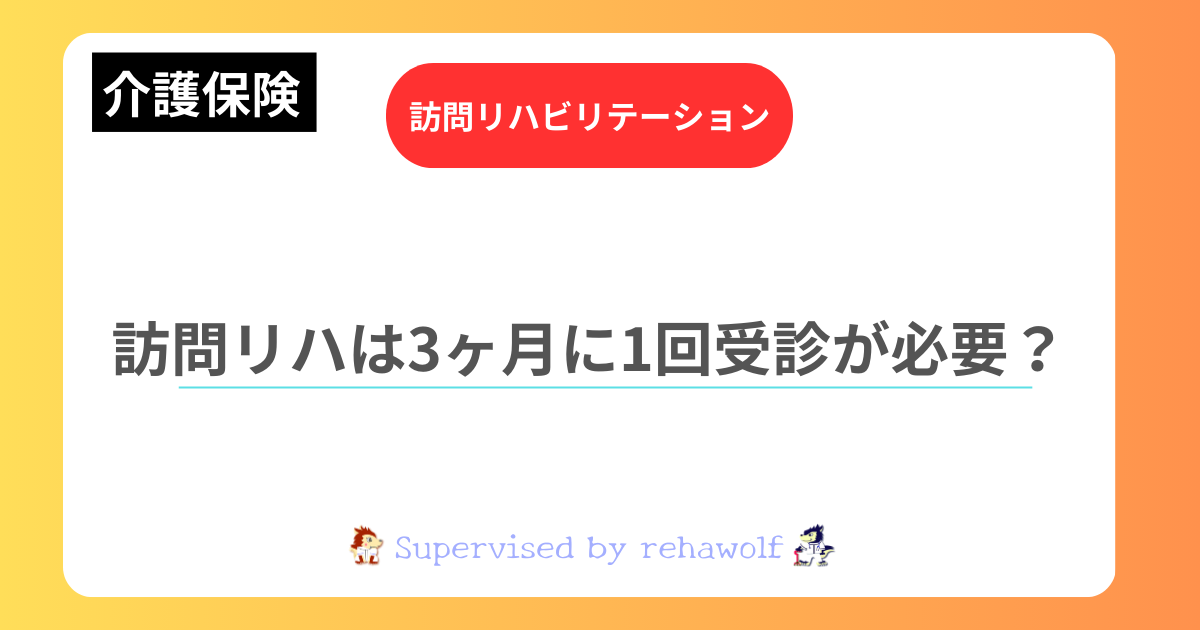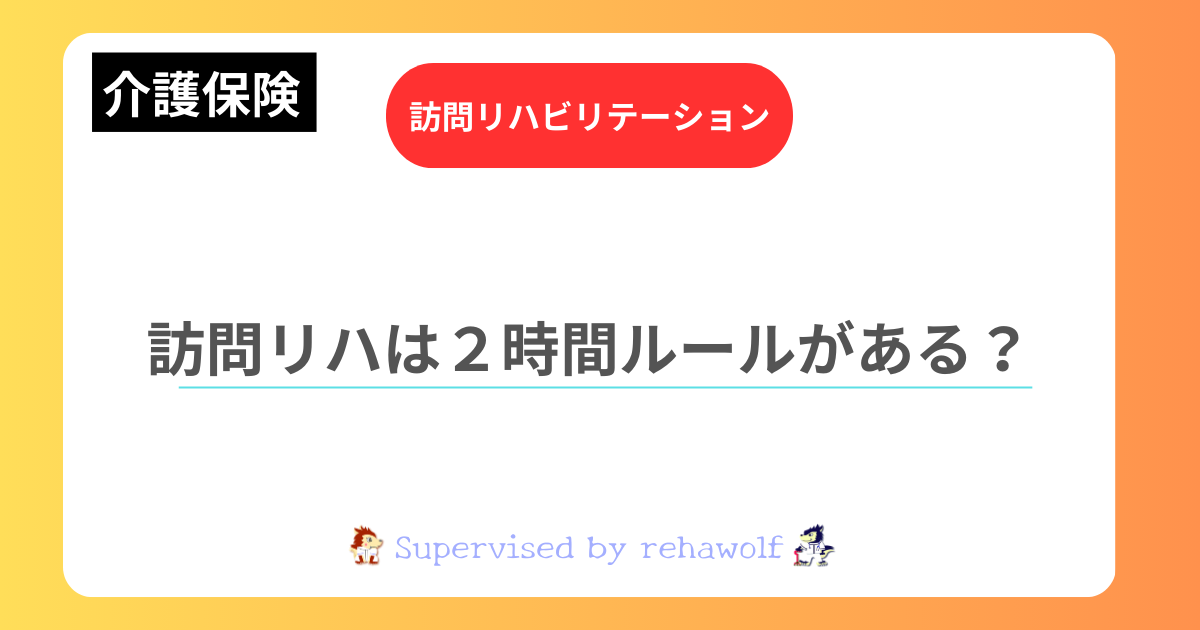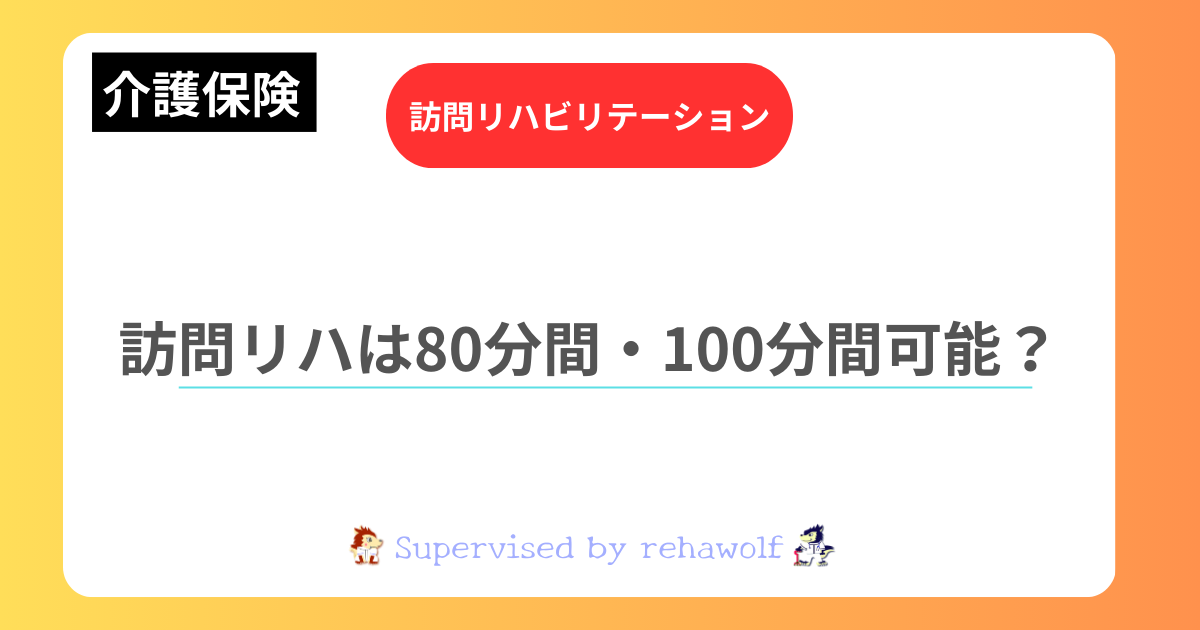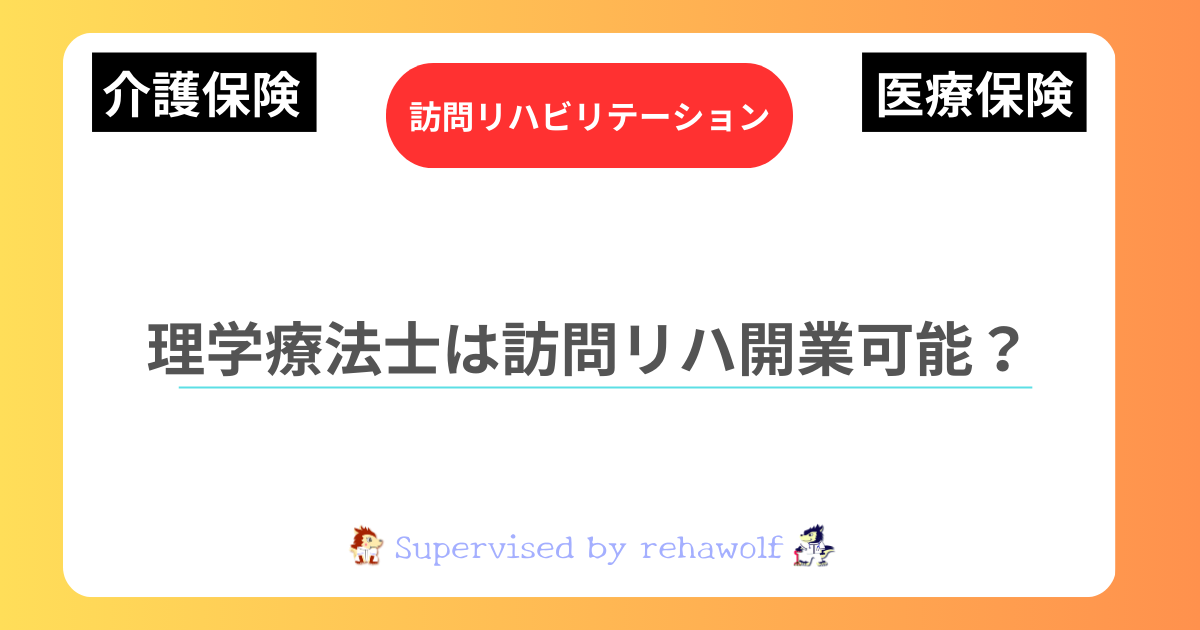訪問リハビリの計画書の作成頻度はどのくらい?制度を元に解説
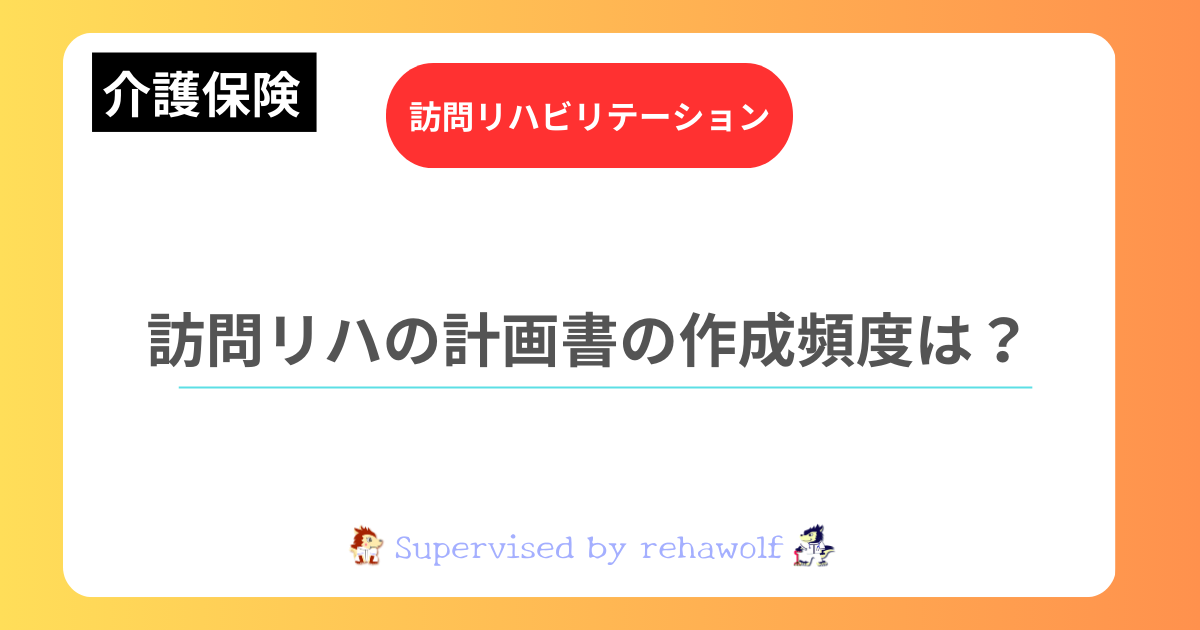
「訪問リハビリの計画書の作成頻度はどのくらいおきに作れば良いの?」
このような疑問を解決できる記事です。
この記事を読めば下記のことがわかるようになります。
- 訪問リハビリの計画書の作成頻度
この記事を読むと訪問リハビリの計画書の作成頻度についてマスターできます。
ぜひ、最後まで読んでください。
訪問リハビリの計画書の作成頻度
訪問リハビリの計画書の作成頻度は下記の通りです。
この計画書は簡単なもので良い
ここの時点で完成させる
サービス提供前に必ずリハビリ計画書を作成しましょう!
最初の計画書は原案なのでそこまでしっかり作成しなくても良いです。
運営指導では最初のサービス提供前に計画書を作り、同意を得ているかをチェックされます。
なので、計画書作成日→同意した日→初回サービス提供日という時系列にする必要があります。
この時系列であれば良いので、『計画書作成日』と『同意した日』と『初回サービス提供日』が同日でも構いません。
訪問リハビリの計画書の作成頻度の根拠は下記の通りです。
サービス開始時におけるアセスメント・評価、計画、説明・同意について
関連スタッフ毎にアセスメントとそれに基づく評価を行い、多職種協働でサービス開始時カンファレンスを開催し、速やかにリハビリテーション計画の原案を作成する。リハビリテーション計画の原案については、利用者又はその家族へ説明し同意を得る。
〜略〜サービス開始後二週間以内のアセスメント・評価、計画、説明・同意について
リハビリテーション実施計画の原案に基づいたリハビリテーションやケアを実施しながら、サービス開始からおおむね二週間以内に以下のアからカまでの項目を実施する。
〜略〜アからオまでの過程はおおむね3月毎に繰り返し、内容に関して見直すこととする。また、利用者の心身の状態変化等により、必要と認められる場合は速やかに見直すこととする。管理者及び関連スタッフは、これらのプロセスを繰り返し行うことによる継続的なサービスの質の向上に努める。
出典)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について
上記に追加して、下記の場合も計画書を作成する必要があります。
1)ケアプランが変更になった場合
2)短期集中リハビリテーション実施加算算定時
3)要支援から要介護になった場合
4)要介護から要支援になった場合
5)介護度が変わった時
制度をしっかりと理解して計画書を作成してサービス提供をしましょう!